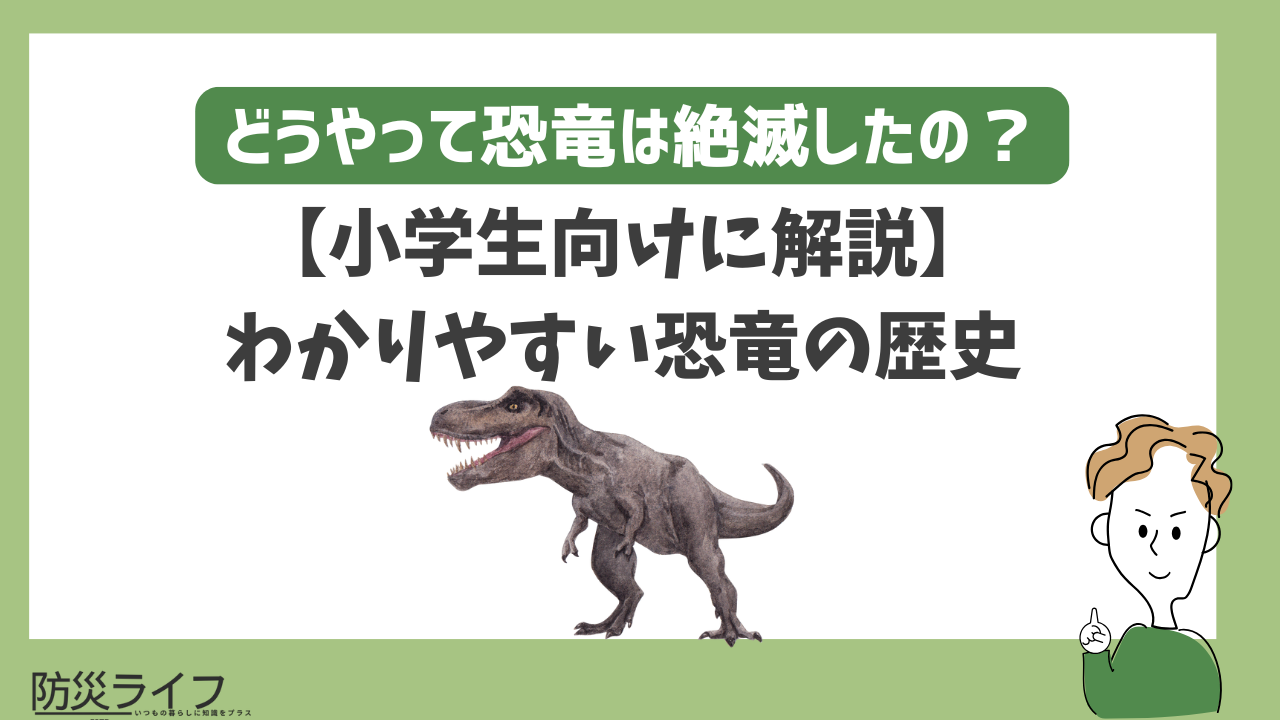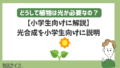恐竜(きょうりゅう)は、むかしの地球で大さかりした生き物です。 ところが、約6600万年前に多くの恐竜が地球からいなくなりました(絶滅)。
では、なぜそんなことが起きたのでしょうか? そのとき空・海・大地で何が起き、どんな生き物が生きのこったのかを、やさしい言葉と図のかわりになる表でくわしく説明します。小学生でも読み進めやすい内容にまとめ、自由研究にも使える観察・学びのコツも紹介します。
1.恐竜ってどんな生き物?入門ガイド
恐竜が生きていた時代と広がり
恐竜があらわれたのは三畳紀(さんじょうき)で、ジュラ紀(じゅらき)、白亜紀(はくあき)と続き、約1億6000万年のあいだ地球のあちこちでくらしました。森、平原、砂漠、川べり、海に近い地域まで、環境に合わせて進化し、多くの種類が生まれました。時代の中で地形や気候も変わり、恐竜はそれに体の作りを合わせていったのです。
| 時代 | はじまりのおよその時代 | おもなできごと・代表的な恐竜 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 三畳紀 | 約2億3000万年前〜 | 小型の恐竜があらわれる/二足歩行が目立つ | 恐竜時代のスタート、いろいろな形の先祖が登場 |
| ジュラ紀 | 約2億年前〜 | ブラキオサウルス、ステゴサウルスなど | 大型化と多よう化が進み、群れで行動する種も |
| 白亜紀 | 約1億4500万年前〜 | ティラノサウルス、トリケラトプスなど | 花の植物が広がる/時代の終わりに大絶滅 |
さらにくわしく見ると、時代ごとに食べ物(草・肉)や歯の形、足の長さ、すむ場所に違いがありました。下の表は、くらしの違いを簡単にまとめたものです。
| くらしのタイプ | 代表例 | 食べ物 | 特徴 | すみ場所の例 |
|---|---|---|---|---|
| 草食 | トリケラトプス、ブラキオサウルス | 草・葉・木の芽 | かたい草を切るくちばしや広い奥歯 | 森、川べり、広い平原 |
| 肉食 | ティラノサウルス、ヴェロキラプトル | 他の生き物 | するどい歯・つよいあご・速い足 | 平原、森のへり |
| 杂食 | 小型恐竜の一部 | 草+小動物+実 | 何でも食べて生きのびる | 森、低木地帯 |
体の大きさと形のちがい
ブラキオサウルスのようなとても大きい草食、ティラノサウルスのような力の強い肉食、トリケラトプスのように角をもつ草食など、くらし方に合わせた体の形をしていました。速く走る足、ものをつかむ手、かたいよろいのような板など、体はまるで道具のセットのようです。体のつくりとくらしの関係は、化石の歯・骨・足あとから読みとれます。
空や海の生き物とのちがい
同じ時代にプテラノドンのような翼竜(よくりゅう)、海ではモササウルスやプレシオサウルスなどの海にすむは虫類がくらしていました。これらは恐竜の仲間とよばれることもありますが、せいかくには恐竜ではありません。 恐竜は主に陸(りく)でくらし、足のつくり(まっすぐ体の下にのびる骨)に共通点がある生き物のグループです。翼竜ははね、海のは虫類はひれが発達しており、そこが大きなちがいです。
2.なぜ恐竜は絶滅したの?主な考え方
巨大ないん石の衝突(しゅうとつ)
もっとも有力とされる考えは、メキシコ・ユカタン半島ちかくに直径10kmほどのいん石が落ち、地球の環境がとつぜん大きくかわったというものです。いん石の落下で大つなみが発生し、地表は火の玉のような高温になりました。空にはちりやこまかい岩の粉がまき上がり、太陽の光がさえぎられました(暗くて寒い時期が長く続いたと考えられます)。
大きな火山のふん火(ふんか)
同じごろ、インドなどで長いあいだ続く大ふん火が起き、空気に火山灰(かざんばい)や気体が広がりました。これにより、雨の性質が変わったり、気温が下がったりして、生き物にとってくらしにくい環境が広がったと考えられます。
いくつかの変化が重なった可能性
海の水位の上下、気温の大きなへん化、植物の入れかわりなど、いくつもの変化が重なって恐竜が生きぬくのがむずかしくなった、という見かたもあります。下の表は、原因→すぐに起きたこと→その後のしくみ→結果のながれをまとめたものです。
| 原因の候補 | すぐに起きたこと | その後のしくみ | 結果 |
|---|---|---|---|
| いん石の衝突 | 大つなみ・地表の高温・強い衝撃 | 空にちりが広がり、太陽の光が弱くなる | 地球が急に寒くなり、植物が育ちにくい |
| 大ふん火 | 火山灰や気体が空に広がる | 雨の性質がかわる/気温が下がることがある | すむ場所や食べ物がへる |
| 変化の重なり | 海の水位や気温のゆれ動き | 食べ物の種類が入れかわる | 長い時間をかけて生き物に大きな影響 |
3.絶滅のしくみをやさしく図解(文章で)
太陽の光がさえぎられると何が起きる?
空にちりや火山灰が広がると、地表にとどく光が少なくなります。光が弱いと植物の光合成(こうごうせい)がさがり、草や木があまり育たなくなります。光は食べ物づくりの出発点なので、ここが弱まると食べものの量全体がへり、あらゆる生き物に連鎖して影響します。
食物連鎖(しょくもつれんさ)がくずれる流れ
植物がへる → 草食の恐竜のえさが足りない → 肉食の恐竜も食べものがへる。このつながりのくずれが、広い地域でいっせいに進みました。海でも同じで、海の植物プランクトンがへると、貝や魚、その上の大きな生き物まで影響を受けます。下の表は、陸と海での変化をならべて見やすくしたものです。
| 場所 | 出発点(いちばん下の生産者) | 出発点がへると… | 上の生き物に起きること |
|---|---|---|---|
| 陸 | 植物(草・木) | 草食が食べる量が足りない | 肉食も食べもの不足になり、全体が弱る |
| 海 | 植物プランクトン | 小さな動物プランクトンがへる | 魚・大型生物までえいきょうが広がる |
空・海・大地で同時に起きたこと
空は暗く寒くなり、海は冷たくなったり酸性に近づいたり、大地は植物が育ちにくい状況になりました。くらしにくい世界にかわったことで、多くの恐竜が生きのこれなくなったのです。とくに大きな体の恐竜は、たくさんの食べものを必要とするため、環境の変化に弱かったと考えられます。
4.恐竜がいなくなったあとの地球と私たち
生きのこった生き物と新しい主役
絶滅のあと、小さなほ乳類、ワニやカメ、鳥の先祖などが生きのこりました。時間がたつと、小さなほ乳類からいろいろな動物が進化し、やがて人間もあらわれました。地球の主役が入れかわったといえます。下の表は、絶滅のあとに目立つようになったグループの得意わざをまとめています。
| グループ | 生きのこりの理由のヒント | 得意わざ |
|---|---|---|
| 小型ほ乳類 | 体が小さく、少ない食べ物でも生きられる | 夜や土の中ですごすのが上手 |
| 鳥の先祖 | 羽があり、動き回ってえさをさがせる | 体温を保つしかけが発達 |
| ワニ・カメ | 変化に強い体のしくみ | 長く生き、環境のゆれに耐える |
鳥は恐竜の子孫なの?
最新の研究では、鳥は恐竜のなかまから進化したと考えられています。羽のあと(羽毛の化石)が見つかることもあり、ニワトリやスズメの遠い先祖は恐竜といえるのです。恐竜の特徴が今も生きていると考えると、恐竜は完全に「ゼロ」になったわけではありません。
学べることと観察の工夫
恐竜の絶滅は、環境の急な変化が生き物に大きなえいきょうをあたえることを教えてくれます。近くの博物館で化石を見たり、図鑑で時代をならべて調べたり、学校の自由研究で気温や光と生き物の関係をまとめるのもおすすめです。学びを自分の言葉でノートにまとめ、原因→しくみ→結果の順に整理すると、理解が深まります。
5.しつもんQ&Aと用語ミニ辞典・学びのコツ
よくある質問(Q&A)
Q1:恐竜は本当に全部いなくなったの?
**A:**恐竜そのものは多くが絶滅しましたが、鳥として子孫が生きのこったと考えられます。
Q2:人間が恐竜といっしょにくらした時代はあるの?
A:ありません。恐竜の絶滅は人間があらわれるよりずっと前の出来事です。
Q3:いん石が落ちたことはどうやって分かったの?
**A:**丸い地形(クレーター)や、特別な金属をふくむ地層が見つかり、研究からその可能性が高いと分かってきました。
Q4:恐竜はいなくなるまでどのくらい時間がかかったの?
**A:**一気に消えたというより、環境の変化が続く中で少しずつ数がへっていったと考えられます(場所によってちがいがあります)。
Q5:大きい恐竜と小さい恐竜、どちらが生きのこりやすかった?
A:一般に小さい方が食べ物が少なくても生きられるため、有利だった可能性があります。ただし、すむ場所や食べ方でも変わります。
Q6:海や空の生き物も同じように絶滅したの?
**A:**多くがえいきょうを受け、アンモナイトなどは絶滅しましたが、魚や一部の海生は虫類、鳥は生きのこりました。
Q7:恐竜の色や羽はどうやって分かるの?
A:羽毛の化石や色のもと(色素)のしるしが残ることがあり、そこから色合いや羽の有無を推測します。
Q8:恐竜の声は分かるの?
**A:**はっきりとは分かりませんが、骨の形や頭のくうのようすから、音の出し方を想像する研究が進んでいます。
用語ミニ辞典(やさしい言いかえつき)
| ことば | 意味 | やさしい言いかえ |
|---|---|---|
| 絶滅 | 生き物の一つのグループがいなくなること | いなくなること |
| いん石 | 宇宙から落ちてくる石のかたまり | 宇宙の大きな石 |
| 光合成 | 植物が光を使って栄養を作るはたらき | 光でごはん作り |
| 食物連鎖 | 食べる・食べられるのつながり | 命のリレー |
| 羽毛 | 羽のもとになるうすい毛 | 鳥の羽のもと |
| クレーター | いん石や火山でできた丸いへこみ | 大きなくぼみ |
| 地層 | 土や岩がかさなってできた層 | 地面の年れきのページ |
読む→考える→調べる:学びのステップ
1)読む:時代の順番(三畳紀→ジュラ紀→白亜紀)をおさえる。
2)考える:原因→しくみ→結果の流れで、どこで何が起きたかを言葉で説明できるようにする。
3)調べる:博物館の展示や図鑑を見て、**表や図(自作)**にまとめる。比べたい項目(場所・食べ物・体のつくり)を決めると整理しやすい。
4)まとめる:自分の言葉で感想と学びを書き、次に調べたいことをメモする。自由研究のしめくくりになります。
まとめ
恐竜が絶滅した大きな理由は、いん石の衝突や大きな火山のふん火など、地球の環境が急にかわったことにあります。 その結果、太陽の光がさえぎられ、植物が育たず、食べ物のつながりがくずれたと考えられます。
絶滅のあと、鳥として恐竜の特徴は今も受けつがれ、ほ乳類が発展して、人間の時代へとつながっていきました。自然の変化と命のつながりを学ぶことで、地球を大切にする気持ちが育ちます。