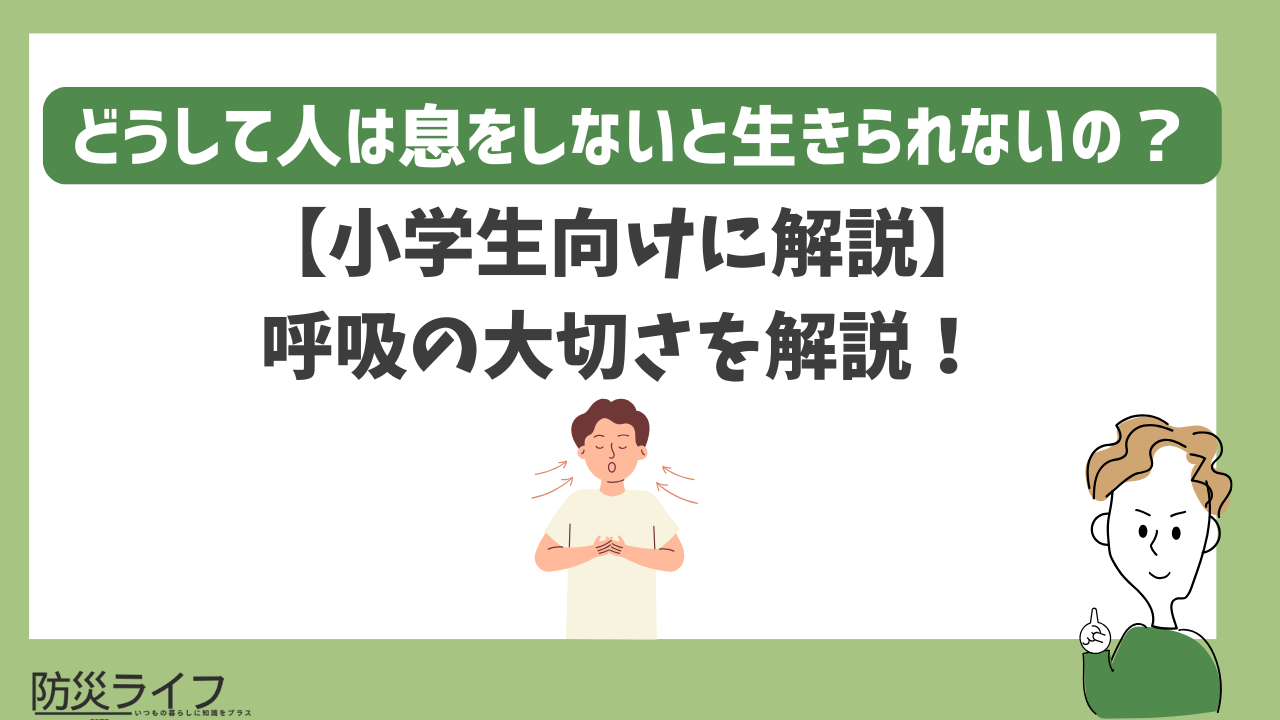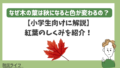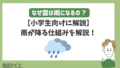はじめに——わたしたちは、起きていてもねていても、1日に2〜3万回も「すう・はく」をくり返しています。目には見えない細かな動きですが、じつは体ぜんぶを動かす“エネルギーづくり”に直結する超たいせつな仕事。この記事では、**呼吸(こきゅう)**がなにか、どうやっておこなわれ、なぜ命に必要なのかを、小学生にもわかりやすくたっぷり解説します。
この記事で学べること
- 呼吸ってなに?空気はどんな道を通る?
- 酸素がどうやって“力(エネルギー)”になるの?
- 肺と血液と心臓のチームワーク
- 脳や筋肉が作る「呼吸のリズム」
- きょうからできる“上手な息のしかた”と自由研究アイデア
呼吸ってなに?——空気と体の入れかえ工場
① 息の出入りで何が起こる?
- 吸う(吸気):空気の中の**酸素(さんそ)**を体に取りこみます。
- 吐く(呼気):体の中で生まれた**二酸化炭素(にさんかたんそ)**を外に出します。
- この入れかえで、細胞(さいぼう)がエネルギーを作る材料がそろいます。
② 空気の旅マップ(鼻・口→気管→肺)
- 鼻/口…空気の入口。鼻はあたため・しめらせ・ゴミ取りが得意。
- のど(咽頭/いんとう)…食べ物の道と空気の道が交差する場所。
- 気管→気管支…空気の大通り。左と右の肺へ枝分かれ。
- 肺(はい)…スポンジみたいにやわらかい臓器。超小さい袋**肺胞(はいほう)**がぎっしり。
- 肺胞でガス交換——酸素は血液へ、二酸化炭素は肺へもどって吐く息になります。
③ 空気の中身は?
- 窒素(ちっそ)約78%、酸素約21%、ほかに二酸化炭素・水蒸気など。
- 体がとくに必要なのは酸素。取りすぎる心配よりも「足りなくならないこと」が大切。
表:吸うとき・吐くときの体の変化
| うごき | 体の変化 | 何が起こる? | 覚え方のコツ |
|---|---|---|---|
| 吸う | むねがふくらむ/お腹が前へ | 酸素が肺に入りこむ | 風船に空気を入れるイメージ |
| 吐く | むねがしぼむ/お腹がへこむ | 二酸化炭素が外へ出る | 風船の空気を出すイメージ |
④ 鼻呼吸と口呼吸はどうちがう?
| ちがい | 鼻呼吸 | 口呼吸 |
|---|---|---|
| 空気の準備 | あたため・加湿・ゴミ取りができる | そのまま入り、のどが乾きやすい |
| 体へのやさしさ | のどにやさしい、風邪をひきにくい | 風邪・アレルギーが出やすいことも |
| 運動時 | ふだんは鼻、強い運動は鼻+口 | 強い運動のときの補助に向く |
なぜ酸素が必要?——細胞のエネルギーづくり
① 細胞は「小さな工場」
体は数えきれない細胞でできています。細胞はごはん由来の栄養(ぶどう糖など)と酸素を使ってエネルギーを作ります。工場のエンジン役はミトコンドリア。ここで作られるエネルギー(ATP)は、体の“電池”のようなものです。
② ごはん+酸素=動く力
- ごはんだけでは“材料”どまり。そこへ酸素が加わって、はじめて**力(エネルギー)**に変身。
- 心ぞうがドクドク動くのも、頭で考えるのも、走るのも、この仕組みのおかげ。
③ 二酸化炭素は出たらすぐ外へ
エネルギーづくりの**出がらし(老廃物)**が二酸化炭素。体にためると調子が悪くなるので、呼吸で外へ出すことが重要です。
表:酸素が足りないときに出るサイン
| サイン | どうして起こる? | たいおう |
|---|---|---|
| あくび・だるさ | 脳に酸素がたりない合図 | 姿勢を正し深呼吸、外の空気を吸う |
| めまい・立ちくらみ | 酸素不足で脳がボーッ | すこし休んで水分補給 |
| 息切れ | 体がもっと酸素をほしがる | 動きをゆるめて呼吸を整える |
やってみよう! 窓のそばで背すじを伸ばし、4秒吸う→6秒吐くを3回。頭がスッキリするか感じてみよう。
④ 高い山で息が切れるのはなぜ?
高い山は空気がうすく、同じ回数吸っても酸素をとりこみにくいから。体は呼吸や心拍を速くしてがんばります。
肺と血液のチームワーク——全身へお届け便
① 肺胞と毛細血管のすごい連携
肺胞の表面は毛細血管でおおわれ、壁は髪の毛よりも薄い!ここで酸素が血液へ、二酸化炭素が肺へと行き交います。
② 赤血球は酸素宅配トラック
血液の主役赤血球(せっけっきゅう)が、酸素をしっかりつかんで全身へ運搬。赤血球の色のもとヘモグロビンが酸素をつかんだり、はなしたりして配送します。
③ 心ぞうポンプでスピード配達
心臓がポンプの役め。血液を送り出し(動脈)/戻し(静脈)、体のすみずみに酸素を届けます。
表:空気の通り道と役わり
| 部位 | 主なお仕事 | 観察ポイント |
|---|---|---|
| 鼻 | 空気をあたため・しめらせ・ゴミをキャッチ | 鼻呼吸だとのどにやさしい |
| のど・気管 | 空気の大通り | せきは異物を出す防御反応 |
| 気管支 | 左右の肺へ枝分かれ | 木の枝のように細くなる |
| 肺胞 | ガス交換の現場 | 超ミクロのふくろが数おおし |
年れい別の呼吸数めやす(1分あたり)
| 年れい | めやす |
|---|---|
| 低学年 | 18〜30回 |
| 高学年 | 16〜24回 |
| 大人 | 12〜20回 |
はかり方:1分静かにすわり、胸やお腹の上下で**1回(吸って吐いてで1回)**を数えよう。
息のリズムはどう決まる?——脳と筋肉のしくみ
① 脳の自動運転:延髄(えんずい)の呼吸中枢
脳の奥にある延髄が、吸う・吐くのリズムを自動でコントロール。だからねていても呼吸は止まらないのです。
② 横隔膜(おうかくまく)と肋間筋(ろっかんきん)
- 横隔膜が下がる→胸の空間が広がる→空気が入る。
- 肋間筋が肋骨を持ち上げ、胸をさらに広げて助けます。
③ 自律神経と気持ちの関係
ドキドキ緊張のときは浅く速い息、リラックスのときは深くゆっくり。これは**自律神経(交感/副交感)**の働きによるもの。ゆっくり吐くと落ち着きやすくなります。
表:こんなとき呼吸はどう変わる?
| 場面 | からだの変化 | くふう |
|---|---|---|
| 運動中 | 呼吸が速く深くなる | スタート前後に深呼吸、こまめに水分 |
| 緊張・ドキドキ | 浅く速い息になりがち | 吸う3秒・止める1秒・吐く6秒で落ち着ける |
| せき・鼻づまり | 空気の通りが悪い | 姿勢を正し、部屋を加湿して休む |
呼吸を守る暮らしのコツ——今日からできる!
① 深呼吸・姿勢・外遊び
- 背すじをスッとのばすだけで肺が広がり吸える量アップ。
- 外の新鮮な空気で3回ゆっくり深呼吸。気分もリセット!
② 風邪・アレルギーと上手につきあう
- 手あらい・うがいでのどを守る。
- 鼻がつまると口呼吸になりがち。加湿・鼻ケアで鼻呼吸を取りもどす。
- 花粉の季節はマスク・ゴーグルで刺激を減らす。
③ 季節の注意
- 冬:乾燥でのどがカサカサ→加湿・水分。
- 夏:熱中症予防に水分・塩分、直射日光をさける。
④ 運動・歌・ふえで肺をきたえる
- 鬼ごっこ、なわとび、マラソンで持久力アップ。
- 歌やリコーダーは長く吐く練習になり、呼吸が上手に。
表:今日から試せる“呼吸トレ”ミニメニュー
| メニュー | やり方 | ねらい |
|---|---|---|
| 4-4-6呼吸 | 4秒吸う→4秒止める→6秒吐く×3回 | 心を落ち着ける |
| ふーっとロウそく | お腹をへこませながら長く吹く | 吐く力アップ |
| 風船ふくらまし | 少しずつ空気を入れる | 肺のふくらみ感覚をつかむ |
⑤ 空気をきれいにする工夫
| 家の中でできること | 理由 |
|---|---|
| こまめに換気 | 二酸化炭素やホコリを外へ |
| 加湿(50〜60%) | のど・鼻が楽、ウイルス対策にも |
| 掃除とほこり取り | 吸い込む刺激をへらす |
やってみよう!呼吸の自由研究と実験
① 1分間呼吸数をはかろう
- すわって1分数える→歩いたあとにも数える。
- どう変わった?グラフにして比べよう。
② 紙風車/ストローの実験
- 紙風車やストローにゆっくり長く息を吹くと、回り方や音が変わる。
- 吐く長さと速さの関係を観察しよう。
③ ボトルで肺モデル
- 2Lボトル、風船2個、ストロー、テープで肺モデルを作る。
- 下の風船(横隔膜役)を引っ張ると、上の風船(肺役)がふくらむ!
④ 簡易“肺活量”メモ
- 同じ風船を何回吹きでどれくらいの大きさになるか、日ごとに記録してみよう。
安全ガイド——呼吸をじゃまするものに注意!
- 煙や強いにおい(洗剤・スプレー)を吸いすぎない。
- 食べ物をよくかんで、走りながらの飲食は避ける(誤飲・誤えん予防)。
- 水の中での息こらえは無理をしない。必ず大人といっしょに安全に。
Q&A——呼吸のギモンをスッキリ!
Q1. 口で息をしてもいいの?
A. はい、走るときなどは口も使います。でもふだんは鼻呼吸がおすすめ。空気が温まり、ホコリもキャッチできます。
Q2. しゃっくりはなに?
A. 横隔膜が急にピクッと動くこと。水をのむ・ゆっくり深呼吸でおさまることが多いです。
Q3. ため息は体に悪い?
A. ため息は深く息を吐き切る動き。実は胸のこわばりをゆるめる働きも。気づいたら“深い吸い直し”をセットにしましょう。
Q4. 息を止める練習は危なくない?
A. 長時間は危険。苦しくなる前にやめる、大人といっしょに安全に。水の中では絶対に無理をしないで!
Q5. 咳(せき)はとめたほうがいい?
A. せきは気道のお掃除。強く長く続くときは休む・水分、必要なら医療機関へ。
Q6. 冬に“白い息”が出るのは?
A. 吐いた空気の水蒸気が冷えて白く見えるから。湯気と同じ仕組みです。
Q7. いびきは呼吸と関係あるの?
A. のどの空気の道がせまくなると音が出ます。鼻づまりや寝る姿勢を見直すとよくなることがあります。
Q8. 過呼吸ってなに?
A. 速く浅い呼吸が続いて二酸化炭素が減りすぎた状態。ゆっくり吐くことを意識し、落ち着ける姿勢で休みましょう。
用語辞典(よく出てくる言葉)
- 酸素(さんそ):体がエネルギーを作るのに必ずいる気体。
- 二酸化炭素(にさんかたんそ):エネルギーを作ったあとに出る“いらない気体”。息で外へ。
- 肺(はい):胸の中の空気の工場。ガス交換を担当。
- 気管・気管支:空気の通り道。気管から左右に分かれて細くなる。
- 肺胞(はいほう):ガス交換の現場となる超小さなふくろ。
- 赤血球(せっけっきゅう):血液の細胞。酸素の運び屋。
- ヘモグロビン:赤血球の色のもと。酸素をつかむ名人。
- 横隔膜(おうかくまく):息を吸うときに下がる“呼吸の主役筋”。
- 肋間筋(ろっかんきん):肋骨を持ち上げ胸を広げる筋肉。
- 延髄(えんずい):呼吸のリズムをつくる脳の場所。
- 自律神経:体の働きを自動で調節する神経。呼吸の深さや速さにも関与。
- 呼吸数:1分間に何回息をするか。大人は12〜20回、子どもはやや多め。
まとめ——息は「命のスイッチ」
呼吸は、酸素を取りこみ二酸化炭素を出す命のスイッチ。肺・血液・心臓・脳・筋肉がチームになって、24時間あなたを支えています。背すじをのばし、外の空気で深呼吸。
よく遊び、よく笑い、よく眠る——それだけで呼吸はもっと上手になります。今日も“すう・はく”を味方に、元気いっぱい過ごしましょう!