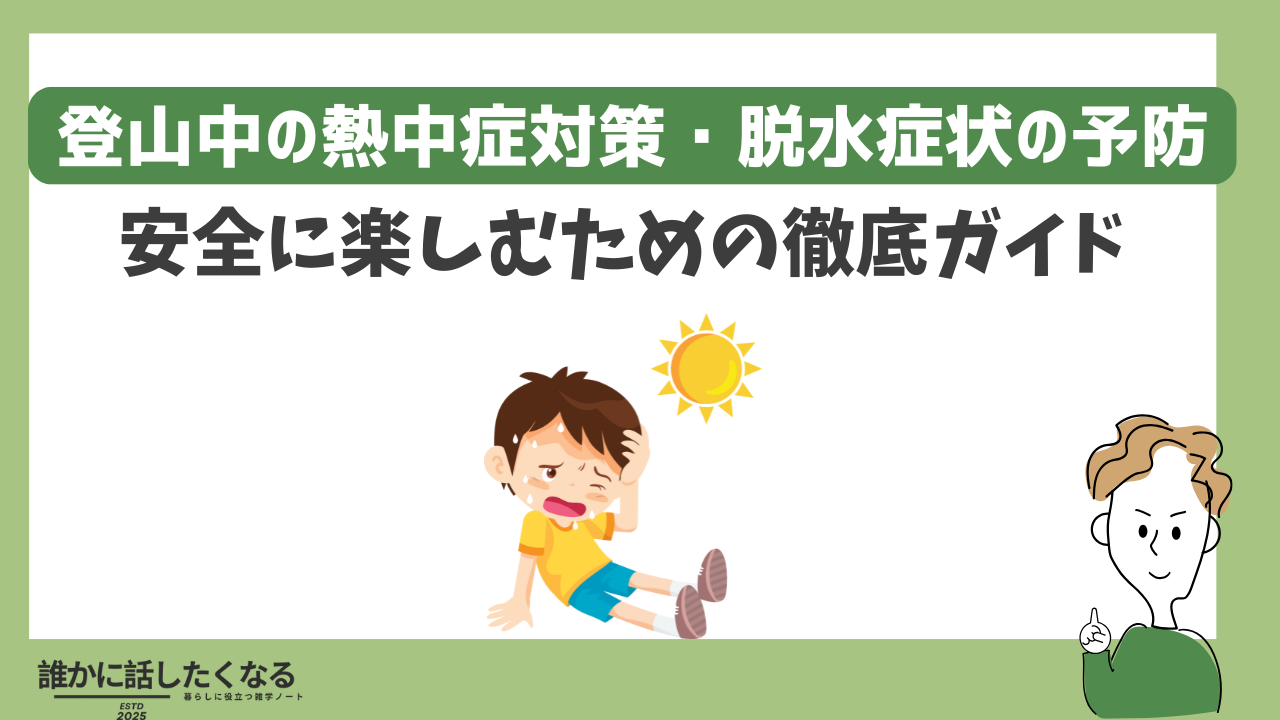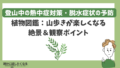登山は自然とふれあい、心身の健康や達成感をもたらす一方で、夏場や高温期には熱中症と脱水のリスクが急上昇します。標高差の大きいルート、樹林帯の無風・高湿、長時間の行動は、気づかぬうちに症状を進行させがちです。
本ガイドは、出発前→行動中→下山後のすべての場面を通して、仕組みの理解/装備と補給の設計/気象とコース取りの工夫/“即判断”フレーム/応急手当を、表・チェックリスト・計算例・ケーススタディで体系化しました。今日の山行からそのまま使えます。
1. 熱中症・脱水の仕組みと山でのリスク
1-1. 発症メカニズム(なぜ起こるのか)
- 熱中症:体内で生じた熱を放出できず、深部体温が過度に上昇した状態。高温・多湿・強い日射・無風・厚着・運動強度の高さが重なると危険。
- 脱水:汗・呼吸・尿で失う**水と電解質(特にナトリウム)の補給が追いつかない状態。水だけ大量は低ナトリウム血症(“水中毒”)**を招くことも。
- 体液バランス:汗で失うのは水だけでなく塩分や微量ミネラル。体液が薄まると筋けいれん・頭痛・意識障害へと進行しやすい。
山でリスクが高まる要因
- 強い日射×薄い空気:標高が上がるほど紫外線が強まり、皮膚表面の受熱量が増える。
- 樹林帯の無風・高湿:汗が蒸発せず放熱が妨げられる。
- ロング登り+背面の熱だまり:ザック背面に熱がこもりやすい。
- 前日の疲労・寝不足・空腹:体温調節と判断力が低下。
- 黒い岩稜・南向き斜面:輻射熱で体感温度が上がる。
1-2. 初期〜重症サイン(見逃さない)
| 重症度 | 主なサイン | 行動指針 |
|---|---|---|
| 初期 | めまい、立ちくらみ、頭痛、悪心、倦怠、筋けいれん(足がつる)、多汗 | 日陰へ移動・衣服ゆるめ・水+電解質を少量ずつ |
| 中等度 | 判断力低下、ふらつき、吐き気、皮膚が熱いのに汗が出にくい、尿量減・濃色 | 冷却(頸・腋・鼠径部)+補給、行動短縮・下山検討 |
| 重症 | 意識障害、けいれん、歩行不能、体温40℃前後 | 冷却最優先+救助要請(無理な歩行は避ける) |
簡易セルフチェック(60秒):舌や唇の乾き、尿の色(濃い=脱水傾向)、言葉が滑らかに出るか――一つでも違和感があれば立ち止まって評価。
1-3. 熱指数(WBGT)と標高の考え方
| 指標(WBGT) | 目安 | 行動の基準 |
|---|---|---|
| 21〜25(注意) | 涼しい時間帯を活用 | 休憩増やし、水分・電解質をこまめに |
| 26〜28(警戒) | 行程を短縮 | 30〜40分毎に休憩、日陰を選ぶ |
| 29〜31(厳重警戒) | 日中行動は避ける | 早出早着、稜線での長居は避ける |
| 32〜(危険) | 原則中止 | 低山でも撤退判断 |
参考メモ:気温は標高100mで約0.6〜0.7℃下がるのが目安。ただし日射・風・湿度で体感は大きく変わります。
1-4. 暑さへの「慣れ」を作る(暑熱順化)
| 期間 | 取り組み | ねらい |
|---|---|---|
| 1〜3日目 | 低山や平地で30〜45分の早歩きを毎日 | 発汗反応の立ち上がりを早める |
| 4〜7日目 | 標高差300〜500mの短時間登山、早出で実施 | 発汗量・皮膚血流が最適化しやすい |
| 8〜10日目 | 目標ルートの一部を試走/試歩 | 実戦環境で補給と冷却の最適化 |
無理せず段階的に。体調不良日は中止が原則。
2. 出発前の準備計画(体調・ルート・装備)
2-1. 体調・睡眠・“プレ・ハイドレーション”
- 前日は7〜8時間の睡眠。発熱・下痢・二日酔い時は計画変更。
- 出発2〜3時間前からコップ2杯の水+軽い塩分・糖質。カフェイン・アルコールは控えめに。
- 朝食は主食+たんぱく+味噌汁など塩分で、発汗に備えた体内ストックを作る。
2-2. 水と電解質の持参量(計算法)
- 予定行動時間×時給補給量(0.4〜0.8L)=基本量
- 気温・直射・風の弱さ・行動強度を見て**+20〜40%のバッファ**
- 山小屋・水場での補給可能性が低い場合はさらに+0.5〜1.0L
- 電解質はNa300〜700mg/時を目安(汗に白い塩跡が出る人は高め)
例:6時間行動・暑熱・樹林帯多め
0.7L/時×6h=4.2L → バッファ30%で約5.5L(ハイドレーション3L+ボトル500ml×5)。Naは時給500mg×6h=3,000mgを目安。
2-3. ルート取りと時間設計(避難ノードを可視化)
- 早出早着(日の出〜午前中に核心区間を通過)。
- 樹林帯の日陰区間を活用。南向き直射の長い尾根は回避。沢沿いは涼しいが増水・滑落に注意。
- 山小屋・水場・日陰・エスケープなどの**“避難ノード”**を地図にマーキング。プランA/B/Cを用意。
2-4. ウェアと装備(汗と日射をコントロール)
- ベース:吸湿速乾(綿は避ける)。
- ミドル:通気フリースor薄手化繊。休憩用に軽量ダウン。
- シェル:防風・防水。ピットジップがあると放熱しやすい。
- 小物:通気性の良い帽子、UVカットサングラス、アームカバー、ネックゲイター。
- 給水装置:ハイドレーション(1.5〜3L)+500mlボトル(電解質用)。
- ザック:背面メッシュ/ベンチレーション構造で熱だまり軽減。
冷却系アイテムの比較(例)
| 種別 | 例 | 体感効果 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 蒸発冷却 | 濡らすタオル/ネックゲイター | 軽量・継続的 | 乾燥地域で効果大、樹林帯高湿では過信しない |
| 伝導冷却 | 保冷剤・氷入りボトル | 即効性が高い | 凍傷に注意、布で巻く |
| 対流冷却 | 携帯扇風機・うちわ | 風がない時に有効 | バッテリー管理 |
事前チェックリスト(出発60分前)
| 項目 | OK基準 |
|---|---|
| 体調 | だるさ・頭痛なし、睡眠十分 |
| 飲食 | 水500ml+塩分/糖質を済ませた |
| 荷物 | 水・電解質・行動食・冷却具・地図・ヘッドライト |
| ルート | 早出計画・短縮案・避難ノードを確認 |
| 連絡 | 計画共有、バッテリー満充電・予備携行 |
3. 行動中の予防テクニック(補給・ペース・冷却)
3-1. 補給設計と“自分の汗量”の計算
- 一般登山の給水目安:0.4〜0.8L/時(暑熱時は最大1L/時)。
- 電解質:ナトリウム300〜700mg/時(ジェル・経口補水・タブレット・梅干し等)。
汗量の簡易推定(自宅や低山で事前に)
- 行動前後で体重を量る(着衣・装備同じ)
- 途中で飲んだ量を足す/排尿量を引く
- 重量差(kg)≒発汗量(L) → 行動時間で割る=発汗L/時
- その70〜80%を補給量の上限に(過剰飲水を避ける)
6時間行動のサンプル補給スケジュール
| 時刻/経過 | 水 | 電解質 | 行動食 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 150ml | Na100〜150mg | 小さなパン1 | スタート直前に口を潤す |
| 0:30 | 100ml | Na100mg | ジェル1 | 立ち休憩30秒 |
| 1:00 | 150ml | Na100〜150mg | ナッツ/羊羹 | 日陰で5分休憩 |
| 2:00 | 200ml | Na150mg | 塩せんべい | シェル開放・帽子濡らす |
| 3:00 | 200ml | Na150mg | ジェル1 | コース短縮の可否を確認 |
| 4:00 | 200ml | Na150mg | ドライフルーツ | 風の通る場所で休憩 |
| 5:00 | 150ml | Na100mg | クッキー | 下山モード切替 |
| 6:00 | 100ml | Na100mg | 予備 | 下山後の補給へ |
3-2. ペース配分・休憩・行動食
- 20〜30分ごとに2〜3口:水+電解質。大量一気飲みはNG。
- 行動食は糖質+塩分(ジェル、塩せんべい、ナッツ+ドライフルーツ、梅干し、羊羹)。
- **味替え(甘味/塩味/酸味)**を用意→食欲低下を予防。
- 心拍が上がり過ぎたら**“立ち休憩30秒”**で呼吸を整える。
- 40〜60分ごとに日陰で5〜10分休憩。靴ひもを緩め、背面を風に当てる。
3-3. 体温コントロールのコツ(蒸発冷却を最大化)
- 登り始めは1枚少なめ、汗が噴き出す前にファスナー開放。
- 帽子やネックゲイターを濡らして気化冷却を促進。
- 冷却ポイントは首・腋・鼠径部。濡れタオル→風を当てると効果大。
- ザックのショルダー・ヒップベルトは指1本分のゆとりで血流を妨げない。
仲間とセルフチェック(合言葉)
- 「30分に一口・1時間に一息」(補給と休憩のリズム)
- 顔色・発汗・会話の滑らかさを互いに観察。違和感があれば止まって判断。
3-4. 地形と時間帯の“涼しい選択”
| 地形/時間 | ねらい方 | リスク |
|---|---|---|
| 早朝の樹林帯 | 日射前に核心を消化 | 朝露で足元が滑りやすい |
| 稜線(午前中) | 風で放熱しやすい | 雷・強風日は回避 |
| 北斜面トラバース | 直射を避けられる | 落石・残雪に注意 |
4. 現場の“即判断”と応急手当(重症化を防ぐ)
4-1. 即判断フレーム(アルゴリズム)
- 症状?(めまい/吐き気/足つり/頭痛)→ Yesなら次へ
- 場所替え:日陰・風通しへ、荷を下ろす
- 冷却:衣服をゆるめ、水かけ、頸・腋・鼠径部を重点冷却
- 補給:電解質+水を少量ずつ(氷入り飲料も可)
- 再評価:10分おき→改善なければ下山・救助連絡
4-2. 症度別の応急手当
| 症状レベル | 具体例 | 初動 |
|---|---|---|
| 軽症(I度) | めまい、足つり、軽い頭痛 | 安静・日陰、頸/腋/鼠径冷却、経口補水を少量ずつ |
| 中等度(II度) | 会話不十分、吐き気、歩行不安定 | 冷却最優先、行程短縮、下山判断を明確に |
| 重症(III度) | 意識障害、けいれん、歩行不能 | 119/警察/管理事務所へ。冷却継続、無理な歩行は避ける |
4-3. 救助要請のテンプレ
- 場所:山域名/コース名/標高・地形(尾根・沢・分岐)
- 状況:症状・発症時刻・意識レベル・歩行可否・体温(測れれば)
- 人数:要救助者数・同行者数・年齢層
- 対処:実施済みの冷却/補給/安静
- 目印:派手色レイン、ライト点滅、ホイッスル
よくある誤解(神話と真実)
| 神話 | 実際 |
|---|---|
| 水は多いほど良い | 水だけ大量は低Na血症リスク。電解質も一緒に |
| 汗はかかない方が良い | 汗は体温調節に必要。乾かす装備と行動が重要 |
| 風があるから安全 | 熱波・強日射では風があっても体温上昇に注意 |
早見表:熱中症・脱水・低Naの見分けと初動
| 症状/所見 | 熱中症寄り | 脱水寄り | 低Na血症寄り |
|---|---|---|---|
| 体温 | 高い/皮膚熱い | やや高い | 正常〜やや低いことも |
| 汗 | 出ない/粘る | 多い | 多い or 普通 |
| 尿 | 少ない/濃い | 少ない/濃い | 普通〜多い/薄いことも |
| 主訴 | 頭痛/吐き気/ふらつき | のど渇き/足つり/倦怠 | 頭痛/むくみ/混乱 |
| 初動 | 冷却最優先 | 水+電解質を少量ずつ | 飲水抑制+電解質 |
4-4. 搬送・保温・通信のポイント
- 体位:嘔気が強ければ横向き。意識低下時は気道を確保。
- 保温:冷却と同時に直射・風を遮る。体温が下がり過ぎないよう断熱シートを併用。
- 通信:電波が弱い所は高所・開けた場所へ1名のみ移動し通報。位置は地図アプリの座標・分岐名で具体化。
5. ケーススタディ・チェックリスト・下山後の回復
5-1. ケーススタディ(失敗から学ぶ)
- 例1:樹林帯の蒸し暑さで頭痛
状況:標高差800mの登り、風弱く高湿。頭痛と吐き気。
対処:ザックを下ろし日陰で横臥→頸・腋冷却→経口補水150mlを5分おき→30分で回復。以降は行程短縮し下山。 - 例2:稜線直射+強風で汗が乾きすぎ脚が攣る
状況:発汗実感が薄く水だけを摂取。大腿のけいれん。
対処:塩タブ+ジェルでNa補給、ストレッチ、下りはストック活用→痙攣消失。以後Na補給を時給400mgに修正。 - 例3:長い下りでふらつき
状況:水が尽き集中力低下。午後の気温上昇。
対処:同行者から分けてもらい補給→日陰で15分のマイクロナップ→最寄りエスケープへ退避。 - 例4:子ども連れでの低山ハイク
状況:幼児が急に不機嫌・無口に。
対処:木陰で帽子を濡らし、甘塩っぱい飲料を少量ずつ。歩行再開は機嫌と会話が戻ってから。
5-2. “持ってて良かった”装備カタログ(例)
| カテゴリ | 例 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 冷却 | ネッククーラー、保冷剤、冷感タオル | 首・腋・鼠径部の局所冷却 |
| 給水 | ソフトフラスク、吸い口付きボトル | こまめな一口補給を楽に |
| 日射 | 広いつば帽、サンシェード、偏光サングラス | 直射・照り返し対策 |
| 収納 | 胸ポケットベスト、ベルトポーチ | 電解質・ジェルを即取り出し |
| 安全 | 笛、反射テープ、赤色点滅ライト | 合図・視認性アップ |
5-3. 下山後のリカバリー(翌日に疲れを残さない)
- 補給:水+電解質を体重1kgあたり20〜30ml。糖質+たんぱく(カカオ、ヨーグルト、豆乳など)を早めに。
- 冷却/入浴:軽いシャワー→ぬるめ入浴で副交感神経を優位に。
- 睡眠:就寝前の過度な飲酒は控える(夜間の脱水を防ぐ)。
- 翌日のサイン:頭痛・むくみ・疲労感が強い場合は低Naも疑い、塩分・水分のバランスを取り直す。
5-4. ポケット版チェックリスト(コピー用)
- □ 早出早着/短縮案あり
- □ 水( L)+電解質( mg/h×時間)
- □ 行動食(甘・塩・酸の3種類)
- □ 冷却具(濡らせる布/保冷剤/帽子)
- □ 地図アプリ+紙地図/ヘッドライト
- □ 連絡先共有/予備バッテリー
Q&A(よくある疑問)
Q1. 水とスポーツ飲料はどのくらいの割合?
A. 暑熱時は電解質入り:水=1:1前後を目安に。甘味が辛くなったら塩味の固形で調整。
Q2. 氷や冷凍ペットボトルは有効?
A. 有効。首・腋・鼠径部を冷やすと体温低下が早い。溶けた水は電解質を追加して利用。
Q3. 子ども・高齢者はどう配慮する?
A. 体温調節機能が弱いので休憩を増やし、荷物軽量化。早出早着、午後の直射を避ける。
Q4. 低ナトリウム血症はどう避ける?
A. 水だけを大量に飲まず、Na300〜700mg/時を目安に**“水+電解質”で。汗に白い塩跡が出る人はやや高め**に設定。
Q5. コーヒーやお茶は利尿で不利?
A. 適量なら問題ないが、水・電解質の置き換えにはしない。暑熱時はまず電解質入り飲料を。
Q6. 炭酸飲料は?
A. のどごしは良いがガスで膨満し、飲水量が落ちることがある。行動中は控えめに。
Q7. 山小屋の水だけで十分?
A. ルートと混雑で入手が不確実。自前で必要量+予備を持つのが基本。
用語辞典(やさしく理解)
- 深部体温:体の中心部の温度。上がりすぎると内臓機能が低下。
- 電解質:体液の塩分など。特にナトリウムは神経・筋肉の働きに必須。
- WBGT(暑さ指数):気温・湿度・輻射熱を含めた熱ストレスの指標。
- エスケープルート:悪天や体調不良時に安全に退避できる道。
- マイクロナップ:短時間の仮眠。10〜20分で回復を促す。
- 輻射熱:地面や岩肌から放たれる熱。南向き斜面や黒い岩で強い。
まとめ:熱さの季節も、賢く・快適に山を楽しむ
登山は素晴らしい体験ですが、夏や高温・多湿の環境では熱中症・脱水・低ナトリウム血症が三位一体で迫ります。水・電解質・糖質の計画的摂取、吸湿速乾のウェア、早出早着のルート設計、冷却と補給のタイミング、そして**「違和感が出たら止まる」勇気**。
この5本柱を徹底すれば、暑い季節も安全に、そして快適に、誇らしく山を楽しめます。持病のある方、妊娠中・服薬中の方、子ども・高齢者は事前に医療者へ相談を。知識と備えで、命を守る登山を。