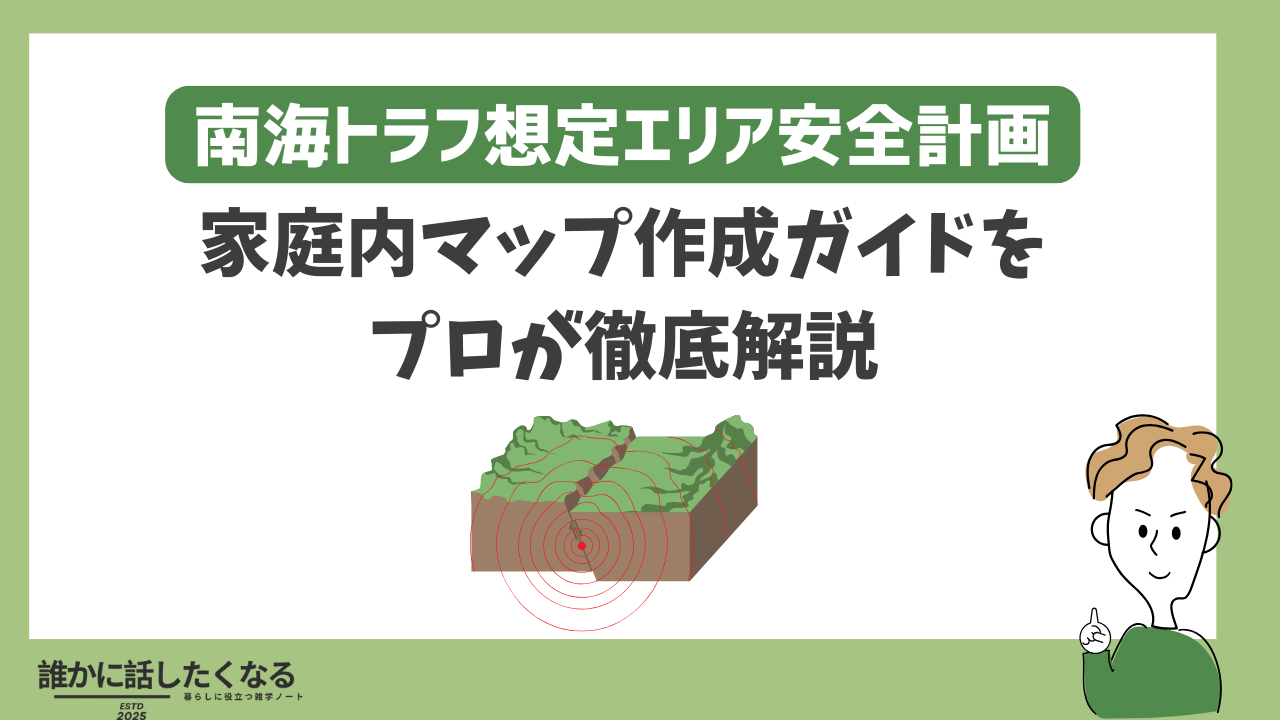南海トラフ地震の想定域では、地震→津波→余震→長期停電→物資不足の連鎖を見越した家族単位の設計図が生死を分けます。本記事は、家庭内マップを中核に、避難経路・集合場所・連絡手段・備蓄配置・役割分担を一枚に落とし込む方法を解説。
さらに、**家の構造別(平屋/二階/マンション)・地形別(海沿い/内陸/河口)**の調整、発災72時間の行動計画、近所力の活かし方まで立体的に整理します。作成の型・見直しの頻度・訓練メニューを加えまとめました。
1.結論と全体像:地震直後の“最初の10分”と“最初の72時間”を設計する
1-1.安全計画のゴール
- 家族全員の現在地→安全地点を10分以内の行動で結ぶ。
- 停電・断水・通信不調でも動ける紙のプラン(防水袋入り)を玄関・冷蔵庫・持ち出し袋に3部配置。
- 代替の代替(A案が倒れたらB、Bが無理ならC)を行動・連絡・避難先それぞれに明記。
1-2.10分の行動タイムライン(雛形)
| 経過 | 行動 | チェック |
|---|---|---|
| 0分 | まず身を守る(机・浴槽脇・柱のそば) | 頭部・足元の確保、ガラス飛散 |
| 1〜2分 | 火の始末(コンロ/ストーブ) | 炎とガス臭の確認、可燃物の退避 |
| 3〜5分 | 家族の声かけ・負傷確認 | 出血・骨折・挟まれ、応急処置の要否 |
| 5〜7分 | 玄関/窓を開け退路確保 | 建付け変形の前に開放、靴を履く |
| 7〜10分 | 避難の要否判定→出発 | 津波高/液状化/火災方向、危険物の回避 |
1-3.家庭内マップの必須レイヤー(重ね書き)
- 危険箇所(倒れやすい家具・ガラス・重い照明・水槽・食器棚・冷蔵庫)。
- 退路(室内→玄関/窓→道路→高台/避難所)を2経路以上。
- 遮断ポイント(ブレーカー・ガス元栓・止水栓・給湯器・太陽光パワコン)。
- 備蓄配置(飲料水・食料・簡易トイレ・衛生・灯り・工具・燃料・予備眼鏡・常備薬)。
- 集合・連絡(第1:宅前/第2:公園/第3:高台、家族の連絡先、県外親族のハブ)。
1-4.家の構造別・地形別の要点(追加)
| 区分 | 平屋 | 二階建て | マンション |
|---|---|---|---|
| 退路 | 玄関と勝手口の2経路 | 階段経由の退路を昼夜で確認 | 屋内階段→共用廊下→屋外階段を優先 |
| 津波 | 徒歩で高台へ | 2階一時退避→高台 | 垂直避難(上階)+長期停電対策 |
| 備蓄 | 玄関・寝室に分散 | 1階は浸水想定なら高所保管 | 上階へ多めに(水の持ち上げ計画) |
| 地形 | 海沿い | 河口・低地 | 内陸・丘陵 |
|---|---|---|---|
| 主な脅威 | 津波・塩害 | 液状化・浸水 | 斜面崩落・道路寸断 |
| 退路 | 高台へ最短 | 高い道路へ退避 | 崩落回避ルートの把握 |
1-5.発災72時間の行動計画(家族版)
| 時間帯 | 目標 | 行動の型 |
|---|---|---|
| 0〜1時間 | 生命維持 | 身の保護→火の始末→負傷確認→退路確保→避難判定 |
| 1〜12時間 | 家族の合流 | 集合場所へ移動、掲示/メモで足跡、安否連絡は短文で反復 |
| 12〜24時間 | 一晩を越える | 屋外/避難所の寒さ・雨対策、簡易トイレ設置、睡眠の確保 |
| 24〜72時間 | 生活の安定 | 飲食のローテーション、物資の節約、近所との助け合い、怪我のフォロー |
2.家庭内マップの作り方:紙一枚に“命の情報”を集約
2-1.準備(材料と下書き)
- A3用紙(なければA4を2枚つなぐ)、太マーカー、透明ポケット、マスキングテープ。
- 方位と家屋の簡単な間取り(玄関・階段・窓・寝室・台所・ブレーカー・元栓)。
- 外周図(自宅→最寄り高台・学校・公園・広い道路・橋・川)を徒歩目線で描く。
2-2.描き込み順序(5層のレイヤー)
- 退路と出口:室内から外へ最短2経路以上。夜間の暗所も記す。
- 危険の印:転倒物・ガラス・ブロック塀を赤でマーキング。家具の固定要否も書く。
- 遮断ポイント:ブレーカー/ガス元栓/止水栓を青で囲む。操作の順番メモも追記。
- 備蓄置き場:水・食料・トイレ・工具を緑でアイコン化。数量・賞味期限の最終確認日を書き込む。
- 集合場所・伝言の手順:第1(宅前)→第2(公園)→第3(高台)。待ち時間と掲示の合図も設定。
2-3.家族別の出発位置と代替経路
- 在宅時:寝室・台所・風呂場から直接退路を示す。夜間はヘッドライトの置き場をマーク。
- 外出時:学校/職場からの徒歩帰宅ルートと川・海から離れる矢印。橋とアンダーパスは回避ルートも併記。
- 高齢者・乳幼児:抱っこ/おんぶルート、段差回避、ベビーカー→抱っこ切替点を具体化。
2-4.色と記号の“家内ルール”
| 色/記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 赤線 | 危険 | ガラス/落下物/塀 |
| 青丸 | 遮断 | ブレーカー/元栓/止水栓 |
| 緑□ | 備蓄 | 水/食料/トイレ/灯り |
| ★ | 集合 | 第1/第2/第3の位置 |
| → | 退路 | 室内→外→道路→高台 |
家庭内マップ 必須記入項目表(拡張)
| 区分 | 記入内容 | 例 |
|---|---|---|
| 退路 | 室内→外→道路→高台 | 寝室→廊下→勝手口→高台階段 |
| 危険 | 倒れ物・落下物・ガラス | 食器棚/本棚/TV/姿見 |
| 遮断 | 電気・ガス・水 | 分電盤位置/元栓/止水栓 |
| 備蓄 | 種類・量・場所・期限 | 水/食料/簡易トイレ/灯り |
| 集合 | 第1/第2/第3・待ち時間 | 家の前→桜公園→神社高台(15/30分) |
| 連絡 | ハブ先/短文テンプレ | 「無事・桜公園へ」 |
3.避難計画と連絡の設計:動く順番・伝える順番
3-1.避難判定の基準
- 揺れが長い/立てない:外へ。ブロック塀・看板・窓下を避け、広い道路へ。
- 海・河口が近い:迷わず高台/上階へ(水平移動より垂直避難を優先)。津波警報の有無に依らず先に動く。
- 火災/ガス臭:上流側に回り込み、風下を避けて移動。交差点での火の粉に注意。
3-2.連絡の優先順位(家族→避難所→親族)
- 家族間の合図:短文(「無事・◯◯向かう」)。既読は期待しない前提で複数経路(電話・SMS・メモ・掲示)。
- 固定電話/公衆電話も候補に。無人でもメモを残すルール。
- 県外の親族1名をハブに指名し、伝言の一本化で回線混雑を回避。
3-3.集合場所と合流のタイムリミット
- 第1集合:宅前(危険ならスキップ)。
- 第2集合:近所の公園(15分待ち)。
- 第3集合:高台/避難所(30分後に合流、以降は掲示板やメモで足跡を残す)。
3-4.情報の見極めと誤情報対策
- **「誰が」「いつ」「どこで」**を伴う情報を優先。出所不明は鵜呑みにしない。
- 自分の足元の状況(火災・水位・道路状態)が最優先の事実。
緊急連絡テンプレート(携帯メモ用)
| 宛先 | 内容の型 | 例 |
|---|---|---|
| 家族 | 無事/向かう先/人数/時刻 | 無事・桜公園へ・3人・10:20 |
| 親族(県外) | 状況/場所/次の行動 | 全員無事・自宅前→高台へ |
| 近隣 | 手助け要否/物資 | 水は足りる/ガス遮断済み |
4.備蓄配置と装備:家の“どこに何を置くか”まで決める
4-1.最低3日→望ましくは7日分
- 飲料水:1日1人3リットル(調理・歯磨き含む)。
- 主食:袋飯/缶パン/乾麺/クラッカーを調理不要→要湯→加熱の順でローテ。
- 簡易トイレ:1人1日5回分を目安。消臭剤・凝固剤・二重袋をセット。
- 灯り・情報:乾電池/手回し/ソーラーを重ね技に。電池は型を統一。
4-2.収納は“分散”が鉄則
- 玄関(持ち出し袋)/寝室(ヘッドライト・笛・靴)/台所(水・食料)/車内(ブランケット・水・カッパ)。
- 高所保管(浸水想定)と床置き回避(転倒・破損)を徹底。吊り戸棚の落下にも注意。
4-3.持ち出し袋の中身(大人1人の例)
| 分類 | 品目 | 目安 |
|---|---|---|
| 灯り | ヘッドライト/小型ランタン | 電池は型を統一 |
| 通信 | モバイル電源/ケーブル | 充電残量を月1確認 |
| 水・食 | 500ml×3/高カロリー食 | 期限のローテーション |
| 衛生 | 簡易トイレ/ウェット/マスク | 追加でポリ袋多数 |
| 保護 | 軍手/ホイッスル/靴 | 厚底の運動靴 |
| 情報 | 紙地図/家族名簿/筆記具 | 連絡テンプレ同梱 |
4-4.持病・アレルギー・ペットの備え
- 常備薬(7日分)と処方箋の写し、アレルギー表示カード。
- ペット:クレート・餌・水・トイレ砂・ワクチン控え。吠え対策の覆い。
4-5.車中避難・衛生・燃料
- 車中避難は換気・一酸化炭素・エコノミー症候群に注意。足首の体操と断続的な外気導入。
- 燃料:満タン習慣、携行缶は屋外・直射回避。
4-6.調理いらず“1日メニュー例”
| 食事 | 例 | 水使用量 |
|---|---|---|
| 朝 | クラッカー+缶詰果物 | 0 |
| 昼 | レトルトご飯+缶詰カレー | 少量(湯せん) |
| 夜 | パン缶+スープパック | 0〜少量 |
5.訓練と見直し:暦に組み込む“家族のルーティン”
5-1.月次10分訓練(家内)
- 夜間停電の想定:ヘッドライトで退路→玄関を歩き、段差・障害を修正。
- 遮断操作:ブレーカー・元栓の場所と手順を声に出して確認。子どもも役割を持つ。
- 救急の基礎:出血圧迫・三角巾代用(タオル)・骨折の固定のイメージ練習。
5-2.季節前見直し(梅雨前・台風前・年末)
- 家具固定・飛散防止の点検。L字金具・耐震ジェル・突っ張り棒の緩み確認。
- 液状化・津波想定に合わせ、集合場所と高台ルートを再確認。
- 消耗品の期限入替(ローリングストック)。水は6か月ごとに更新目安。
5-3.近所力の活用
- 要配慮者の所在(高齢者・乳幼児)を把握。声かけ順を決める。
- 井戸・発電機・道具の所在共有。貸し出しルールを紙に。
- 掲示板/ポストを伝言の足跡として活用。家単位のマーク(◎=在宅無事、△=外出中)を決める。
年間ルーティン表(拡張)
| 時期 | 実施内容 | 所要 |
|---|---|---|
| 毎月 | 夜間退路歩行/遮断確認 | 10分 |
| 梅雨前 | 浸水ルート/側溝確認 | 30分 |
| 台風前 | 飛散物固定/窓養生 | 30分 |
| 年末 | 備蓄総点検/マップ更新 | 60分 |
| 春秋 | 家具固定の点検/避難訓練 | 20分 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.マンションは上階だから津波は安心?
A. 建物自体の安全は相対的に高くても、階下の浸水や停電でエレベーター停止・給水停止が長引く可能性。物資・水の上階搬入計画、階段での運搬用キャリーの用意が必要です。
Q2.車で避難すべき?
A. 渋滞・道の寸断・津波の逆走で立ち往生のリスク。徒歩で高台へ向かう選択肢を優先。車は退路を塞がない位置に停め、キーの保管場所も家族で共有。
Q3.ペットはどうする?
A. クレート・餌・水・トイレをセット化。避難所ルールに合わせ、近隣の預け先や車中待機の換気も準備。
Q4.子どもが学校にいる時間帯は?
A. 学校の引き渡しルールを家族で共有。迎え不可のときの集合先(第2/第3)をマップに明記し、合言葉(短文)を決めておく。
Q5.地図アプリで十分では?
A. 停電・電池切れ・圏外の場面で紙の一枚が最後の拠り所。玄関・冷蔵庫・持ち出し袋に3部貼付/同梱が安心です。
Q6.家の中がガラス片だらけ…どう歩く?
A. 厚手の靴を履き、懐中電灯で足元を照らす。ほうき・ちりとりを玄関近くに常備すると復旧が早い。
Q7.ガス復帰はいつ?
A. 元栓は閉、臭いがないことを確認。復帰手順は落ち着いて行い、不安があれば専門家を待つ。
Q8.余震が続く中での就寝は?
A. 通路を確保し、倒れやすい家具から離れた位置に寝る。靴・ライト・笛を手の届く場所へ。
用語辞典(やさしい解説)
- 遮断ポイント:電気(ブレーカー)/ガス元栓/止水栓など、二次災害を防ぐために最初に操作する場所。
- 垂直避難:横へ逃げるより上階・高台へ上がる避難。津波・浸水時に有効。
- ローリングストック:ふだん使う食料を使い回しながら常に備蓄する方法。期限切れを防ぐ。
- 代替の代替:A案がダメならB、Bが無理ならCと三段階で用意する考え方。
- 要配慮者:高齢者・乳幼児・障がいのある人・妊産婦など、配慮が必要な人。
- エコノミー症候群:狭い姿勢で長時間過ごすと血栓ができやすくなる状態。足の体操・水分が重要。
- 液状化:地盤が振動で泥状になり、道路や建物が沈む現象。退路に影響する。
まとめ
家庭内マップ=家族の生存図です。退路・危険・遮断・備蓄・集合の5要素を紙一枚に重ね、10分の行動と72時間の流れを誰でも辿れる形に。
月次10分の訓練と季節ごとの見直しで現実に寄せれば、南海トラフ級の揺れでも迷わず動ける家になります。今日のうちに玄関・冷蔵庫・持ち出し袋へ3部を貼り、家族で声出し訓練と徒歩ルートの実踏を始めましょう。