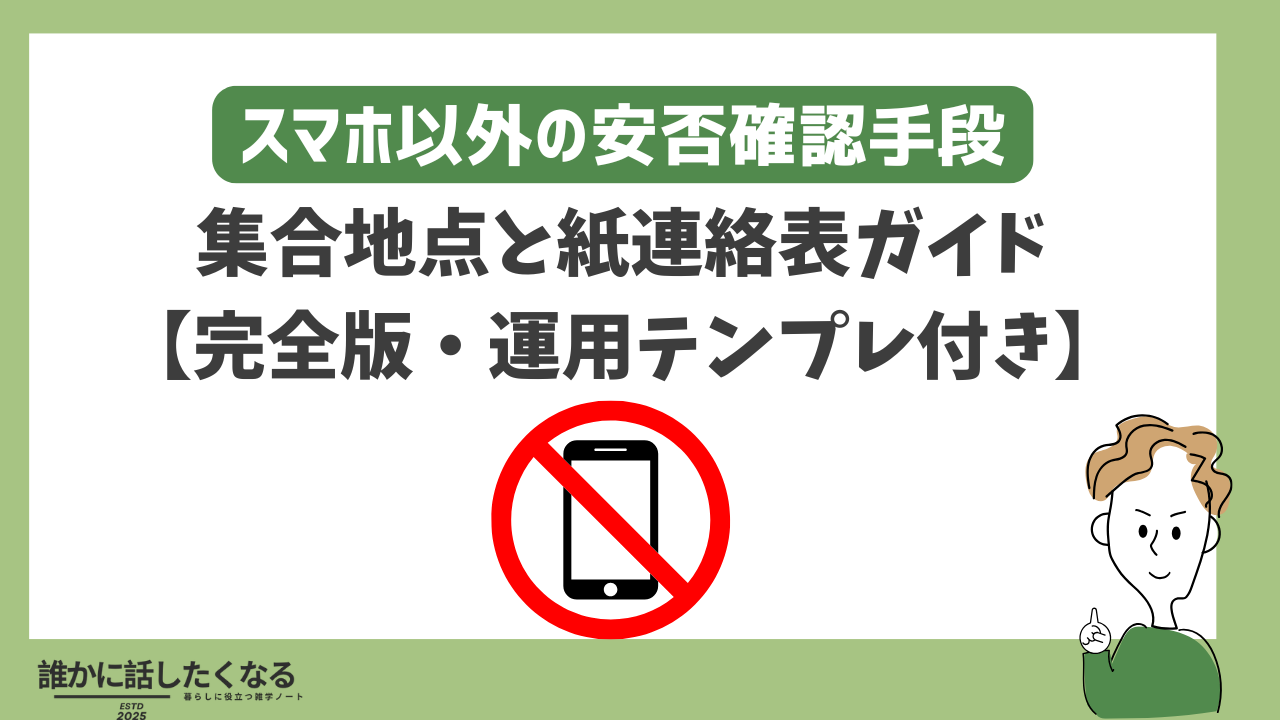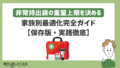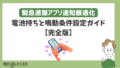なぜ「スマホ以外の安否確認」が必要か
回線輻輳・停電・基地局障害の三重リスク
大地震や大規模停電では、回線が混み合う(輻輳)、長時間の停電、基地局や中継設備の故障が同時に起きやすい。スマホ本体が無事でもつながらない・電池が切れる・圏外になることは珍しくない。災害時優先通信や通話規制が入れば、なおさら個人の連絡は通りにくい。だからこそ、スマホに頼らない連絡と集合の仕組みを平時から用意しておく必要がある。
家族で共通の「紙と場所」を持つ
安否確認の柱は、紙の連絡表と決めた集合地点である。電子機器が止まっても、紙は読めるし場所は消えない。紙と場所を同じ情報で結び、誰が見ても同じ動きを再現できるようにしておく。特に幼児・高齢者・日本語が不慣れな家族には、ふりがな・地図の絵・写真での補助が効く。
3段構えで途切れない連絡線
1)家庭内(家の中)、2)生活圏(学校・職場)、3)広域(親戚・避難先)の3段構えにして、それぞれで紙・掲示・掲示板の手段を持つ。冗長に見えても重複こそ安全である。どの段で連絡が切れても、次の段が拾い上げる構造にしておく。
集合地点の決め方|一次・二次・最終
一次集合(家の近く)を30分で到達できる場所に
最初に集まる場所は、自宅から徒歩30分以内で、倒壊・火災・落下の危険が少ないひらけた空間にする。具体的には公園の中央広場・学校の校庭・河川敷の広いスペースなど。高架下・看板のそば・電柱の直下・ガラス張りの前は避ける。雨天や夜間でも見つけやすいように、時計台・案内板・特徴的な樹木など動かない目印をひとつ決める。
二次集合(生活圏の中心)で合流を確実に
通学・通勤エリアの中心に二次集合を設定する。最寄り小中学校の体育館前、区役所・公民館の敷地入口、駅前の広場の“像の前”など、誰でも場所を説明できる目印があることが条件。一次に来られない人は二次に直行のルールで迷いを減らす。徒歩での迂回路を紙地図に描き、橋・踏切・トンネルの代替も用意する。
最終集合(広域避難先)で一日を締める
家が使えない場合に備えて、親戚や友人の家、広域避難所など最終集合を決めておく。公共交通が止まる前提で徒歩や自転車で行けるかを確認し、日没までに到着できる距離を上限とする。到着したら連絡札を掲示し、翌日の集合時刻を決めたうえで休む。
季節・時間帯で変わる注意点
夏は日陰の確保と給水、冬は風よけと保温が重要。夜間は街灯・非常灯の有無を事前に調べ、反射材やライトの点滅合図を家族共通にしておく。雨天時はぬかるみ・増水で河川敷が使えないことがあるため、雨天用の代替地点を一つ用意する。
集合地点の選定チェック表
| 観点 | 一次 | 二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 徒歩時間の目安 | 〜30分 | 30〜60分 | 60分超(現実的範囲) |
| 危険の少なさ | 倒れ物・落下物が少ない | 公的施設で安全管理 | 宿泊・受け入れ可否 |
| 目印 | 広場中央・時計台 | 体育館入口・庁舎門 | 表札・施設看板 |
| 夜間の見通し | 街灯あり | 非常灯あり | 連絡札を掲示して誘導 |
| 雨天時の代替 | 近隣の屋根付き広場 | 公共施設のピロティ | 受け入れ先の屋根・庇 |
紙の連絡表を作る|家族カードと集合掲示
家族カード(携帯用)に必ず入れる項目
氏名(ふりがな)/生年月日/血液型/持病・服薬/アレルギー/緊急連絡先(3件以上:近所・親戚・職場)/集合地点(一次・二次・最終)/通学・通勤ルートの目印/避難所名。カードは名刺サイズで作り、ラミネートか厚手の透明ケースに入れて財布・定期入れ・ランドセルへ。裏面にはホイッスルとライトの合図、家族のコールサインを書いておくと、緊張時でも思い出せる。
家族掲示(家の玄関)で伝言を残す
家庭内に伝言用の掲示板(A4クリアファイルで可)を玄関脇に設置。外出時は誰が・どこへ・何時に・誰とを太字で書き残す。災害時は**「無事・軽傷・搬送・不在」の四択をチェック形式にして素早く記録できるようにする。黒の太字→誰でも読める/赤の細字→補足など筆記ルール**を家族で統一する。
集合地点専用の連絡札
一次・二次・最終の各地点に貼れるよう、防水の連絡札を複数枚作って持出袋に常備。内容は氏名・日時・次の移動先・同行者の数。貼る場所は目立ちすぎず、探せば見つかる高さ(目線〜少し上)に。個人情報は最小限にとどめる。はがす担当を決めて情報の古さが残らないようにする。
子ども・高齢者向けの工夫
子ども用は大きな文字と絵記号、高齢者用はふりがな・服薬欄を広めに。写真入りにすると確認が早い。外国語表記が必要な家族・友人がいる場合は、日本語+ふりがな+簡単な英語の三段表記にする(読みやすさ優先)。
家族カード(携帯用)のひな型(例)
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 氏名 | 山田 太郎(やまだ たろう) |
| 生年月日 | 1985/07/14 |
| 血液型 | O |
| 持病・服薬 | 高血圧/朝晩1錠 |
| アレルギー | そば・スギ花粉 |
| 緊急連絡1 | 祖母:山田花 000-0000-0000 |
| 緊急連絡2 | 会社代表 000-0000-0000 |
| 緊急連絡3 | 近所:佐藤 000-0000-0000 |
| 集合(一次) | ○○公園 時計台前 |
| 集合(二次) | △△小体育館入口 |
| 集合(最終) | 親戚宅(□□市□□) |
| 合図 | 3短=助けて/1長=集合/2回点滅=合流 |
スマホ以外の安否確認手段|紙・無線・掲示
伝言板・張り紙(紙の力を最大に)
家の玄関・集合地点・職場入口に統一フォーマットの張り紙を使う。矢印と時刻だけでも情報価値は高い。油性ペンと養生テープを常備し、雨に強い紙(耐水紙・ラミネート)で作っておくと、一晩の雨風でも読める。路面にはチョークで矢印、柱には結束バンドで札など素材に合わせた留め方を準備する。
ホイッスル・合図(音と光の合図)
3回短く吹く=助けて、1回長く=集合開始など、家族ルールの合図を決める。ライトの点滅も合図に使える(3回=異常、2回=合流、1回長=移動開始)。夜間は反射材を身につけ、探す側が見つけやすい格好で動く。合図の誤用を防ぐため、練習日を月1回設ける。
トランシーバー(簡易無線)
家族や近隣で特定小電力トランシーバーを用意すると、数百メートル〜1km程度で連絡がとれる。チャンネルとコールサイン(呼び名)を紙に書いて家族カードに同封。電池式を選ぶと停電でも運用しやすい。通信の定型(呼び名→応答→要件→復唱→終了)をメモ化しておく。
防災行政無線・ラジオの併用
屋外拡声器の放送は屋内では聞こえにくいことがある。小型ラジオ(AM/FM)を乾電池で保管し、避難所開設・給水所などの情報を拾う。周波数のメモを家族カードと同じ場所に入れておくと、誰でも即座に合わせられる。
近隣掲示板・自治会ルート
自治会の掲示板・回覧板を災害時の情報ハブにする。掲示担当や連絡係を平時から決め、避難所掲示板→自治会板→各戸の一方通行の矢印で情報を流すと混乱が少ない。役割分担表を印刷して冷蔵庫に貼り、代理担当も記入しておく。
手段ごとの強みと弱み(比較表)
| 手段 | 強み | 弱み | そなえ |
|---|---|---|---|
| 紙の張り紙 | 電源不要・誰でも読める | 個人情報の露出 | 最小限の情報にする |
| ホイッスル | 電池不要・遠くへ届く | 風で届きにくい | 合図の意味を共有 |
| ライト合図 | 夜間に強い | 昼は見えにくい | 予備電池を添える |
| トランシーバー | 同時双方向 | 距離・障害物に弱い | チャンネル・呼び名を固定 |
| ラジオ | 広域情報が早い | 双方向ではない | 周波数のメモを同封 |
連絡ルートを設計する|時刻と動線のルール
30分待って来なければ「次の地点へ」
一次集合に**時刻の締切(例:発災後2時間以内)を決め、30分待って来なければ二次へのルールで動く。待ち続けないことが生存率を上げる。張り紙に移動先と時刻を書き、全員が同じ動きをする。遅延時の備考欄を作って、「AはBを迎えに行く」**などの行動を短文で残す。
子ども・高齢者の移動ルール
子どもは学校→二次集合へ直行。迎えが必要な場合は迎え役を紙に書いて固定する。高齢者は最短・平坦ルートを紙の地図に太線の矢印で記す。階段・工事中・水たまりなどの注意点も紙に書いておく。迷ったら戻る地点(安全な広場や交差点)も指定する。
会社・学校・自宅の三角連絡
会社と学校、自宅の三点で同じフォーマットの紙を使う。誰が見ても同じ意味になるよう、「氏名・時刻・次の目的地」の三行だけで書く。長文は読まれにくいことを前提に、矢印と時刻を大きく書く。
伝言の書き方(短く・正確に)
- 氏名(名字のみでも可)
- 今の時刻
- 次に向かう場所
- 同行者の数(子1・大2など)
- 簡単な状態(無事・軽傷)
移動と連絡のフローチャート(詳細)
1)発災→身を守る→安全確保。
2)家の掲示板に伝言→一次集合へ。
3)30分待機→来なければ二次集合へ移動。
4)張り紙を残す→最終集合へ合流。
5)到着確認→家族カードのチェック欄に丸→翌日の集合時刻を決める。
時間割の例(平日昼間の発災)
| 時刻 | 行動 | 紙で残す要点 |
|---|---|---|
| 12:10 | 身の安全確保 | 家族名・無事・現在地 |
| 12:30 | 会社・学校で集合 | 二次集合の時刻 |
| 13:30 | 二次→最終へ移動開始 | 矢印と到着予定 |
| 15:30 | 最終集合・点呼 | 翌日の集合時刻 |
紙・無線を運用する道具|軽く・濡れない・なくさない
最小セット(各人が持つ)
油性ペン(太・細)/A6メモ(耐水)/養生テープ/家族カード/ホイッスル/小型ライト(頭につけるタイプ)。これだけで書く・貼る・知らせるが回せる。胸ポケット・首下げですぐ取り出せる位置に置く。笛とライトは就寝時も枕元に置く習慣をつける。
家族共用セット(持出袋に)
A4耐水用紙/ラミネート袋/クリップボード/替え電池/トランシーバー(電池式)/地図(紙)/結束バンド/チョーク。地図には集合地点を赤丸と矢印で印し、徒歩ルートの所要時間を書き込む。方位磁石があると迂回時も迷いにくい。
紙・無線の保護と更新
紙はクリアファイル+ジッパー袋で二重に。年に1回、連絡先・集合地点を見直す。引っ越し・進学・転職のたびにその日のうちに差し替えるのが理想。古いカードは予備として封筒に入れて保管し、色で見分けられるようにする。
持ち物と役割の割り当て表(例)
| 品目 | 持つ人 | 予備 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 家族カード | 全員 | — | 財布・定期入れに常備 |
| ホイッスル | 全員 | 2個 | 首下げで携行 |
| 耐水メモ+油性ペン | A・B | — | 1人は太字、もう1人は細字 |
| トランシーバー | A・C | 予備電池 | 呼び名とチャンネルを固定 |
| 地図(紙) | B | 予備1 | 赤丸と矢印の手書きでOK |
| ラミネート袋 | C | 5枚 | 札・カードを防水 |
| 結束バンド | A | 10本 | 札の固定・簡易修理 |
訓練と見直し|10分で回す家族ドリル
月1回・10分の確認で定着させる
家族全員でカードの位置確認→合図の練習→玄関掲示の更新までを10分で回す。子どもは笛3短・ライト2回点滅を、目をつぶってもできるまで繰り返す。高齢者は筆記具の置き場所と眼鏡の予備も合わせて確認する。
半年に1回・道順の実踏(一次→二次)
実際に一次から二次へ歩く。坂・段差・工事中の箇所を地図に追記し、到着時刻を書き込む。暗くなる前の帰宅を原則とし、雨天回も一度は実施する。学校・職場が変わったらその週のうちに道順を更新する。
模擬張り紙と情報更新のリハーサル
玄関に模擬の連絡札を貼り、家族が順に短文で記入する練習をする。「名字+時刻+次の場所」の三点のみで済ませる訓練をすると、実際の緊張時でも迷わない。
Q&A(よくある疑問を短く解決)
Q1.張り紙で個人情報が心配。
A.名字+時刻+次の場所の三点だけで十分。電話番号や住所は書かない。紙ははがす担当が回収する。
Q2.集合地点にたどり着けない道路がある。
A.第二ルートを紙の地図に矢印で書いておく。橋・踏切・トンネルは迂回案も記載。雨天用の代替地点も用意。
Q3.ホイッスルの合図を忘れそう。
A.家族カードの裏に合図の意味を書いておく。3短=助けて、1長=集合、2点滅=合流など。月1回の練習で定着する。
Q4.トランシーバーは使いこなせる?
A.月1回・3分の練習で十分。呼び名→応答→要件→復唱→終了の定型を覚える。電池残量は毎月点検。
Q5.夜間に子どもを探すコツは?
A.反射材のたすきと頭につけるライトを常時携行。高い声で名前を短く呼ぶと届きやすい。合流後はライトを2回点滅で合図。
Q6.家族が別々の自治体にいる。
A.最終集合を中間地点の公的施設に設定し、地図と所要時間を紙で共有。着いたら掲示→合流→翌日の時刻決めを繰り返す。
用語辞典(やさしい言い換え)
安否確認:家族や仲間が無事かどうか確かめること。
集合地点(一次・二次・最終):順番に集まる場所。来られなければ次へ進む。
掲示板:紙を貼って知らせる場所。
輻輳(ふくそう):電話や通信が混み合ってつながらない状態。
コールサイン:トランシーバーで呼ぶ決めの名前(例:「タロウ1」)。
耐水紙:雨でもにじみにくい紙。
緊急放送:自治体や放送局が行う災害情報の放送。
まとめ
スマホが沈黙する日でも、紙・場所・合図・無線があれば連絡線は途切れない。一次→二次→最終の三段集合と、家族カード+玄関掲示+連絡札を今日作っておく。重複は安全である。書く・貼る・集まるを習慣にし、月1回10分の訓練で手順を体に入れておけば、どんな夜でも再会できる。