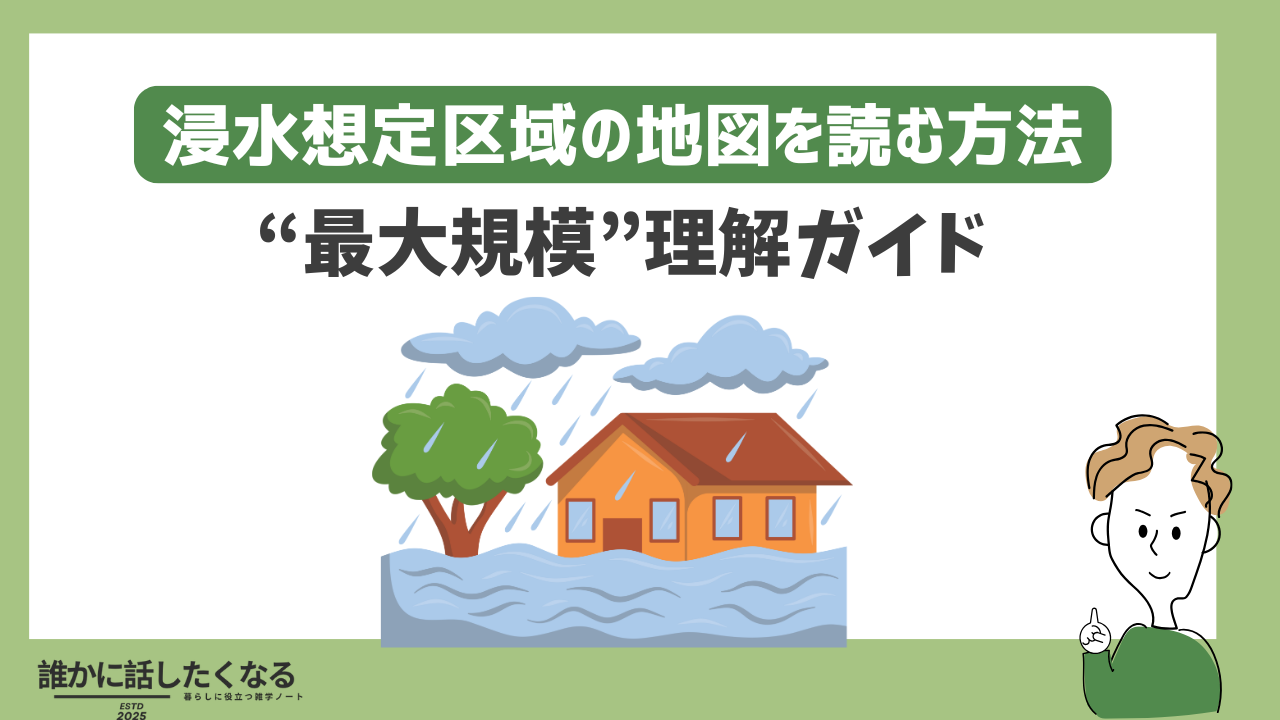浸水想定区域図は、豪雨や河川はんらんで「どこまで・どれくらい深く・いつ頃」水が来るかを色と数値で示した“行動の地図”です。色の読み違い、縮尺の勘違い、「最大規模」の誤解が重なると、数十分の遅れが命取りになります。本ガイドは、凡例→深さ→時間→地形→行動の順で整理し、地図を自宅基準の行動計画へ落とし込む具体手順を解説。家族・職場でそのまま使える表・チェックリスト・短文テンプレも収録しました。
浸水想定区域図の基本をそろえる(凡例・色・尺度)
1)凡例の“3要素”を先に確定
- 浸水の種類:河川はんらん/高潮/内水(下水あふれ)で色の意味が変わる。同じ色でも対象が違えば危険の質が違う。
- 深さの区分:例)0.5m未満/0.5〜3.0m/3.0〜5.0m/5.0m以上。境界値(0.5m・1.0m・2.0m)に注目。
- 時間情報:家屋到達時間(例:30分以内・1時間以内)や浸水継続時間のレイヤーが別図で用意されることがある。
2)縮尺と基準面を合わせる
- 縮尺:100mが地図上で何cmかを把握し、徒歩分数に換算。夜間・雨中でも移動可能かを現実目線で評価。
- 標高・地盤高:等高線や陰影起伏図で自宅と河川の高低差を確認。川より低い地盤は長時間滞水しやすい。
- 方角:北向き矢印を確認し、風向(押し戻し)や海側・川側の関係を意識。
3)「色=水深」を生活単位へ変換
- 0.5m(床下〜ひざ):玄関・駐車場が使えない。ブレーカー・家電低所に注意。
- 1.0m(腰):ドア圧着で開閉困難。屋内移動が難しい。
- 2.0m(胸)以上:1階ほぼ使用不能。屋外歩行は流れで危険。
水深と影響の早見表(目安)
| 水深の目安 | 屋外の状態 | 屋内・生活影響 | 行動の原則 |
|---|---|---|---|
| 0.3m | 足首〜ふくらはぎ。段差が見えない | 床下浸水リスク | 外に出ない、排水口は開放 |
| 0.5m | ひざ。軽自動車は走行困難 | 家電・配電盤に注意 | 早期退避、車は中層へ |
| 1.0m | 腰。ドア圧着・歩行不可 | 1階ほぼ使用不能 | 上階避難、救助要請も検討 |
| 2.0m+ | 胸〜頭。流れ強い | 屋内滞在も危険 | 屋外移動禁止、屋根・高所へ |
ポイント:色は“深さ”、時間図は“余裕”、等高線は“逃げやすさ”を教える。
“最大規模”の正しい理解(上限を知り、行動を先取り)
1)定義:最悪の宣告ではなく“上限の目安”
行政の想定最大規模は、過去事例・地形・統計を元にした極めてまれな雨量・はんらん規模での上限想定。毎回起きる前提ではないが、起きたらそこまで達しうるラインです。
2)ありがちな誤解を正す
- 誤:最大規模=必ずその深さ → 正:達しうる深さ。だから逃げ遅れない高さ・経路を先に決める。
- 誤:薄色=安全 → 正:薄色でも到達が早い/流速が速いと危険。
- 誤:最大図だけ見れば十分 → 正:計画規模や到達時間図も重ね、時間差で動く。
3)住まい・備えへの反映
- 電源の高所化、室外機・給湯器のかさ上げ、車の中層駐車を平時に固定。
- 在宅上階避難の部屋と外部高所(高台・中層P)を家族カードに明記。
- 夜間ルート(街灯多・段差少)を別途設定。
最大規模×準備の対応表
| 地図の最大水深 | 住まいの備え | 避難方針 |
|---|---|---|
| 0.5m未満 | 配電高所化・屋外機器の脚上げ | 在宅上階で様子見 |
| 0.5〜2.0m | 1階機能の上階移設・家財上げ置き | 上階避難を標準、外部退避も併記 |
| 2.0m以上 | 1階は通路のみ・はしご準備 | 早期に外部退避、車は事前移動 |
自宅基準に落とす3ステップ(住所→深さ・時間→避難線)
1)位置を“点”で決める(入口基準)
地図上で玄関・ガレージの入口にピンを置く。敷地に高低差があるなら最低地点にも印。坂の下・交差点角は要注意。
2)ピンの“色(深さ)”と“矢印(流れ)”を読む
色=最大水深、矢印=流れの向き。合流点・坂の下・橋のたもとへ向かう矢印は危険。家屋到達時間が短い所は早行動が鉄則。
3)時間レイヤーで“何分の余裕”かを把握し、避難線を引く
到達時間図があれば重ね、T–60/–30/–15分の行動を決める。上階→中層P→公民館高層階など複数の高所へ線で結び、夜間でも迷わない距離か確かめる。
自宅→避難先の書き込み表(記入式)
| 項目 | 記入例 | 我が家の設定 |
|---|---|---|
| 自宅ピンの色(最大深さ) | 0.5〜2.0m | |
| 到達時間の目安 | 1時間以内 | |
| 上階避難部屋 | 2階北側洋室 | |
| 外部避難先(徒歩) | 中層立体P 3階 | |
| 車の待避場所 | 立体P 3階A区画 | |
| 夜間の合図 | 懐中電灯×2・短文連絡 |
コツ:地図上の“線”は、段差・暗がり・狭い歩道を避けて引く。現地で一度歩いて確認。
地図から“行動”へ:合図・タイムライン・持ち物
1)合図は短文・定刻・同じ言い回し
- 毎時00/30分に「色:○、時間:○→上階/外部」の短文で家族共有。
- 例:「色1.0m・到達1h→2階集合」「2.0m・30分→中層Pへ移動」。
2)タイムライン(例:到達1時間・最大1.0m)
- T–60分:車を中層へ、ベランダ排水・玄関桝の解放。
- T–30分:上階へ移動、電源の高所化(延長コード撤去)。
- T–15分:外部退避を最終判断、応急持ち出し。
- T–0分:出歩かない、上階で待避。
3)持ち物・役割のミニマム
- ヘッドライト・携帯電源・貴重品・常用薬・飲料・手袋・靴。
- 役割:合図担当(短文送信)、移動先案内(地図と鍵)、戸締り(ブレーカー・ガス)。
行動フロー早見表(色×時間)
| 最大水深の色 | 到達時間 | 基本方針 | 重点行動 |
|---|---|---|---|
| 0.5m未満 | 1h以上 | 在宅上階 | 排水確保・車中層 |
| 0.5〜2.0m | 1h以内 | 上階→外部も検討 | 早期移動・持ち出し |
| 2.0m以上 | 30分以内 | 外部退避優先 | 直近高所へ短距離移動 |
よくある疑問と用語・仕上げチェック
1)Q&A(よくある疑問)
Q1. 「最大規模」以外の図も見るべき?
A. 計画規模や到達時間図も確認。最大=深さ、時間図=余裕を示す。両輪で判断。
Q2. 薄色エリアなら車で移動してよい?
A. 不可。浅くても早い・速いは危険。アンダーパス・低地を避け、中層駐車へ先に移動。
Q3. 自宅が白抜き(対象外)。準備は要らない?
A. 要る。内水(下水あふれ)・側溝詰まりで浸水あり。排水口の解放と近隣高所を準備。
Q4. 地図が古そう。どう補う?
A. 開発状況・盛土・道路改良など最新の地形変化を現地で確認し、安全側に補正。
Q5. 高台が遠い。代替は?
A. 在宅上階+中層P・学校上階など**“近い高所”を複数設定。夜間は街灯ルート**を優先。
2)用語辞典(やさしい言い換え)
- 浸水想定区域:大雨などで水につかる可能性がある範囲。
- 想定最大規模:とてもまれだが起きたら最大クラスの雨を前提にした上限の見積り。
- 家屋到達時間:水が家に届くまでの時間。
- 内水/外水:下水・側溝があふれる/川や海があふれる。
- 等高線:同じ高さを結んだ線。高低差の把握に使う。
- 上階避難:建物の高い階へ移って身を守る方法。
3)仕上げチェック(掲示用)
| 項目 | 実施 | 備考 |
|---|---|---|
| 自宅ピン・避難線を書いた | □ | 夜間ルートも作成 |
| 家屋到達時間を確認 | □ | T–60/–30/–15分に分解 |
| 持ち物と役割を決めた | □ | 合図担当・案内・戸締り |
| 車の中層駐車を確保 | □ | 代替地も確認 |
| 家族カードを掲示 | □ | 玄関/冷蔵庫に貼付 |
まとめ:地図は“逃げる順番”を決める道具
色は深さ、時間図は余裕、等高線は逃げやすさを教えます。凡例→深さ→時間→地形→行動の順で読み、自宅ピンと避難線を今日5分で書き込みましょう。最大規模は“恐怖の宣告”ではなく、逃げ遅れない高さと経路を決める上限のガイド。合図・タイムライン・持ち物をそろえ、次の雨で迷いゼロを実現してください。