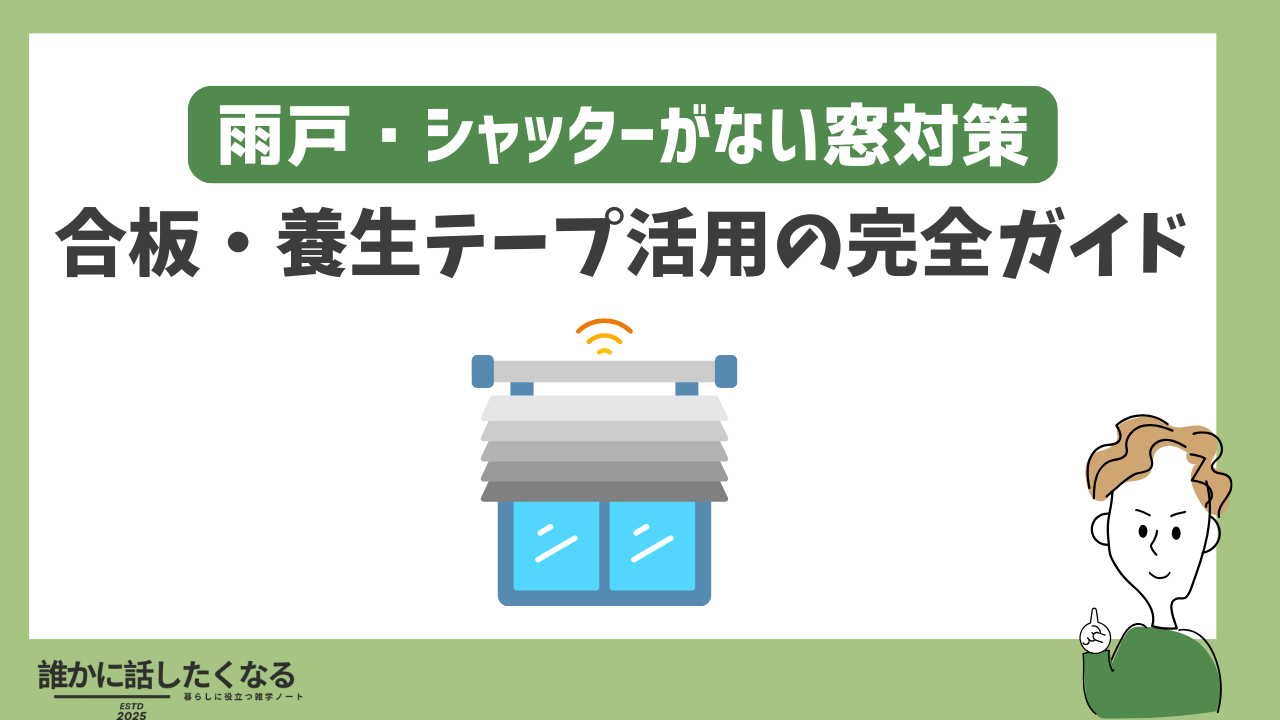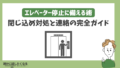強風・飛来物・横殴りの雨は、雨戸やシャッターがない窓にとって大きな弱点です。とはいえ、合板・ポリカ板・養生テープ・補助金具を正しく使えば、短時間でも被害を大幅に減らすことは可能です。
本ガイドでは、準備→固定→養生→退避→復旧の順に、家庭で再現できる手順を徹底的に整理しました。必要な道具、サイズの決め方、固定位置、テープの貼り方、窓種別ごとの注意点、そしてやってはいけないことまで、表とチェックリストで迷わず実行できます。最後に、賃貸でもできる方法、高所で無理をしない代替案、保管と再利用のコツまで踏み込みます。
1.方針を決める:窓のタイプと外力を見極める
1-1.自宅の窓タイプを把握
- 引き違い窓:戸が左右に動く一般的な窓。中央の合わせ目が弱点。
- 掃き出し窓:床まである大きな窓。飛来物と風圧に弱い。
- はめ殺し窓(FIX):開閉しない窓。枠の剛性は高めだが、ガラス面が広い。
- 小窓(トイレ・浴室):面積が小さく室内二重化が効きやすい。
- 型板ガラス・網入りガラス:割れても飛散しにくいが、熱・風圧でひびが広がることがある。
1-2.外力の想定(風速×飛来物)
- 10m/s級:小物が飛ぶ。軽い養生と小物撤去で対応。
- 15〜20m/s:プランター・物干し台が動く。合板・補助金具の出番。
- 25m/s超:看板・波板が外れ得る。屋内退避を優先し、施工は前日までに完了。
- 瞬間風速の山が予想される時間帯は、一段上の対策に格上げ。
1-3.対策の大原則
- 外の飛散物をゼロに(撤去・固定)。
- 窓を面で守る(合板で受ける/室内側で二重化)。
- すき間風と破片の飛散を抑える(養生テープは枠周り重視)。
- 人が安全であることを最優先(高所での無理な作業はしない)。
1-4.風向面の優先度(どの窓から守るか)
- 風上(真正面)>角(建物の曲がり角)>上階の大窓>道路側の順で優先。
- 片側だけ対策する場合は、風上面の掃き出し窓から着手。
1-5.構造別・居住形態別の考え方
- 木造(戸建):柱・梁の位置を探してL金具が効きやすい。
- RC(マンション):外側施工が難しい場合が多く、室内二重化+枠周り封止が主戦術。
- 賃貸:穴開け不可が基本。仮枠・突っ張り・室内板で対応。
構造×居住形態×工法の適合表
| 住まい/工法 | 外側合板+金具 | 外側合板(外構固定) | 室内二重化(仮枠+板) | テープ主体 |
|---|---|---|---|---|
| 木造・持ち家 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 木造・賃貸 | △ | ○(外構許可要) | ◎ | ○ |
| RC・持ち家 | △ | △ | ◎ | ○ |
| RC・賃貸 | × | △ | ◎ | ○ |
×は原則不可/△は条件次第/○は有効/◎は最有効の目安。
2.材料と道具:サイズ決めと買い出し計画
2-1.材料の選び方(入手しやすさ優先)
- 構造用合板 9〜12mm:風雨に強く、面で受ける。外部用には12mmを推奨。
- OSB合板 9〜12mm:入手性が高い。端部のささくれを紙やすりで処理。
- ポリカーボネート中空板(4〜8mm):室内側の二重化に有効。軽く割れにくい。
- 押さえ板(30×90mm程度の角材):合板の縁を面で押さえるための部材。
- L金具(ステンレス)+コーチスクリュー:外壁の柱・下地に固定して合板を締結。
- 養生テープ+布テープ:枠周りの封止と仮固定。米字貼りは補助(破壊防止ではない)。
- 発泡スペーサー(10〜20mm):合板とガラスの当たり防止。
- 防腐塗料:再利用を見込む合板の耐久アップ。
2-2.道具(最低限+あると便利)
- 最低限:メジャー、差し金、鉛筆、充電ドライバー、下穴ドリル、軍手・保護メガネ、脚立、カッター、ロープ。
- あると便利:スタッドファインダー(柱探し)、紙やすり、面取りカンナ、ヘッドライト、シーリング材。
2-3.サイズ決め(採寸のコツ)
- 開口寸法(W×H)+左右・上下それぞれ+30〜50mmが合板寸法の目安(枠を覆う)。
- 2枚貼りの場合は下側先行→上側重ねで雨水の侵入を抑える。
- サッシの出っ張りや手すりを避けるため、紙型を作ってから切断すると失敗が少ない。
- 合板は端部を面取りすると割れにくく、テープも密着しやすい。
代表寸法と材料の目安表
| 窓の大きさ | 合板寸法(外側) | 固定点 | 追加材 | 参考枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 小窓 600×600 | 700×700 | 4点 | スペーサー | 1枚 |
| 腰窓 900×1000 | 1000×1100 | 6点 | 押さえ板 | 1〜2枚 |
| 掃き出し 1650×2000 | 1750×2100 | 8〜10点 | 押さえ板+補助桟 | 2〜3枚 |
2-4.費用と買い出しの順番(混雑前に)
| 品目 | 目安単価 | 必要数(腰窓1か所) | 小計の目安 |
|---|---|---|---|
| 構造用合板12mm | 中 | 1枚 | 中 |
| 押さえ板 | 低 | 2〜3本 | 低 |
| L金具+ビス | 低〜中 | 4〜6組 | 低〜中 |
| 養生テープ+布テープ | 低 | 各1巻 | 低 |
| スペーサー | 低 | 4個 | 低 |
買う順番:合板→押さえ板→金具→テープ→スペーサー。直前は売切れやすいため前日までに確保。
3.施工手順:外部合板→室内二重化→枠周り養生
3-1.外部合板の取り付け(基本形)
- 撤去・清掃:ベランダ・庭の飛散物ゼロ。窓周りの汚れを拭く。
- 仮合わせ:スペーサーを四隅に置き、ガラスに直当てしない。
- 固定金具の位置決め:窓左右の柱位置(外壁ビスの並びで推定)にL金具を仮止め。
- 押さえ板+ビス固定:合板の外周に押さえ板(30×90mm程度)を当て、**等間隔(150〜200mm)**で締める。
- すき間封止:合板の周囲を養生テープ→布テープの順に重ねて雨の吹込みを減らす。
- 最終点検:角の浮き・ビス緩みがないかを触って確認。
3-2.室内側の二重化(賃貸や高所向け)
- 仮枠(2×2材)でサッシ内側にはめ込み枠を作る。
- ポリカ板または薄合板をビス/結束バンドで固定。
- 緩衝材(発泡パッキン)を壁・ガラス接触部に入れて共振を軽減。
- 枠周り封止:サッシと板のすき間をテープで連続封止。
3-3.枠周りの養生(割れ・すき間対策)
- テープは“枠周り”優先:四辺のサッシ枠とガラスの境目を連続で封止。
- 米字貼りは補助:破片の飛散軽減が目的。破壊防止ではないことを理解。
- クレセント(カギ)の上下に短冊テープを貼り、合わせ目のがたつきを抑える。
- 排水溝・換気口をテープで完全に塞がない(結露・漏水の原因)。
3-4.代替工法(外壁に穴を開けられないとき)
- 突っ張り棒+内桟+板:窓内側に上下突っ張り→横桟→板で圧着(毎時点検)。
- ベランダ手すり固定:手すりにロープ・ラチェットベルトで合板を外付け(共用部は管理規約を確認)。
- 外構フェンス固定:窓正面に支柱を仮設し、そこへ合板を固定(転倒防止の下部重し必須)。
施工チェックリスト(現場で使える)
| 工程 | 確認点 | 完了 |
|---|---|---|
| 撤去・清掃 | 飛散物ゼロ/窓周り清掃 | □ |
| 仮合わせ | スペーサーあり/干渉なし | □ |
| 金具位置 | 柱推定位置に設定 | □ |
| 固定 | 周囲等間隔で締結(150〜200mm) | □ |
| 封止 | 枠周り→上端→側面→下端の順 | □ |
| 室内二重化 | 仮枠ガタつきなし | □ |
| 代替工法 | 毎時点検の計画あり | □ |
4.よくある失敗と回避策:破損・浸水・共振
4-1.合板が風で“鳴く”(共振)
- 症状:ドンドンと低い音が続く→ビス間隔が広い/押さえ板が短い。
- 対策:押さえ板を追加、ビス間隔を150〜200mmに、中央に横桟を足す。
4-2.雨が回り込む(浸水)
- 症状:合板の下から水滴、室内の敷居に水。
- 対策:上側を外側重ねにし、上端のテープを二重。下端に水切り(薄板)を付ける。
4-3.ガラスが先に割れる
- 症状:合板の角が当たる、テープのみで安心していた。
- 対策:スペーサーで浮かす、室内二重化を同時に行う。米字だけは不可。
4-4.下地にビスが効かない/位置が分からない
- 症状:ビスが空転する、手応えがない。
- 対策:スタッドファインダーで柱を探す、押さえ板の幅を広げて複数箇所で固定。
4-5.結露・カビが出る
- 症状:窓周りが湿る、黒ずむ。
- 対策:風下側の小窓を短時間換気、除湿剤、封止し過ぎない(排水経路を確保)。
失敗→対策 早見表
| 失敗例 | 原因 | すぐできる対策 |
|---|---|---|
| 合板が鳴る | 固定点不足 | 押さえ板追加・ビス間隔200mm以内 |
| 水が回る | 上端のかぶせ不足 | 上→側→下の順にテープ二重 |
| ガラス割れ | 直当て・飛来物 | スペーサー+室内二重化 |
| ビス効かず | 下地不明 | 柱探索+幅広押さえ板 |
| カビ発生 | 密閉し過ぎ | 風下側小窓で短時間換気 |
5.当日の運用と復旧:退避場所・撤去・後処理
5-1.待機のしかた(割れてもケガしない)
- 風下側の部屋、窓の少ない中央寄りで待機。
- 足元は厚手の靴、手袋を手元に。割れた後は無理に片付けない。
- 停電備え(ライト・モバイル電源・ラジオ)を手の届く範囲にまとめる。
5-2.撤去の順序(安全第一)
- 風が弱まるまで待つ。脚立作業は無理にしない。
- 上からビスを外す→押さえ板→合板の順に。風上側から外すとあおられにくい。
- テープ糊は中性洗剤→ぬるま湯→専用リムーバーの順で。
- 写真で記録(合板・金具配置・不具合)。次回の改善資料にする。
5-3.点検と次回への改善
- サッシのがたつき、ガラスの微細な欠け、シール材の割れを確認。
- 合板は乾燥させ、防腐塗装で再利用性アップ。次回用の穴位置をマーク。
- 部屋ごとの保管札を作り、どの窓にどの板か一目で分かるようにする。
復旧・保管チェック表
| 区分 | すること | 完了 |
|---|---|---|
| サッシ | ガタ・鍵・レール点検 | □ |
| ガラス | 欠け・ヒビ点検 | □ |
| テープ跡 | 洗剤→ぬるま湯→専用剤 | □ |
| 合板 | 乾燥・防腐塗装・保管札 | □ |
| 写真 | before/afterを保存 | □ |
Q&A(よくある疑問)
Q1. 養生テープの米字貼りだけで大丈夫?
A. 不可です。米字は破片の飛散を減らすだけ。合板やポリカで面で受ける対策が基本です。
Q2. 賃貸で壁に穴を開けられない。
A. 室内側の仮枠+ポリカ板で二重化し、枠周りの封止を徹底。突っ張り棒+押さえ板を併用する方法もあります。
Q3. 何mmの合板を選べばいい?
A. 外部は12mmが目安。風当たりが強い面や上階は押さえ板と固定点を増やしてください。
Q4. 台風直前で合板が買えない。
A. ポリカ中空板+段ボール重ね+仮枠でもないより数段良い。室内側二重化を急ぎ、外の撤去を優先しましょう。
Q5. ガラスが割れたあと、塞ぐ最短手段は?
A. 厚手の養生シート+ベニヤの仮当て。枠周りを先に封止し、後で押さえ板で補強します。
Q6. 合板は外側・内側どちらが良い?
A. 外側が基本(飛来物の直撃を面で受ける)。高所・賃貸は内側二重化を主にし、可能なら外側も併用。
Q7. どのテープが良い?
A. 養生テープは剥がし跡が少ない。布テープは補強用。ガムテープは糊残りが多く推奨しません。
Q8. 防犯フィルムが貼ってある窓は?
A. 破片の飛散は減るが風圧への強化ではない。合板or室内二重化は必要です。
Q9. 何年も同じ合板を使って良い?
A. 反り・割れ・腐食が出たら交換。防腐塗装と乾燥保管で寿命が延びます。
Q10. 換気はどうする?
A. 風下側の小窓を短時間だけ開け、割れ物から離れて行います。風上の大窓は開けません。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 合板(ごうはん):薄い板を重ねて接着した板。強く変形しにくい。
- OSB:木片を押し固めた板。入手しやすい。
- ポリカ板:軽くて割れにくい板。室内二重化に向く。
- 押さえ板:合板の端を面で抑えるための木材。
- スペーサー:ガラスと合板の緩衝材。
- 仮枠:内側に作るはめ込みの枠。そこへ板を固定する。
- 封止:すき間をテープでふさぐこと。
- スタッド(柱):壁の中の支え材。ここにビスが効く。
まとめ:面で受けて、すき間を消し、室内で守る
雨戸・シャッターがなくても、外の飛散物ゼロ→合板で面受け→枠周り封止→室内二重化の順で手を打てば、被害は確実に減らせます。施工は前日までに、当日は屋内退避と安全確認を最優先に。次回に備え、採寸・材料・仮枠を窓ごとにキット化しておけば、準備時間は劇的に短縮できます。さらに、写真記録と保管札で再現性を高め、家族で手順を共有しておくと、直前の慌てを最小化できます。