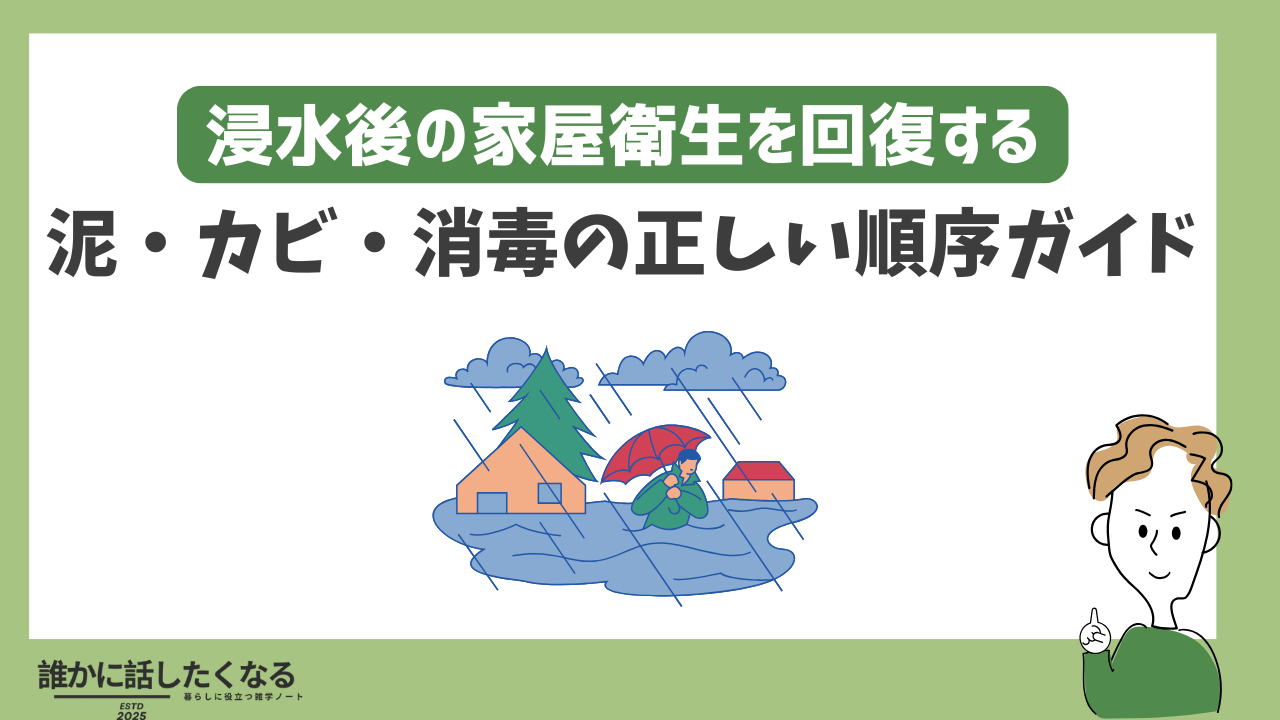浸水後の家は、泥・雑菌・カビが同時に襲います。焦って消毒から始めると効果が落ち、素材を傷めることも。本ガイドは、安全確認→記録→泥出し→洗浄→乾燥→消毒→防カビ→再発防止の順序を、手順・道具・配合・時間軸まで落とし込みました。
加えて、床下・壁内・電気設備・給排水といった部位別の対処、食品・衣類・薬の扱い、廃棄と保管の線引き、保険・助成の準備まで広くカバー。高齢者や小さなお子さん、ペットのいる家庭、木造・RC・集合住宅など状況別のコツも網羅しました。印刷して現場で見ながら使える実践版です。
1.作業前の安全確認と「最初の1時間」
1-1.感電・ガス・下水のリスクを最初に排除
- ブレーカーは総元から切る。 濡れた手で触らない。漏電が疑われるときは電力会社に連絡し、勝手に復電しない。
- ガス臭・シュー音があれば元栓を閉め、立ち入り禁止。再開は専門業者の点検後。
- 下水逆流は黒い水/異臭が目印。トイレ・排水口は養生テープ+ビニールで一時封鎖。
1-2.建物の安全と立入の可否
- 基礎のひび・土台のずれ・外壁のふくらみがないかを外から確認。傾きが疑われる場合は立入禁止。
- 階段・手すり・床梁の抜け・たわみを点検。踏み抜き防止に厚板・べニアを仮敷き。
1-3.防護具と動線づくり
- 防護具(PPE):長靴、厚手手袋、ゴーグル、N95等の高性能マスク、帽子。半袖×、肌は露出しない。
- 汚水動線と清潔動線を分け、玄関外に汚れ置き場を設ける。室内はブルーシートで養生し、撤去物の置き場を決める。
1-4.保険と罹災記録(10分でOK)
- 撤去前に写真・動画を広角→寄り→シリアルの順で。水位痕(ぬれ線)と、家電の型番・製造年も撮影。
- 家財の型番・購入年・概算価格をメモ。見積・領収は封筒に一括保管。
最初の1時間チェック表
| 項目 | 確認 | 備考 |
|---|---|---|
| ブレーカーOFF | □ | 乾いてから復電 |
| ガス元栓閉 | □ | 業者確認まで開栓不可 |
| 下水封鎖 | □ | 逆流止め・臭気対策 |
| 建物外観確認 | □ | 傾き・亀裂・はらみ |
| 記録撮影 | □ | 広角→寄り→番号 |
| PPE装着 | □ | 交代制で休憩 |
2.泥出し→粗洗い→排水の順序(消毒はまだ)
2-1.泥出し(スコップ→デッキブラシ→湿式回収)
- 玄関に近い部屋から外へ向けて掻き出す。重い泥→軽い泥の順で体力を節約。
- デッキブラシ+水でかき集め、ちりとり/ち水(ちすい)ワイパーで排水口へ誘導。窓下→扉口の順で進む。
- 外構(庭・駐車場)も同時に泥寄せすると、再流入を防げる。
2-2.粗洗い(界面活性剤で「汚れ」を落とす)
- 泥や有機物が残ったまま消毒しても効きません。まず中性洗剤や弱アルカリで表面の膜を落とす。
- 木部はこすりすぎ禁止。繊維方向に沿って短時間で洗い→拭き取り。合板は水を含ませすぎない。
2-3.排水の管理と目詰まり防止
- 排水口にゴミ受けネット。泥は袋で可燃へ、砂利は不燃へ(自治体指示に従う)。
- 屋外の側溝・集水桝を並行して掃除すると、室内の水はけが大きく改善。
2-4.床下・巾木・配線ダクトの一次処置
- 床下点検口から泥・水たまりを確認。雑巾→スポンジ→ウェスで吸い取り、送風の準備。
- 巾木は取り外すと壁内に風が通る。配線ダクトは水濡れがあれば通電厳禁。
泥出し・粗洗い・排水の段取り表
| 手順 | 目的 | 道具 | 時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 泥出し | 室内の体積を減らす | スコップ/バケツ | 1〜3時間 |
| 粗洗い | 汚れ膜の除去 | 中性洗剤/ブラシ | 1〜2時間 |
| 排水 | 目詰まり防止 | ゴミ受け/ワイパー | 随時 |
| 床下一次処置 | 湿気源の遮断 | ウェス/簡易ポンプ | 1〜2時間 |
3.乾燥こそ主役:風を通し、湿気を切る
3-1.通風・除湿・加温の三本立て
- 対角の窓を全開、サーキュレーターを入口→出口へ向け風の道を作る。扇風機は送風、換気扇は排気に役割分担。
- 除湿機は満水停止対策(ペットボトル直結・こまめに廃水)。衣類乾燥機能があると効率的。
- 気温が低いときは短時間の加温→換気で効率アップ。加湿器は使わない。
3-2.床・壁・断熱材の見極め
- 畳は屋外で立て掛けて乾燥。黒ずみ・臭い強なら廃棄を検討。
- フローリングは反り・隙間を確認。床下点検口から湿気・泥を必ずチェック。
- 石膏ボードは浸水高さ+30cmで切り取り、内部の断熱材を抜いて送風。防湿シートがある場合は切り欠きを作る。
3-3.家具・家電・空調の扱い
- 布張り家具は早期に乾燥できないなら廃棄。木製家具は脚を浮かせて送風。
- 家電は完全乾燥→専門点検まで通電禁止。冷蔵庫の臭いは重曹・活性炭で緩和。
- エアコン・換気システムのフィルタ・ドレンパンは取り外して洗浄・乾燥。室外機が浸水した場合は業者点検。
3-4.乾燥の進みを“見える化”
- 水分計(簡易)や紙テープで含水率・乾燥日を記録。結露が出るようなら送風方向を見直す。
乾燥の優先度・時間目安
| 対象 | 優先 | 乾燥のめやす |
|---|---|---|
| 床下 | ◎ | 48〜72時間送風 |
| 壁内 | ◎ | 3〜7日(切り欠き+送風) |
| 畳・カーペット | ○ | 1〜3日(天日+送風) |
| 家具(木) | ○ | 3〜5日(脚上げ+送風) |
| 空調フィルタ | ○ | 洗浄→完全乾燥 |
4.消毒・防カビは“汚れゼロ+乾燥後”に一点集中
4-1.素材別の消毒の考え方
- 金属・プラスチック:次亜塩素酸ナトリウム0.05%を浸して拭き→10分→清拭。
- 木部:アルコール(70%前後)を軽く霧吹き→拭き取り。濡らし過ぎ・染み込み過ぎに注意。
- 布:熱湯(70℃以上で10分)または洗濯後、天日干し。
- タイル目地:塩素系0.05〜0.1%で点付け→数分→水拭き。金属部にかけない。
4-2.配合のめやす(家庭用漂白剤を使う)
- 家庭用漂白剤は**有効塩素5〜6%**が多い。**0.05%**にするには、水1Lに漂白剤10mlが目安。
- 0.1%が必要な場合は水1Lに20ml。使用中は換気+手袋・ゴーグル。酸性洗剤と混ぜない。
4-3.カビの抑え込み:再発を防ぐ仕上げ
- 目に見えるカビはアルコールで拭き、乾燥を優先。塩素は色落ちに注意。
- 床下・壁内は防カビ剤より乾燥の徹底が有効。含水率が落ちれば増殖しにくい。
- 施工後は24時間は換気し、臭気が残る間は在室時間を短くする。
消毒・防カビ 早見表
| 対象 | 推奨 | 手順 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 金属・樹脂 | 次亜0.05% | 拭き→10分→清拭 | さび・変色注意 |
| 木部 | アルコール | 霧吹き→拭き | ぬらしすぎ× |
| 布 | 熱湯/洗濯 | 洗う→干す | 色落ち注意 |
| 目地 | 塩素0.05〜0.1% | 点付け→水拭き | 金属NG |
5.再発防止と生活再開:ニオイ・虫・衛生動線
5-1.ニオイ対策の三段階
- 発生源除去(泥・有機物)→乾燥→吸着(活性炭・重曹)。
- 下水臭はトラップの水切れが原因。コップ1杯の水を排水口に。封水の蒸発を防ぐため定期的に注水。
5-2.虫・小動物の侵入を止める
- 網戸・戸当たり・排水口メッシュで侵入路を封鎖。食品は密閉、生ごみは毎日処分。
- ネズミの痕跡(糞・かじり跡)があれば粘着シートと出入口封鎖を並行。
5-3.衛生動線と家族の健康
- 玄関に清潔・汚染の分岐点を設置。作業後は手洗い→うがい→着替えを徹底。
- 高齢者・乳幼児・持病のある方は乾燥と清掃が終わるまで別室で生活。
5-4.食品・衣類・薬の扱い
- 冷蔵・冷凍食品が室温に長時間さらされた場合は廃棄。密封瓶でも泥水接触があれば外面を消毒。
- 衣類は先に泥を落としてから洗濯。塩素は色落ちに注意。
- 常備薬は湿気・汚水で劣化の恐れ。医師・薬剤師に相談し代替処方を受ける。
廃棄・保管の線引き早見表
| 品目 | 原則 | 例外・備考 |
|---|---|---|
| 布団・マットレス | 廃棄 | 乾燥・消毒が困難 |
| 合板家具 | 状態次第 | 膨れ・反りがあれば廃棄 |
| 無垢木家具 | 乾燥後判断 | 反り少なければ再塗装可 |
| 子ども玩具(布) | 廃棄 | 洗浄・乾燥が難しい |
| 調理器具(金属) | 再生可 | 洗浄→塩素→清拭 |
生活再開・優先行動表
| 段階 | 目標 | 行動 |
|---|---|---|
| 初動(1〜3日) | 乾燥・通風 | 床下送風、壁切り欠き |
| 中期(4〜10日) | 消毒・防カビ | 素材別処置、再乾燥 |
| 後期(〜3週) | 復旧・再発防止 | 排水点検、臭気封じ、虫対策 |
Q&A(よくある疑問)
Q1. すぐに漂白剤で拭けば早い?
A. 逆効果です。 泥や有機物が残ると消毒剤が効きません。泥出し→洗浄→乾燥→消毒の順が基本。
Q2. 石膏ボードは全部剥がすべき?
A. 浸水高+30cmを目安に切り取り、内部の断熱材を撤去して送風乾燥。上まで濡れていれば広めに。
Q3. 木の床が黒ずんだ。元に戻る?
A. 早期乾燥と軽い研磨+再塗装で改善することがあります。ひどい場合は部分張替え。
Q4. 家電はいつ通電できる?
A. 完全乾燥後に専門点検。内部が湿っているとショート・火災の恐れ。
Q5. 家の臭いが取れない。
A. 発生源の残りが原因。床下の泥・壁内の断熱材を再点検。活性炭を置き、換気を継続。
Q6. カビ取りで塩素と酸性洗剤を一緒に使っていい?
A. 絶対に×。 有毒ガスが出ます。単独使用+十分換気を守ってください。
Q7. 子どもと高齢者はいつ戻れる?
A. 乾燥・清掃・消毒完了後。目安は床下が乾き、臭気が薄れ、カビの再発がない状態です。
Q8. 井戸水や受水槽は飲んでもいい?
A. 不可。 検査と消毒・洗浄が済むまで飲用・調理には使わないでください。
Q9. ボランティアを受け入れるときの準備は?
A. 作業区分・道具・休憩所・トイレを事前に用意し、安全説明(PPE・動線)を最初に行います。
用語辞典(やさしい言い換え)
- ぬれ線:壁や家具に残る水位の跡。
- トラップ:排水口の水の栓。臭いや虫の逆流を防ぐ。
- 含水率:木材の水分の割合。乾くほどカビが生えにくい。
- PPE:作業時の身を守る道具(手袋・長靴・マスクなど)。
- ち水ワイパー:床の水を外へ押し出す道具。
- 切り欠き:壁や床に乾燥用の小さな開口を作ること。
まとめ:順序がすべて—乾燥してから消毒
浸水後は順序が命綱です。安全→記録→泥出し→洗浄→乾燥→消毒→防カビ→再発防止を同じ段取りで反復すれば、無駄が減り、家の回復が早まります。焦りは禁物。乾燥してから消毒、これだけは忘れずに。