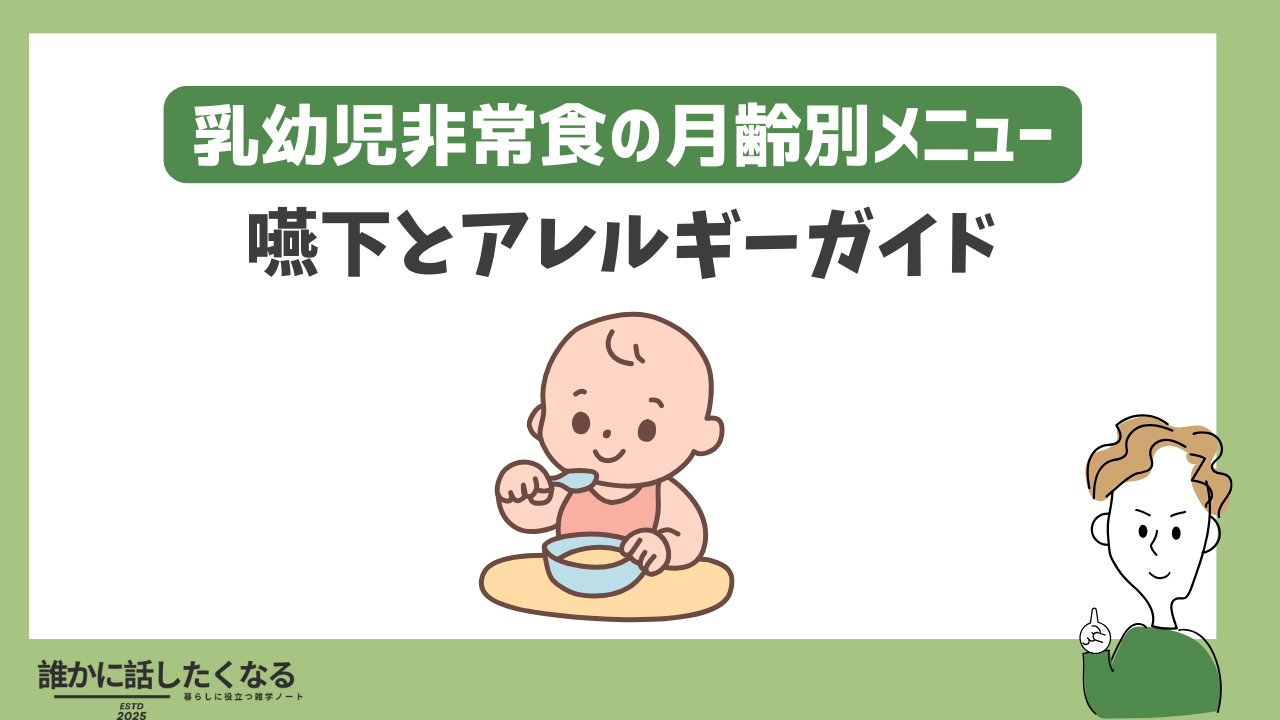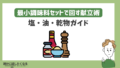災害やライフラインの停止時でも、月齢に応じた嚥下(のみ込み)安全とアレルギー配慮を両立させた食事が用意できれば、子どもの不安はぐっと和らぎます。本ガイドは、月齢別の食べられる固さ・量・味付けの目安、備蓄の組み方、加熱・水が乏しい時の代替手順まで、家庭でそのまま使える実務情報を一冊にまとめました。
さらに、避難所・車中・在宅避難など状況別の運用、水と燃料の優先配分、ミルクの使い分け(粉/液体)、とろみ付けによる誤嚥予防、持ち出し袋の最小セットまで具体的に整理しました。
既に食べ慣れた銘柄を中心に回すこと、薄味で形状を段階的に進めること、危険形状(丸い・つるつる・弾む)を避けることを基本に、7日×3食のテンプレとローリング備蓄の回し方も示します。医療的配慮が必要な子どもについては、主治医の指示を最優先し、本書は日常からの準備と非常時の再確認のための実務メモとして活用してください。
要点先取り(まずここだけ)
- 最優先は嚥下の安全:形状はペースト→やわらか粒→小さめ角→普通サイズへ段階的に。無理に進めない。
- アレルギーは既知優先:非常時は既に食べ慣れた食品を中心に。新規食材は落ち着いてから。
- 塩分・味付けは最小限:塩・しょうゆはごく薄味。だし・野菜の自然なうま味を軸に。
- 備蓄は“主食・主菜・副菜・水”の箱分け:1日×3食×7日を箱ごとに分けると迷わない。
- 水の確保が味より大事:ミルク・離乳食・手洗いの優先順位を家族で決めておく。
1.月齢別の固さ・量・味付けの基準
1-1.5〜6か月(初期)
- 形状:なめらかペースト。粒なし。
- 量の目安:1回小さじ1〜3から。1日1〜2回へ。
- 味付け:無塩が基本。野菜や米の自然な甘みで十分。
1-2.7〜8か月(中期前半)
- 形状:ヨーグルト状〜とろみ。ごく小粒を混ぜてもOK。
- 量:1回50〜80g目安。1日2回。
- 味付け:極薄味。だし少量は可。
1-3.9〜11か月(中期後半〜後期)
- 形状:歯ぐきでつぶせる固さ(バナナくらい)。5〜8mm角に刻む。
- 量:1回80〜120g。1日2〜3回。
- 味付け:薄味。油はごく少量。
1-4.12〜18か月(完了期)
- 形状:歯ぐきで噛める。1cm角まで。
- 量:1回120〜150g。
- 味付け:家族よりかなり薄味。辛味は不可。
1-5.19〜36か月(幼児食)
- 形状:一口大だがかたい物・丸い物は小さく。
- 量:食欲に合わせ調整。
- 味付け:大人の半分程度の塩分を目安に。
2.月齢別:非常食メニュー例と作り方
2-1.5〜6か月(初期):お湯とスプーンで完結
- 米がゆペースト:レトルト米がゆを小分け→お湯で伸ばしなめらかに。
- 野菜ペースト:にんじん・かぼちゃのキューブを湯せん→潰す。
- 白身魚ペースト:湯せんしたパウチ魚をだしでのばす。
2-2.7〜8か月:とろみ+やわらか小粒
- とろとろ雑炊:米がゆ+ささみフレーク+野菜キューブ。
- 豆腐とやさい:絹ごし豆腐を湯せん→スプーンで崩す+やさいと和える。
- さつまいもミルクがゆ:粉ミルクでミルクだしを作りペーストに。
2-3.9〜11か月:歯ぐきでつぶせる一皿
- やわらか炊き込み:レトルトご飯を水でほぐす→湯せん、野菜・魚を5〜8mmで混ぜる。
- 高野豆腐そぼろ:戻して指でつぶす→だし少量で含める。
- パラパラ鯵缶おじや:鯵缶を湯せん→骨を除き細かく→おじやに混ぜる。
2-4.12〜18か月:手づかみ+一品完結
- やわらかおにぎり:小さめ俵型。海苔は細く巻く。
- 野菜のとろみあえ:片栗粉代わりにとろみ粉(水溶き)でまとまりUP。
- 豆腐つくね:ツナ・豆腐・片栗で小判にして湯せん又は焼く(油は薄く)。
2-5.19〜36か月:薄味の“家族取り分け”
- 具だくさん汁:具は小さめ、味は薄めにして取り分け。
- 蒸しパン・蒸し芋:手づかみで腹持ち◎。
- 焼きおにぎり風:しょうゆ薄塗りで香りだけ。
3.備蓄設計:主食・主菜・副菜・水の整え方
3-1.備蓄の骨格(7日×3食×人数)
| 区分 | 初期(5〜6m) | 中期(7〜11m) | 完了〜幼児(12m〜) |
|---|---|---|---|
| 主食 | 米がゆパウチ | レトルトご飯/軟飯 | レトルトご飯/うどん |
| 主菜 | 白身魚・鶏・豆腐パウチ | ツナ水煮・鮭・高野豆腐 | 鯖・鮭・大豆・ツナ |
| 副菜 | 野菜ペースト | 野菜キューブ/乾燥野菜 | 冷凍/乾燥野菜・海苔 |
| 水 | 飲用水・湯冷まし | 飲用水・湯冷まし | 飲用水・湯冷まし |
ミルク使用家庭は、粉ミルク・液体ミルク・哺乳びん洗浄具も日数分。
3-2.形状・アレルギー別の置き方
- 箱A:普段から食べている味(既知食材のみ)
- 箱B:代替食(卵・乳・小麦不使用など)
- 箱C:水・とろみ粉・ベビースプーン・紙皿
3-3.賞味期限の回し方(ローリング)
- 月に1回、一番古い箱から使用→同数を補充。
- 補充時に月・年のラベルを貼り替える。
4.加熱・水が乏しい時の代替手順
4-1.湯せん・保温で仕上げる
- 鍋1つに湯→パウチを入れて湯せん。
- 保温容器(発泡箱・鍋保温袋)で余熱を活かす。
4-2.とろみで安全性UP
- スプーンから滑り落ちにくいとろみをつけると、むせを減らせる。
- 片栗粉や市販のとろみ剤をごく少量から。
4-3.水の節約
- 使い捨てスプーン・紙皿・口拭き用の清潔な布を準備。
- 調理は袋内で混ぜる方式にして洗い物ゼロ。
5.誤嚥・窒息を防ぐカット・盛り付け
5-1.避けたい形と工夫
- 丸い・つるつる・弾む食品(ぶどう、ミニトマト等)は小さく切るか避ける。
- 皮・筋は除く。繊維は短く切る。
5-2.盛り付けのコツ
- 一皿に多種類を盛り過ぎない。
- 汁気はとろみでまとめると食べやすい。
5-3.食べる姿勢
- 椅子で背すじを支える。ねんね食べは避ける。
- 一口量を小さく、ゆっくり。
6.月齢別・献立テンプレ(7日)
6-1.初期(5〜6か月)
| 日 | 朝 | 昼 | 夕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米がゆペースト | 野菜ペースト | 米がゆ+白身魚ペースト |
| 2 | 米がゆ | さつまいもペースト | 米がゆ+にんじん |
| 3 | 米がゆ | かぼちゃ | 米がゆ+豆腐 |
| 4 | 米がゆ | ほうれん草 | 米がゆ+白身魚 |
| 5 | 米がゆ | じゃがいも | 米がゆ+にんじん |
| 6 | 米がゆ | かぶ | 米がゆ+豆腐 |
| 7 | 米がゆ | 野菜ミックス | 米がゆ+白身魚 |
6-2.中期(7〜11か月)
| 日 | 朝 | 昼 | 夕 |
|---|---|---|---|
| 1 | とろとろ雑炊 | 豆腐+野菜とろみ | やわらか粥+ツナ |
| 2 | さつまいもがゆ | 軟飯+鶏そぼろ | 野菜おじや |
| 3 | 軟飯+鮭 | 豆腐+野菜 | 軟飯+白身魚 |
| 4 | 野菜おじや | 高野豆腐そぼろ | 軟飯+ツナ |
| 5 | 軟飯+豆 | 豆腐+さつまいも | 野菜とろみあえ |
| 6 | とろとろ雑炊 | 軟飯+鮭 | かぼちゃがゆ |
| 7 | 軟飯+鶏 | 豆腐+野菜 | やわらかおにぎり |
6-3.完了〜幼児(12か月〜)
| 日 | 朝 | 昼 | 夕 |
|---|---|---|---|
| 1 | やわらかおにぎり | 豆腐つくね | 具だくさん汁+軟飯 |
| 2 | 蒸しパン | 焼き芋 | うどん薄味 |
| 3 | 野菜とろみあえ | 鮭ほぐし飯 | かぼちゃ含め煮 |
| 4 | おにぎり+海苔 | 豆腐+ツナ | 野菜雑炊 |
| 5 | 野菜スープ | さつまいも | 高野豆腐煮 |
| 6 | うどん薄味 | 豆腐+野菜 | 鮭と野菜の蒸し |
| 7 | 小さめ焼きおにぎり | 具だくさん汁 | 柔らか煮物 |
7.アレルギー配慮の進め方(非常時の基本)
7-1.既知の安全帯を守る
- 食べ慣れた商品を同じ銘柄で備蓄。表示・原材料は更新の都度確認。
7-2.除去が必要な場合
- 卵・乳・小麦など除去版レトルトを複数確保。
- 代替:豆乳・米粉・片栗など、家庭で使い慣れた代替を。
7-3.表示の読み方の基本
- アレルゲン表示と製造ラインの注意書きを確認。
- 不明な場合は安全優先で見送る。
8.衛生・保存・ミルクの運用
8-1.衛生の基本
- 手指の清潔:ウェットシート・清潔布を常備。
- 器具の扱い:使い捨てスプーン、紙皿で洗い物を減らす。
8-2.保存と温度
- レトルトは未開封常温可。開封後は早めに使い切り。
- 余りは小分け→粗熱取り→密閉し冷暗所へ(長時間保存は避ける)。
8-3.ミルクの使い分け
- 粉ミルク:お湯が必要だが軽量。
- 液体ミルク:そのまま使えるが重い。外出・夜間向き。
9.持ち出し袋チェックリスト(乳幼児版)
- レトルトおかゆ/うどん/主菜パウチ
- 野菜ペースト/乾燥野菜/とろみ粉
- 粉ミルク/液体ミルク/ストローマグ
- 使い捨てスプーン・紙皿・はさみ・ジッパー袋
- ウェットティッシュ・手指消毒・口拭き布
- 使い捨てエプロン・ゴミ袋・保温用タオル
Q&A(よくある疑問)
Q1.非常時に新しい食材を試してもいい?
A. 基本は不可。既に安全が確認できている物を優先し、落ち着いてから段階的に。
Q2.子が食べない。味を濃くして良い?
A. 薄味維持が原則。出汁・野菜の甘み・とろみで食べやすさを上げる。
Q3.常温のレトルトは冷やしてもいい?
A. 冷やし過ぎは嚥下低下につながることも。人肌を目安に。
Q4.ミルクや水が足りない時は?
A. 飲用水を最優先。食事はとろみで量感を出す、水分の多いおかゆを活用。
Q5.缶の魚や豆はいつから?
A. 塩分が低い物を選び、細かくして月齢の固さに合わせる。骨や皮は除く。
用語辞典(やさしい言い換え)
嚥下(えんげ):口に入れた食べ物をのみ込む動き。
誤嚥(ごえん):食べ物が気管に入ること。むせや窒息の原因。
完了期:離乳食がほぼ大人食に近づく時期。
ローリング備蓄:日常で使いながら補充して鮮度を保つ方法。
とろみ:片栗粉や専用粉で汁気にとろみを付けること。
まとめ:安全帯を守り、既知の味で回す
非常時こそ、いつも食べている味と形が子の安心に直結します。段階的な固さと薄味、既知食材の徹底、水と衛生の優先。この4点を家族で共有し、7日×3食を箱分けで備えれば、いざという時にも迷わず温かい一口を届けられます。