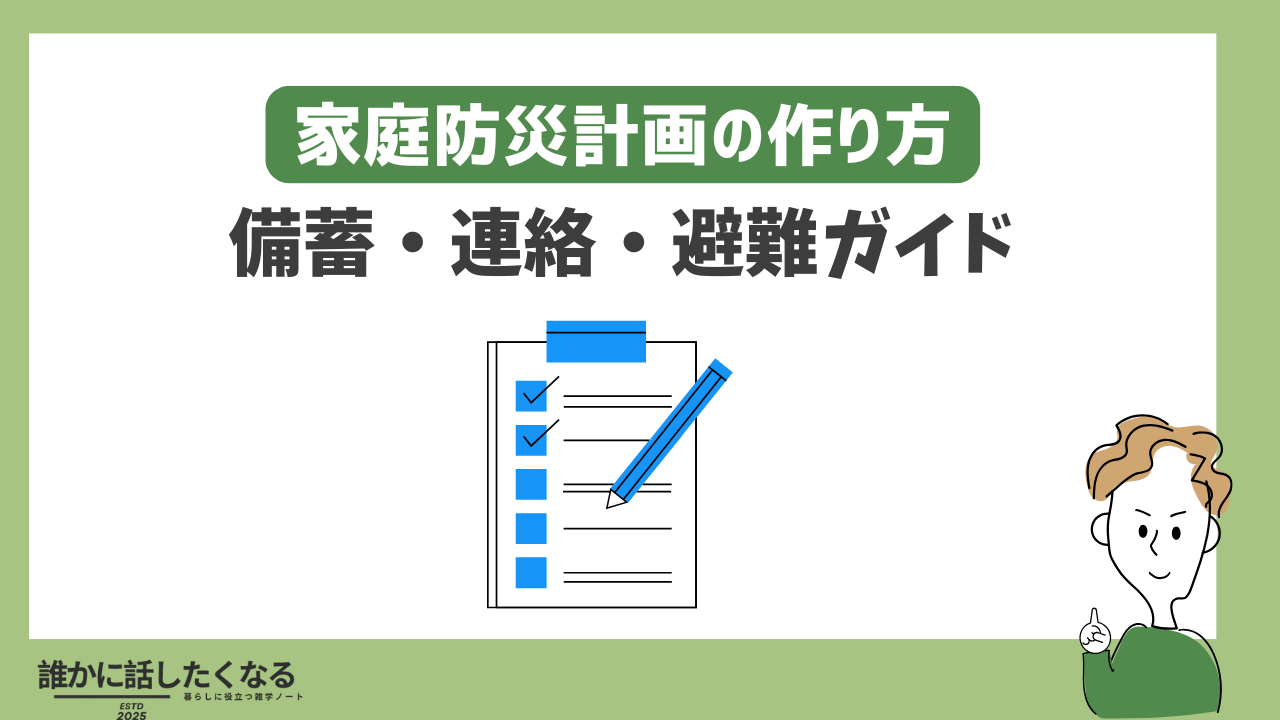「何を、誰が、いつ、どこへ」——これを決めておくだけで、災害時の迷いは激減する。本稿は、家庭ごとの事情に合わせて防災計画(Family BCP)を自作・運用するための実務ガイド。備蓄の量と回し方、連絡・合流ルール、避難先の層構造、在宅避難の衛生と安全までを表・テンプレ・チェックリストで落とし込む。最後にQ&Aと用語辞典を付した。
要点先取り(まずここだけ):①合流場所は3層(自宅前→近隣→広域)と到着期限を紙に固定。②役割分担(水係・情報係・装備係・連絡係)を週次点検とセットで運用。③水は1人1日3L×14日を基準に、前線2週間+後方1か月の二層在庫で回す。④連絡は階層化(家族→親族→県外ハブ)。⑤紙の計画書+家族写真を各自の財布に。
このガイドの使い方:最初に家族構成と連絡先を記入→合流場所3層を地図に落とし→備蓄の数式で家の必要量を算出→置き場所と回し方を決め→月1回5分点検を習慣化する。読み進めるほどにそのまま運用に移せるよう、各章は短い手順→早見表→実例で構成した。
想定シナリオ別・最初の動き
| 事象 | 最初の10分 | 最初の1時間 | その日のうちに |
|---|---|---|---|
| 地震(在宅可) | 火の元確認・家族安否・出口確保 | 断水/停電の有無を確認、物が落ちる場所の封鎖 | 水・食の在庫点検、合流場所と連絡ルールを再確認 |
| 地震(在宅不可) | 退避合図→第1合流へ徒歩移動 | 第2合流候補と迂回路を確認、名簿で点呼 | 広域避難の判断、持出袋の不足を補う |
| 台風・大雨 | 低地/河川から離れる、停電準備 | 在宅避難の断水対策、情報係が警報監視 | 翌日の物資計画、冷蔵庫の中身を先に消費 |
| 停電長期化 | 懐中電灯・換気・冷蔵庫は開閉最小 | 充電計画、夜の動線をヘッドライト化 | 水・食の配分表を作成、近隣と情報共有 |
完成イメージ:玄関に1枚の計画書、キッチンには在庫表と補充ルール、非常持出袋には役割カード。これらが紙で見えるだけで、災害時の判断と会話が短時間で整う。続く章で、作り方と回し方を具体化する。
1.家庭防災計画の骨格:役割・決めごと・更新日
1-1.役割分担(例)
- 水係:飲料・生活用水の在庫と補充。
- 情報係:公的発表・気象・避難情報を確認し家族へ伝達。
- 装備係:非常持出袋・ヘッドライト・モバイル電源を点検。
- 連絡係:家族・親族・近隣・学校/職場の連絡窓口。
1-2.決めごと(平時に紙で可視化)
- 合流場所(自宅前/近隣公園/広域避難の3層)と到着期限。
- 優先連絡先(家族→親族→県外親族の順)。
- 持出順位(人命→薬・眼鏡→情報→現金→衣類)の固定化。
1-3.更新日・点検日
- 毎月1日:飲料水と電池。
- 季節の変わり目:衣類・寝具見直し。
- 年度替わり:学校・職場の連絡網更新。
役割×週次点検表(例)
| 係 | 週の作業 | 所要時間 | 完了チェック |
|---|---|---|---|
| 水係 | ペットボトル消費→買い足し記入 | 10分 | □ |
| 情報係 | アプリの警報テスト/ラジオ動作 | 5分 | □ |
| 装備係 | 充電%確認/ヘッドライト点灯 | 5分 | □ |
| 連絡係 | 家族の所在と通学・通勤経路 | 5分 | □ |
2.備蓄の設計:必要量・回し方・置き場所
2-1.必要量の出し方(飲食・日用品)
- 飲料水:1人1日3L(飲用+調理)。
- 主食:1人1日2食分を目安(常温保存できる主食)。
- トイレ用品:袋式トイレ=人数×日数で用意。
- 衛生用品:石けん/手指消毒/ウェットを家族構成で調整。
2-2.ローリングストックの回し方
- 前線(キッチン・洗面):2週間分を見える棚へ。
- 後方(押し入れ上段):1か月分を箱ごと保管。
- 先入れ先出し:新入りは奥、古いものから手前。日付ラベルで回す。
2-3.置き場所の鉄則(湿気・温度・動線)
- 床直置きNG、台・すのこで湿気遮断。
- 高温多湿の屋根裏・車庫は夏に品質劣化。室内の風通しへ移す。
- 動線短縮:重い箱は膝の高さ、割れ物は胸より下に。
3日・14日・30日 備蓄目安(4人家族例)
| 項目 | 3日 | 14日 | 30日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 飲料水 | 36L | 168L | 360L | 2L×本数で管理 |
| 主食 | 24食 | 112食 | 240食 | 米・麺・パン缶等 |
| レトルト等 | 12袋 | 56袋 | 120袋 | 常温・省水調理 |
| 袋式トイレ | 24回 | 112回 | 240回 | 凝固剤セット |
| 電池・充電 | 充分 | 充分 | 充分 | 端末・ライト用 |
3.連絡・合流・避難:3層で考える動き方
3-1.連絡ルール(途絶を前提に)
- 1回連絡がつかなければ10分後、以降30分ごとに再試行。
- 県外親族を伝言ハブに。SMS・メールは通話より通りやすいことがある。
3-2.合流の3層(近距離→中距離→広域)
- 第1合流:自宅前/最寄り公園。徒歩5〜10分で行ける場所。
- 第2合流:学区外の広い公園や親族宅。
- 第3合流:鉄道主要駅や広域避難所。地図で2ルート以上記す。
3-3.避難の判断と装備
- 在宅避難:家が安全なら水・衛生・空調を確保。
- 一時避難:ヘッドライト・モバイル電源・水1Lを最優先。
- 広域避難:身分証・保険証・現金。家族写真をスマホと紙で持つ。
持出袋ミニマム構成(大人1人)
| 区分 | 品目 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| 照明 | ヘッドライト | 1 | 夜間の両手自由 |
| 電源 | モバイル電源 | 1 | ケーブルも忘れず |
| 水分 | 飲料水500ml | 2 | こまめに補給 |
| 情報 | ラジオ/ホイッスル | 1 | 情報取得・呼びかけ |
| 薬 | 常用薬・貼付薬 | 数日分 | 服用スケジュール同封 |
4.在宅避難を続けるコツ:衛生・空気・温度・安全
4-1.水が少ない時の清潔
- 手指:石けん+流水が理想。ない場合は手指用アルコールで代替。
- 体:濡れタオル拭き→ワセリン少量で皮膚保護。
- 食器:ラップや紙皿で洗い物を減らす。
4-2.空気と温度の整え方
- 換気は“短時間・対角”。
- 夏:遮熱カーテン・保冷剤・打ち水。
- 冬:足元の断熱(段ボール+毛布)とすき間風の封じ込め。
4-3.安全確保(転倒・火災・一酸化炭素)
- 家具固定、通路の段差に養生。
- 燃焼器具の室内使用NG、警報器の点検。
- 停電復旧時は通電火災に注意。
在宅運用チェックリスト(1日1回)
| 時間帯 | すること | 完了 |
|---|---|---|
| 朝 | 体調・飲水量・トイレ残数を記録 | □ |
| 昼 | 連絡可否・充電%・室温を確認 | □ |
| 夜 | 明日の合流場所・持出品を再点検 | □ |
5.家族別の配慮:子ども・高齢者・ペット
5-1.子ども
- 身分証カード(名前・連絡先・アレルギー)。
- 退屈対策:トランプ・塗り絵・折り紙を500g以内で。
- 迷子対策:合図の言葉と集合の絵地図。
5-2.高齢者
- 薬のリストと1週間分の小分け。
- 踏み台や手すりの設置、靴下のすべり止め。
- 補助具(眼鏡・補聴器・義歯)の洗浄・保管キット。
5-3.ペット
- ペット用水・フードは7〜14日分。
- 迷子札と予備リード。
- トイレ用品(ペットシーツ・処理袋)。
家族別ミニポーチ例
| 対象 | 必携品 | 目安重量 |
|---|---|---|
| 子ども | 連絡カード・小灯・トランプ | 300g |
| 高齢者 | 薬・眼鏡予備・杖先ゴム | 400g |
| ペット | フード1日分・予備リード | 200g |
Q&A(悩みを一気に解決)
Q1:何から始めればいい?
A: まず合流場所の3層と役割分担を紙に。次に水(14日分)と照明から着手。
Q2:置き場がない。
A: 長尺ロール・箱形食品を選び体積効率を上げる。ベッド下・押し入れ上段を活用。
Q3:毎月の点検が続かない。
A: 家族の誕生月日や給与日など動機のある日に固定。5分で終わるメニューに絞る。
Q4:在宅か避難か迷う。
A: 家の損傷・火災・土砂・津波の危険があれば避難。安全なら在宅で水・衛生・空調を確保。
Q5:通信が使えない。
A: 紙の計画書と家族写真を各自の財布へ。掲示板や伝言ダイヤルの利用も。
用語辞典(やさしい言い換え)
家庭BCP:家庭の事業継続計画の考え方。暮らしを止めないための段取り。
ローリングストック:普段食べる物を多めに買い、使った分を買い足す在庫法。
先入れ先出し:古い物から先に使い、新しい物は奥へしまう回し方。
在宅避難:家にとどまり生活を続ける避難の形。
広域避難:生活圏を越えて移動する避難。交通や宿泊の計画が要る。
まとめ:決めて、書いて、回す——それが家庭防災
役割分担と合流場所を今日決めて紙に。水・照明・連絡の三点セットを今週中にそろえ、ローリングストックで14日→30日へと厚みを出す。点検は5分・月1回。この仕組み化だけで、災害時の迷いは驚くほど減る。家族の暮らしを守る最短ルートは、決めごとの可視化と小さな習慣だ。