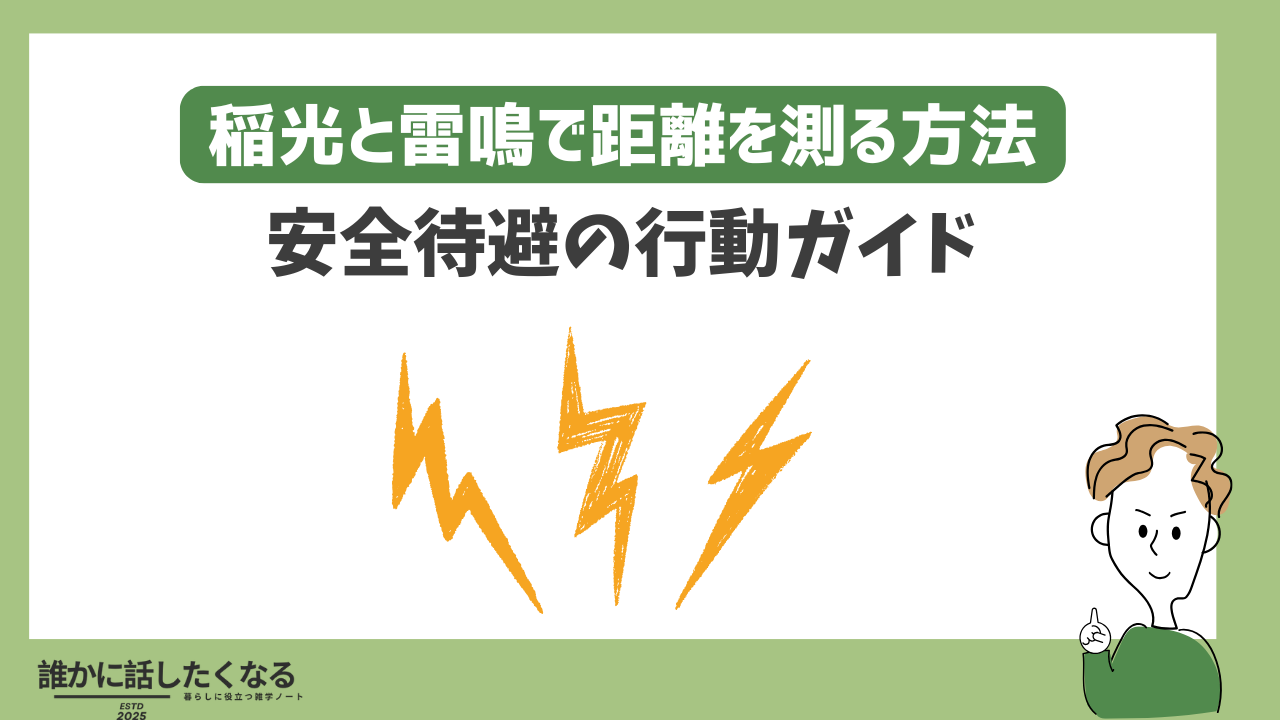結論:雷から身を守る最優先は距離の把握と即時の待避です。稲光を見てから雷鳴が聞こえるまでの秒数×340m(音速の目安)で雷までのおおよその距離が分かります。
さらに3の法則(稲光→3秒以内=約1km以内=危険圏)を合図に、屋内・車内へ移動し、窓・金属・水・高所から離れること。現場では①測る→②判断→③移動→④待機→⑤解除の順で動けば、多くの事故を避けられます。本稿は、測り方の精度向上・兆しの読み取り・屋外と屋内の最善行動・集団の中止基準・復旧と応急対応まで、表と手順で詳述します。
稲光と雷鳴で距離を測る(まず基本を身につける)
音の速さを使う「カウント法」
- 稲光を見たらゼロで開始、雷鳴が聞こえるまで秒数を数える。
- 距離(km)の目安=秒数 ÷ 3。または秒数 × 340mで計算。
- 例:6秒→約2km、15秒→約5km、3秒→約1km(直ちに退避)。
上級メモ(気温補正で精度を上げる)
- 音速は331+0.6×気温(℃)m/秒。30℃なら約349m/秒。夏はやや遠めに出るため、安全側に切り下げて判断する。
数え方のコツ(誤差を減らす)
- 連続する稲光は最も近い光に対して数える。雲内の光でも近い可能性あり。
- 数えながら手帳やスマホに秒数を連記し、接近/離隔の傾向を掴む。
- 音が聞き取りにくい場所(交通量・海岸)では見えた時点で退避開始。
秒数と距離・猶予の早見表(安全側)
| 秒数 | 距離の目安 | 猶予感覚 | 行動の目安 |
|---|---|---|---|
| 0〜3秒 | 0〜1km | ほぼ直上 | 即退避。屋外活動禁止、屋内・車内へ |
| 4〜6秒 | 1.3〜2km | 数分危険 | 中止。水辺・高所・金属から離脱 |
| 7〜12秒 | 2.3〜4km | 接近中 | 退避継続。集団は屋内へ誘導 |
| 13〜18秒 | 4.3〜6km | 警戒 | 屋外は縮小。再開は最後の雷鳴から30分後 |
| 19秒以上 | 6km超 | 一時的に遠のく | 退避維持。慌てて再開しない |
危険度を見極める合図(空・音・周囲のサイン)
空のサイン(接近の兆候)
- 背の高い入道雲が短時間で膨張し、雲底が黒く低い。
- カーテンのような雨脚、雹交じり、雲の舌の垂れ下がり(突風の前触れ)。
- 稲光の頻度が増える、光色が白→青白→紫へ変化(放電路が太い)。
音のサイン(雷鳴の質で判断)
- 連続するゴロゴロ:遠雷の可能性。ただし接近中に変わることが多い。
- ドン!バリバリ!の乾いた破裂音:近距離または真上。
- 胸に響く低音が増える:距離短縮の合図。
周囲のサイン(体感・電気・風)
- 髪が逆立つ、金属がビリビリ:地面との電位差が大。即しゃがむ(足を閉じる)。
- 無線・ラジオの雑音が急増、照明が瞬間的に明滅。
- 冷たい突風と砂塵—降雨直前のことが多い。
サイン→行動 早見表
| サイン | 危険度 | とる行動 |
|---|---|---|
| 黒い雲が急接近 | 高 | 予定中止、屋内へ移動 |
| 3秒以内の雷鳴 | 最高 | 即退避、30分ルール適用 |
| 髪が逆立つ・金属がしびれる | 最高 | 低姿勢・足を閉じる・金属から離れる |
| 雹・太い雨脚 | 高 | 屋根のある建物へ、窓から離れる |
屋外での避難先とNG行動(現場で命を守る)
避難先の優先順位
- 鉄筋コンクリート造の建物:窓から2m以上離れた内側へ。階段室・廊下も有効。
- 金属ボディの車(完全に窓を閉める):安全側の駐車場や施設の庇の下へ移動。アンテナや金属部に触れない。
- やむなしの一時退避:低いくぼ地で足を閉じてしゃがむ(増水の危険があれば不可)。
絶対に近づかない場所
- 高い木・単独の鉄塔・電柱・避雷針の直下(側撃・跳ね返りの危険)。
- 水辺・濡れた地面の広場(電気が表面を広がりやすい)。
- 長い金属(ゴルフクラブ・釣りざお・脚立・金属柵)。
しゃがみ方のコツ(地面電位差を小さく)
- かかとをそろえ、つま先でバランス。両足を離さない(歩幅電圧を小さく)。
- 腕は体側、地面に手をつかない。絶縁できる物(ザック・マット)の上に乗る。
環境別・とる行動 早見表
| 環境 | 退避先 | NG行為 |
|---|---|---|
| 平野・公園 | 建物・トイレ棟の内側 | 大木の下・東屋の柱際 |
| 山・稜線 | 樹林帯の低い木の内側・鞍部 | 稜線・単独木・岩の頂上 |
| 海・川・湖 | 管理棟・車内 | 桟橋・ボート・浜辺の開放地 |
| ゴルフ場 | クラブハウス・避難小屋 | カートで走り回る、傘を掲げる |
| 工事現場 | 事務所棟・車内 | クレーン・脚立・鉄骨近傍 |
家と室内の保護(電気・配線・窓の安全)
電気と配線(過電圧から守る)
- 注意情報が出たら:タコ足配線を最小化、重要機器は雷対策付きタップへ集約。
- 直撃の恐れ:コンセントを抜くのが最も確実。留守時は主電源の遮断も選択肢。
- 通信線・同軸も雷の入口—余裕があれば外す。
窓・ベランダ・水回り(飛散・感電リスク)
- 雨戸・シャッターを閉める。網戸は開けない。
- 物干し・脚立・金属用品は室内へ。水たまりと電源コードの分離。
- 入浴・食器洗いなど水仕事は雷鳴がする間は控える。
家族内の安全帯(集合と連絡)
- 窓の少ない内側の部屋へ集合し、ヘルメット・厚手の上着・靴で飛散対策。
- 懐中電灯・モバイル電源・笛を手元に。冷蔵庫の開閉最小で停電に備える。
屋内の雷対策 チェック表
| 項目 | 確認点 | OK欄 |
|---|---|---|
| 電源 | 雷対策タップ/プラグ抜き | □ |
| 窓 | 雨戸閉・カーテン引き | □ |
| ベランダ | 金属撤収・水と電源分離 | □ |
| 集合 | 内側の部屋・ライト・電源 | □ |
屋外スポーツ・学校・職場(集団の判断基準)
スポーツ・イベントの中止ライン
- 10秒以内(約3km)で直ちに中止・屋内退避。
- 最後の雷鳴から30分経つまで再開しない(30分ルール)。
- 観客にも退避案内を出し、屋根付きでも開放構造は不可。
学校・園の運用(時間割の見直し)
- プール・校庭・屋上は即中止。体育館でも窓・壁際を避ける。
- 登下校:木の下・鉄塔の下で雨宿りをしないよう周知。
- 点呼・連絡網で児童生徒・職員の所在を見える化。
職場・工事現場(停止基準)
- 高所作業・クレーン・脚立は3秒以内で全面停止。
- 通信・電力・屋外配線は予備電源と切替を準備。
- 退避は最短動線、集合場所は窓の少ない内側。
集団行動の基準 早見表
| 場面 | 中止ライン | 再開条件 |
|---|---|---|
| スポーツ | 10秒以内 | 最後の雷鳴から30分 |
| 学校 | 10秒以内 | 室内での安全確保後 |
| 工事 | 3秒以内 | 監督の許可・安全確認 |
落雷後の直後対応と応急処置(二次被害を防ぐ)
触れてはいけない・近づかない
- 倒れた電線、電柱・鉄塔の損傷箇所には近づかない。感電と再転倒の危険。
- 屋根・樹木・看板の落下物に注意。上から下へ順に安全確認。
けが人がいる場合(最初の2分)
- 意識・呼吸を確認。反応がなければ通報し、胸骨圧迫を開始。雷で倒れた人は触れて安全(体に電気は残らない)。
- やけどは清潔な布で覆う。水ぶくれは破らない。
機器と配線の再投入
- 焦げ臭・異音・水濡れがあれば通電しない。写真記録→連絡(保険・管理会社)。
- 通信機器は段階的に再投入。雷対策機器の確認。
Q&A(よくある疑問を一気に解決)
Q1. 稲光は見えるのに音が聞こえない。遠い?
A. 遠い可能性もあるが油断は禁物。風向・地形・交通音で雷鳴が届かないことがある。3秒ルールが出たら即退避を続ける。
Q2. 車の中は本当に安全?
A. 金属ボディが電気を外へ流すため比較的安全。ただし窓は閉める、金属に触れない、木の下では停車しない。
Q3. 家の中で注意することは?
A. コンセント・LAN・同軸の抜線、窓から離れる、ベランダに出ない。入浴・食器洗いなど水回りも控える。
Q4. 雷が去った目安は?
A. 最後の雷鳴から30分待つ。秒数カウントが長く、空が明るくなるまで待機。
Q5. スマホのアプリや位置情報で代用できる?
A. 補助には有効だが最後は自分の目と耳で。電池切れ・電波不通でもカウント法は使える。
Q6. 地下道・高架下は安全?
A. 水がたまりやすい場所は不可。増水の危険がある。建物内の内側の部屋が優先。
Q7. テント泊の時は?
A. 稜線・沢沿いを避ける。金属ポールから離れ、低い場所で足を閉じてしゃがむ。可能なら避難小屋へ。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 稲光(いなびかり):雷の光。雲と地面、雲と雲の間で電気が走る光。
- 雷鳴(らいめい):雷の音。空気が急に熱せられて膨張し、衝撃波が耳に届く音。
- 音速:音が進む速さ。おおよそ340m/秒として計算に使う(気温で変化)。
- 積乱雲(せきらんうん):背が高い入道雲。雷や突風、にわか雨の原因。
- 側撃・跳ね返り:対象物に落ちた雷が横に飛び移る。
- 歩幅電圧:地面に広がる電気で足の間に生じる電位差。足を閉じると小さくできる。
- 雷対策タップ:電気の急な変化から機器を守る装置を内蔵した差し込み口。
まとめ:測る→判断→退避→30分待機
稲光→秒数カウント→距離推定で危険を素早く見積もり、3秒以内なら即退避。屋内・車内では窓・金属・水から離れ、電源・通信の抜線で機器も守る。倒木や電線には近づかず、けが人には通報と胸骨圧迫を。最後の雷鳴から30分を合図に再開。測る→判断→退避→待機をひとつの流れにすれば、雷のリスクは大きく下げられます。