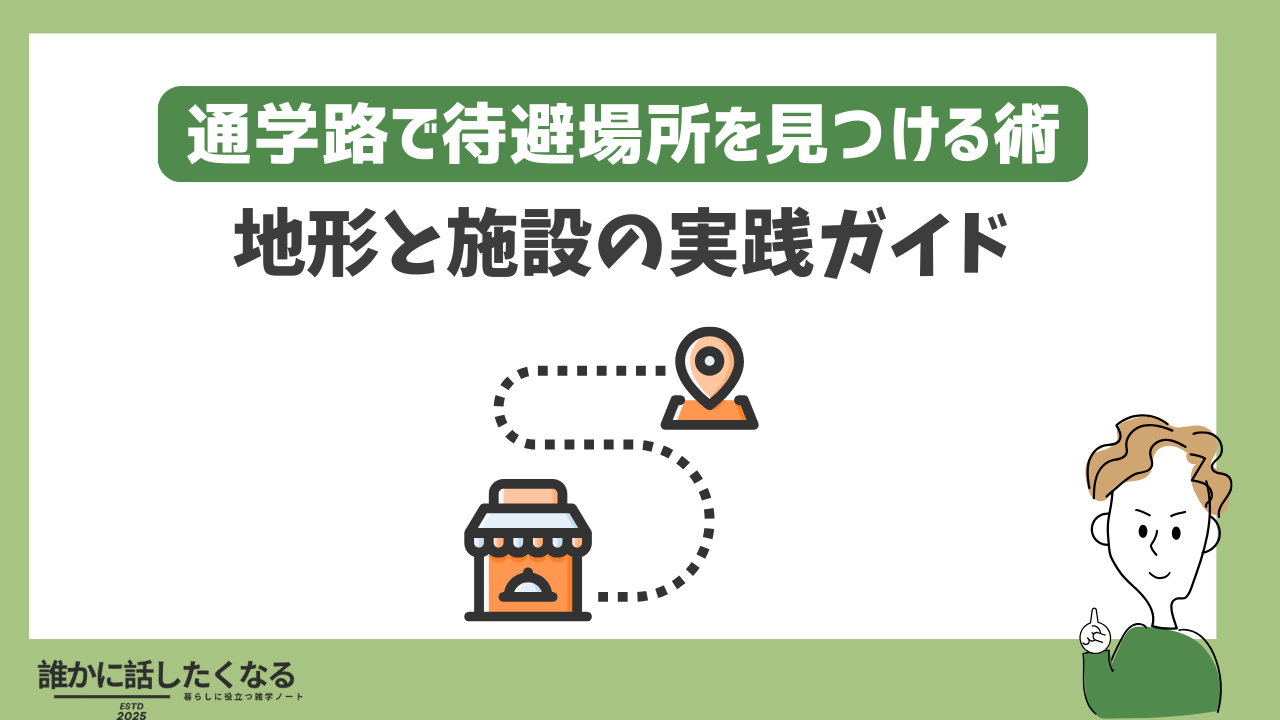突然の豪雨・突風・地震・不審者――「その場で安全に止まれる場所」を先に決めておけば、迷いが行動に変わります。
本稿は、日々の通学路でどこに寄り、どこを避け、どう合図するかを、地形・施設・時間帯・季節の四つの軸で整理。地図に落とし込める判定基準、家庭・学校で共有できる表、声かけテンプレ、5分×4回の訓練メニューまで、今日から使える実践情報をまとめました。
通学路での「待避」の考え方:優先順位・合図・隊列
先に決める三原則(探す順)
- 車両から離れる:車道と柵・段差・植え込みで分かれる場所。
- 屋根で守る:雨・落下物・強風を避けられる庇(ひさし)・アーケード・ピロティ。
- 人目がある:助けを呼べる・見られている(店前・交番近く・駅前)。
迷ったらこの順番:「柵→屋根→人目」。三つそろえば最優先。
隊列と合図(短く・大きく・同じ言葉)
- 先頭が指差し→声→復唱で伝える。合言葉は**「止まる!」「右による!」「店に入る!」**の三語に統一。
- 最後尾は後方確認役。自転車・車が来たら**「後ろ!」**と短く。
- 横断は二列にしない。一列で間隔を取り、曲がり角の前で減速。
やってはいけない行動ベスト5
| NG行動 | なぜ危険か | 代わりにすること |
|---|---|---|
| 白線・金属の上で立ち止まる | 雨で油膜化・横すべり | 白線をまたぐ/脇の乾いた帯へ |
| 角で急旋回 | 足元が滑り転倒 | 減速→一旦止まる→向きを変える |
| 店の入口をふさぐ | 車いす・台車と接触 | 壁ぎわに沿って待つ |
| 帰り道の近道(裏道) | 人目が少ない | 商店前が続く通りへ |
| 低い所へ集まる | 水が集まる・車が切れ込む | 段差が上がる場所へ移動 |
待避の三条件・判定早見表
| 条件 | 目安 | 例 |
|---|---|---|
| 車両から離れる | 柵・段差・植え込みがある | 歩道橋の根元、ガードレール内側 |
| 屋根で守る | 雨・落下物・強風を避ける | 商店の軒、寺社の庇、公共施設のピロティ |
| 人目がある | 助けを呼べる・カメラ | 駅前、交番近く、店内入口付近 |
地形から見つける待避:坂・川沿い・高架・狭い道・海風
坂道(上り・下り)の鉄則
- 上り:見通しの短いカーブ外側は避け、内側の壁沿いへ。階段状の脇道があれば一時退避。
- 下り:速度が出る自転車に注意。縁石が高い側、家の塀がある側へ寄る。
- 合図:**「減速!」**を前から後ろへ復唱。
川沿い・用水路・橋のたもと
- 増水時は橋のたもとを避ける。水門・堰は渦ができやすい。
- 堤防の横風は体を流す。風上側の石垣・建物壁を風よけに。
- 欄干の内側白線があれば必ず内側へ。
高架下・歩道橋・立体交差
- 歩道橋下は柱の内側が安全。車道側の抜けは風であおられる。
- 高架下は水はね・水たまりを避け、壁際の乾いた帯を選ぶ。
- 立体交差の合流点は車の死角が多い。一段低い場所は水が集まるので避ける。
狭い路地・袋小路・工事区間
- 袋小路では背を壁に、出入口を見張れる位置で待つ。
- 工事区間は仮設板・鉄板・段差が滑る。係員の見える位置まで戻る。
- ミラー裏・電柱の影は死角。見通しの利く四つ角へ移動。
海風・山あい(地域特有)
- 海沿いは防風柵の内側、建物の風下へ。
- 山あいは落石注意。ひさし・トンネル入口の側壁で待つ(車道側に出ない)。
地形別・危険と安全の目安
| 地形 | 避けるべき地点 | 待避の良い地点 |
|---|---|---|
| 坂のカーブ外側 | 車・自転車の接近が見えない | カーブ内側の壁沿い |
| 橋のたもと | 増水・水はね・見切り悪い | 橋の手前の広い歩道 |
| 高架下の吹き抜け | 風の通り道 | 柱内側・壁際 |
| 低地のT字路 | 水が集まる・車が切れ込む | 少し高い店先・段差上 |
| 工事の仮設鉄板 | 雨で極端に滑る | 係員近くの歩道側 |
施設から見つける待避:開いている・人がいる・助けを呼べる
公共施設と学校周辺
- 学校の門前・ピロティ:登下校時は人が多く見守りがある。警備員・先生に声をかけやすい。
- 公民館・図書館・出張所:入口の屋根+ベンチが定位置。開館時間を家庭で共有。
- 交番:地図に**「合流点」**として明示し、道順を覚える。
商店街・駅前・個店
- 商店の軒は雨・落下物・風から守られる。**「店の外で立ち止まり→声をかける」**の手順を教える。
- 駅前の喫煙所・駐輪場は人が多いが視界不良。入口近くの明るい場所で待つ。
- コンビニ:店内に入る→保護者へ連絡→店員に相談の三段階で。
医療・交通・地域拠点
- 医院・薬局の庇:雨宿りと応急処置の相談がしやすい。
- バス営業所・ターミナル:係員の目が届き、連絡放送がある。
- 郵便局・消防分団詰所:昼間は人がいることが多い。場所を地図で確認。
寺社・集会所・駐在所
- 門前・庇の下は風よけに最適。段差があり水が寄りにくい。
- 集会所は掲示板に緊急時開放の掲示がある場合。下見で確認。
- 駐在所は小規模でも頼れる窓口。位置を暗記。
施設別・開放性と頼りやすさ
| 施設 | 屋根 | 人目 | 開放性(時間) | 連絡の取りやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 学校門前・ピロティ | ◎ | ◎ | ○(登下校◎) | ◎ |
| 図書館・公民館 | ◎ | ○ | △〜○(開館中) | ○ |
| 商店の軒・コンビニ | ○ | ◎ | ◎(営業時間) | ◎ |
| 医院・薬局 | ○ | ○ | △〜○ | ○ |
| 郵便局・消防分団 | ○ | △〜○ | △〜○ | ○ |
| 寺社・集会所 | ○ | △〜○ | ○(行事時◎) | △〜○ |
| 交番・駐在所 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
時間帯・天気・季節で変えるコース:朝・下校・荒天・夏冬
朝(通勤が重なる)
- 自転車通勤の流れと逆側を通り、広い歩道を優先。
- 信号待ちは屋根のある位置を事前に把握し、止まる場所を固定。
下校(人通りが薄い)
- 商店前の連鎖を合流点として配置。裏道の近道は使わない。
- 日没前後は明るい帽子・反射材で存在を示す。
荒天(豪雨・強風・雷)
- 豪雨:段差の上・建物入口の上りへ移動。水が流れ込む低所を避ける。
- 強風:角・トンネル口は突風。建物の内側の角でやり過ごす。
- 雷:広場・高い単独樹・川原を回避。建物沿いで低姿勢。
季節の注意(夏・冬)
- 夏の熱・夕立:日陰と水分の確保。アスファルトの照り返しが強い場所は避け、商店の軒で冷却。
- 冬の凍結・みぞれ:橋・坂が滑りやすい。点字ブロックの段差でつまずきに注意。
現象別「やること/避ける場所」表
| 現象 | やること(1→3) | 避ける場所 |
|---|---|---|
| 豪雨 | 段差上へ→屋根下へ→連絡 | 低地・地下入口・橋のたもと |
| 強風 | 建物の内角→柱内側→停止 | 吹き抜け・角の先・高架の端 |
| 雷 | 金属柵から離れる→建物沿い→低くしゃがむ | 広場・単独の高木・河川敷 |
| みぞれ | 小刻み歩幅→手すり→白線回避 | 橋・斜面・金属板 |
| 猛暑 | 日陰確保→水分→短距離移動 | 無木陰の道・照り返し強い場所 |
時間帯別・推奨ルート例(作り方の型)
| 時間帯 | 基準 | 待避点の置き方 |
|---|---|---|
| 朝 | 自転車流と逆・広い歩道 | 交差点ごとに屋根のある待機点 |
| 下校 | 人目の多い通り | 商店前→寺社→交番の鎖配置 |
| 荒天 | 風雨・落雷回避 | 建物沿い→屋根→明るい場所連続 |
家庭・学校での共有:待避地図・声かけ・訓練
5分で作る「待避地図」
- 家→学校の地図に星=待避点、矢印=合流方向、電話絵=連絡可能地点。
- 番号順の合流文を短く:「1で待つ→10分で2へ→3で連絡」。
声かけテンプレ(店・交番・学校)
- 店:「雨宿りさせてください。○○小の△△です。連絡が取れるまでここにいます。」
- 交番:「○○小の△△。自宅は□□。保護者に電話をお願いします。」
- 学校:「荒天で店に待避。今は○○店前。10分後に××交番へ移動予定。」
5分×4回の訓練メニュー(週1で回す)
- 指差し・復唱:合図「止まる/右による/店に入る」を10回ずつ。
- 待避点ダッシュ:家の前→最寄りの屋根下まで安全に早歩き。
- 声かけ練習:家族が店員役。一言で用件→名前→所属。
- ルート確認:地図の番号順に歩く。新しい店や工事を更新。
家庭共有・書き込み表(配布用)
| 番号 | 待避点の名称 | 住所/目印 | 合図の言葉 | 次の移動先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 例:○○商店の軒 | ○丁目△番×号 | 「店に入る!」 | 2:□□神社の門前 |
| 2 | 例:□□神社の門 | 鳥居前の庇 | 「右による!」 | 3:××交番 |
| 3 | 例:××交番 | 三叉路角 | 「合流!」 | 家・学校へ連絡 |
事例で学ぶ:3つのケーススタディ
ケース1:下校時の急な豪雨
- 状況:帰り道に雷を伴う強い雨。視界が悪い。
- 行動:交差点手前の商店の軒へ→保護者へ連絡→10分後、交番へ合流。
- 振り返り:低地の横断歩道の中央に残らず、手前で止まれたのが勝因。
ケース2:強風と横断歩道の白線
- 状況:風が急に強まり、白線の上で足が滑りそうに。
- 行動:白線をまたいで乾いた帯へ→建物の内角でやり過ごす。
- 振り返り:角で減速→一旦停止→向きを変えるを守れた。
ケース3:不審者情報でルート変更
- 状況:近所で声かけ情報。通常の裏道を避ける必要。
- 行動:商店前の連鎖ルートへ変更→交番前を通過→学校へ連絡。
- 振り返り:人目の連続性がある通りを選べた。
Q&Aと用語辞典:迷いを先回りで解消
Q&A(よくある疑問)
Q1.店舗の軒で待つのは迷惑?
**A.入口をふさがず、「雨宿りさせてください」**と一言。早めに移動先を決め、長居しないのが礼儀。
Q2.交差点の中央に取り残されたら?
A.無理に戻らず、島状の安全地帯で待つ。信号が変わったら最短の歩道へ。白線の上では立ち止まらない。
Q3.不審者に追われたら?
A.人目のある店・交番へ直行。「助けてください。○○小の△△です」とはっきり。携帯は歩きながら使わない。
Q4.雷で大きな音がしたら?
A.金属柵から離れ、建物沿いで低くしゃがむ。単独の高木・広場は避ける。
Q5.友だちとはぐれたら?
A.地図の番号順に次の待避点へ進み、そこで待つ。逆走しない。
Q6.店が閉まっていた場合は?
A.同じ通りの次の庇へ。閉店でも屋根と人目があれば一時待避は可能。入口はふさがない。
Q7.地下道は安全?
A.豪雨時は水が集まりやすい。地上の屋根下を優先。
Q8.小さな子の合図は?
A.片手を高く上げて振る+大声で三語(止まる/右による/店に入る)。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 待避:危険を避けるため一時的に身を寄せること。
- 庇(ひさし):建物入口上の出っ張り。雨や落下物から守る。
- ピロティ:建物の1階が抜けた空間。屋根があり雨よけになる。
- 合流点:家族や先生と落ち合う場所。
- 風上/風下:風が来る側/流れていく側。
- 安全地帯:交差点の島状の待機場所。
- 白線:横断歩道の白い帯。濡れると滑りやすい。
持ち物チェックと貼り札テンプレ
日常持ち(ランドセル・かばん)
- 小さなタオル/ばんそうこう/連絡カード(氏名・学年・保護者連絡)/反射材シール。
- 折りたたみ雨具は軽く短いもの。風に弱い傘は避ける。
季節追加
- 夏:飲料・日よけ帽子。
- 冬:手袋・耳あて・滑りにくい靴。
玄関貼り札(そのまま使える)
「傘よし/靴底よし/合図よし」
待避点1→2→3、10分ごとに前へ
連絡カードは外ポケット
まとめ:道の“影”をつないで、家まで鎖のように
車から離れ、屋根で守り、人目のある場所を番号順に鎖のように並べておけば、どんな事態でも次の一手が見えます。地形を見る目と施設の開放性を日々更新し、家族・学校で共有しておくこと。通学路は、準備次第で不安の道から「守られた道」へ変えられます。