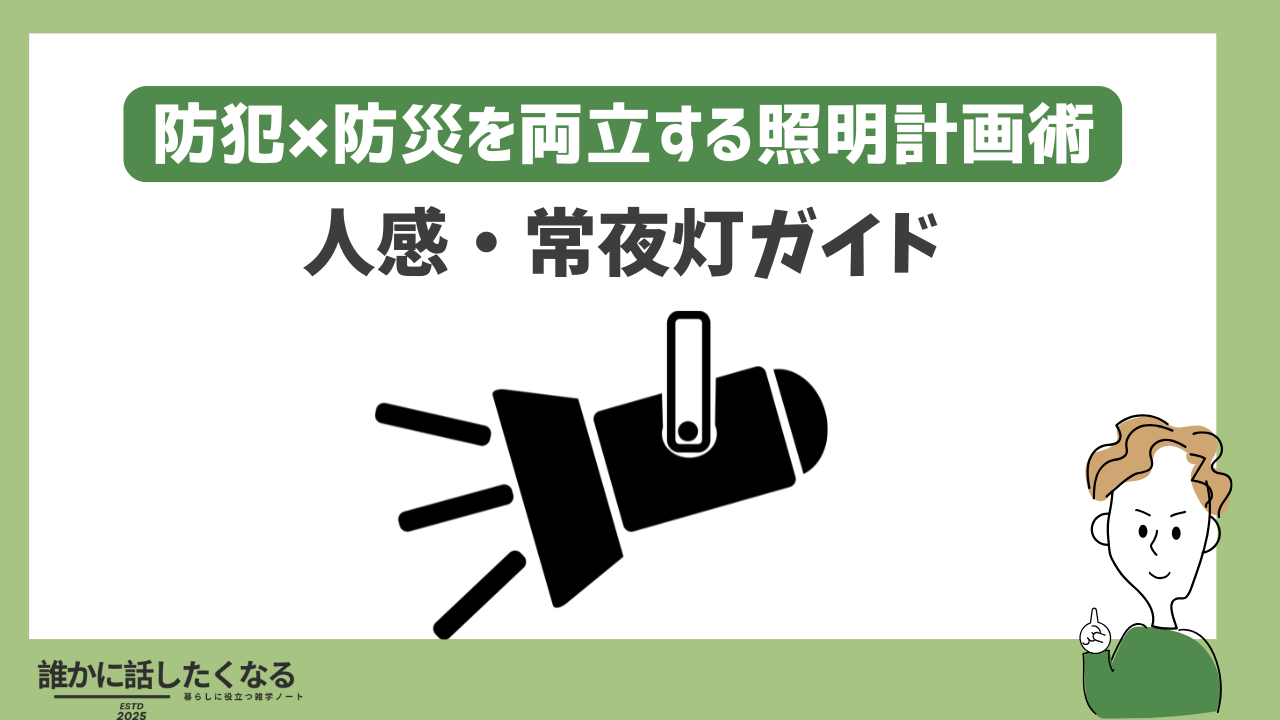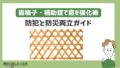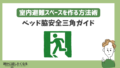「暗がりを減らして、停電でも迷わない」。 防犯と防災を同時に高める照明計画は、人感センサー・常夜灯・非常灯・蓄電を一体で組み合わせ、屋外で寄せつけず、屋内で導き、停電でも光を切らさないことが要となる。
本稿は、屋内外の配置基準、明るさの数値目安(ルクス)、停電時バックアップの設計、配線・電池運用、避難動線の見える化に加え、色温度・まぶしさ・電気代の考え方まで掘り下げた。家庭と小規模オフィスでそのまま使える表・チェックリスト・Q&A・用語辞典付きの実務ガイドである。
1.方針づくり:防犯と防災をつなぐ照明計画
1-1.目的の整理(何を守り、どこを照らすか)
防犯の要は侵入前の抑止、防災の要は停電時の導線確保。家や事務所の図面に侵入リスクの高い窓・出入口、夜間の移動経路、避難口を記入し、照らすべき場所を洗い出す。防犯で光は近づけば点く、防災で光は消えない・すぐ点くが正解だ。
1-2.明るさの基準(ルクスで考える)
| 場所 | 目安ルクス | 目的 |
|---|---|---|
| 玄関ポーチ・門柱 | 50〜100 lx | 顔の識別、鍵操作 |
| 駐車場・アプローチ | 20〜50 lx | 不審者抑止、段差確認 |
| 勝手口・裏庭 | 30〜70 lx | 死角解消、作業 |
| 室内通路・階段(平時) | 20〜50 lx | 安全歩行 |
| 室内通路(停電時) | 5〜10 lx | 退避に最低限 |
1-3.優先順位(三段階で配分)
第一に外周の抑止(門柱・駐車場・勝手口)。第二に出入口の識別(顔と手元)。第三に室内の避難動線(寝室→廊下→玄関)。電源と蓄電は外周>出入口>室内の順に強化し、最初の2時間で必要な光を確保する計画を立てる。
1-4.色温度と見え方(まぶしさを減らす設計)
電球色(約2700K)はまぶしさが少なく落ち着きやすい。昼白色(約5000K)は識別性が高く防犯向き。屋外の顔認識や表札はやや高め、寝室や廊下は低めがよい。演色性(Ra)が高い器具は人物の識別に役立つ。
| 場所 | 推奨色温度 | 備考 |
|---|---|---|
| 玄関・門柱 | 3500〜5000K | 顔識別を優先 |
| 駐車場 | 4000〜5000K | 影が弱く見やすい |
| 廊下・寝室 | 2700〜3000K | まぶしさ低減 |
1-5.電気代と省エネ(つけっぱなしに耐える設計)
常夜灯は低ワット・高効率が肝。人感点灯で無駄点灯を減らし、ソーラーや蓄電で停電時の電力を肩代わりさせる。明るすぎる器具を控えめの数で使うよりも、必要な場所に必要な明るさを分散したほうが総消費は下がる。
1-6.図面化の手順(紙とペンで十分)
平面図に灯具アイコンと検知範囲を描き込む。通路は点線で示し、避難口に非常灯マークを置く。ソーラー位置は日当たりもメモ。これだけで死角・過剰照明・電源の不足が可視化される。
2.屋外:人感+常夜灯で“寄せつけない”
2-1.配置の基本(重ねて死角を消す)
門柱・表札・ポストは常夜灯+人感の二段で常時は低照度、接近で明るく。駐車場・アプローチは歩行方向に沿って互い違いに置き、影の谷を作らない。勝手口や裏庭は縦長配光で足元と手元を同時に照らす。
2-2.器具と電源(配線/ソーラー/電池)
| 方式 | 長所 | 注意点 | 向く場所 |
|---|---|---|---|
| AC配線 | 明るい・安定 | 工事要・停電で消灯 | 常用ライト、門柱 |
| ソーラー | 停電に強い | 影・天候に左右 | 庭・塀・カーポート |
| 乾電池/充電池 | 施工不要 | 電池管理が必要 | 勝手口・臨時増設 |
併用が基本。常時の主照明はAC、停電時の保険はソーラー、一時増設は電池が扱いやすい。
2-3.人感センサーの設定(誤作動を減らす)
検知角は通路に斜めで人の動きが横切るように。点灯時間は30〜90秒が目安。長すぎると在宅が分かりやすく、短すぎると操作が忙しい。明暗しきい値は街灯や月明かりで誤点灯しない程度に調整する。
2-4.配光とまぶしさ(近隣配慮も含めて)
器具の角度を目線より下へ逃がすとまぶしさが減る。グレアカット板や庇で光を切り、敷地外へ漏れる光を抑える。カメラと併設する場合は逆光にならない位置へ配慮する。
| 配光形 | 向く場所 | 注意点 |
|---|---|---|
| 広角 | 駐車場・庭 | 眩しさに注意、角度を浅く |
| 縦長 | 通路・側道 | 先の足元まで届く |
| 狭角 | 表札・鍵穴 | 必要部だけを明るく |
2-5.近隣配慮と管理(苦情ゼロ運用)
夜更けの高出力点灯は点灯時間短縮や照度の段階切替で抑える。落葉や雪でセンサーが隠れないよう季節点検を入れる。門柱の常夜灯は明かりの色を周囲の景観に合わせると違和感が少ない。
3.屋内:常夜灯+非常灯で“迷わない”
3-1.避難動線を光で描く(寝室→廊下→玄関)
足元常夜灯をスイッチ下・コンセント位置に点々と配置し、寝室出口・階段の上と下・トイレ前・玄関をつなぐ。曲がり角は一灯追加で心理的な不安を減らし、夜間のつまずきを抑える。
3-2.停電時のバックアップ(選び分け)
| 方式 | 仕組み | 長所 | 弱点 | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 保安灯(コンセント型) | 通常充電→停電で自動点灯 | 工事不要・携帯ライトにも | コンセント位置に依存 | 廊下・寝室 |
| 非常灯(内蔵蓄電) | 常時給電→停電時に数時間点灯 | 明るい・誘導に最適 | 設置工事あり | 玄関・階段 |
| ポータブル電源+LED | 家電も照明も給電 | 長時間・多用途 | 充電管理が必要 | 家族の集合場所 |
3-3.寝室の最初の一灯(ヒヤリを減らす)
低位置スイッチと足元常夜灯で起床時のつまずきを防ぐ。小児・高齢にはベッドサイドの保安灯を用意し、片手で外せるタイプを選ぶ。夜間トイレまでの経路は連続した足元灯でつなぐと迷わない。
3-4.階段・手すり周り(転倒を防ぐ光)
踏面の先端が分かるよう段の影が出すぎない配光に。手すりの始まりと終わりを柔らかい光で示すと、上り下りの開始姿勢が安定する。色温度は低めが無難だ。
3-5.子ども・高齢者・ペット配慮(驚かせない)
急に明るくならないよう人感の点灯立ち上がりはゆるやかに。ペットの動きで誤点灯しやすい場所は検知高さを調整し、足元灯を常時弱点灯にしておくと安心。
4.停電に強い設計:蓄電・配線・運用のコツ
4-1.蓄電の考え方(何時間、どこを照らすか)
最初の2時間は避難・情報収集が中心。廊下・玄関・トイレを優先して電力を配分する。家族の集合場所にポータブル電源とランタンを常備し、携帯の充電と情報機器も支える。
4-2.回路と配線(分けて守る)
常夜灯回路は主照明と別に分け、停電時は蓄電系へ切替できるようコンセント位置を計画。屋外は防水コンセント、屋内はポータブル電源をつなぐハブを決めておく。ケーブルは足を引っかけないルートで配す。
4-3.月次・季節点検(貼って使える表)
| 項目 | 週次 | 月次 | 季節 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| 人感の反応 | ○ | ○ | – | 必要位置で確実に点灯 |
| 常夜灯の連続性 | – | ○ | – | 途切れなく導線を示す |
| バッテリー残量 | – | ○ | ○(夏・冬) | 50%以上維持 |
| 非常灯の自動点灯 | – | ○ | – | 3分以上安定点灯 |
| 屋外器具の防水 | – | – | ○(梅雨・台風) | ひび割れ・浸水なし |
| ソーラーパネル清掃 | – | – | ○(春秋) | 影・汚れを除去 |
4-4.ポータブル電源と灯りの容量早見表
| 用途 | 灯りの例 | 必要電力の目安 | 2時間確保の目安容量 |
|---|---|---|---|
| 廊下・玄関の足元灯 | LED 2〜4台(各1〜3W) | 2〜12W | 20〜30Wh |
| 集合場所の照明 | LEDランタン(5〜10W) | 5〜10W | 20〜40Wh |
| 情報機器 | 充電2台+ラジオ | 10〜20W | 40〜80Wh |
| 合計の一例 | – | 20〜40W | 80〜160Wh |
※一晩中(8時間)なら上記の4倍を目安にする。
4-5.交換周期と保守(寿命を伸ばす)
非常灯の内蔵蓄電池は数年で劣化する。点灯時間が短くなったら交換の合図。ソーラー灯の電池は年1回点検し、パネルの汚れは春秋に清掃。点検記録を残せば劣化傾向が見える。
5.選定・費用・Q&A・用語:迷わず導入するために
5-1.場所別おすすめ構成(ひと目で分かる)
| 場所 | 平時(防犯) | 停電時(防災) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 門柱・玄関前 | 常夜灯+人感投光 | ソーラー常夜灯 | 表札・鍵操作を明るく |
| 駐車場 | 人感投光器2台互照 | ソーラー補助灯 | 眩しさを回避 |
| 勝手口 | 人感+保安灯 | 乾電池式非常灯 | 裏動線の死角を消す |
| 廊下・階段 | 足元常夜灯連続 | 保安灯・非常灯 | 転倒予防が最優先 |
| 玄関・集合場所 | ダウンライト+常夜灯 | ポータブル電源+LED | 情報・物資の拠点 |
5-2.概算費用の目安(家庭向け)
| 項目 | 構成例 | 目安費用 |
|---|---|---|
| 屋外人感投光(2台) | AC配線・1000lm級 | 1.5〜3万円+工事 |
| ソーラー常夜灯(3台) | 門柱・塀・庭 | 1.2〜2.5万円 |
| 室内保安灯(4台) | 廊下・寝室・階段 | 6千〜1.5万円 |
| 非常灯(内蔵蓄電) | 玄関・階段 | 1〜3万円+工事 |
| ポータブル電源+LED | 300Wh級+ランタン | 2〜5万円 |
5-3.導入ステップ(つまずかない手順)
1)現地確認:暗い場所・死角・段差を夜に歩いて把握。2)図面化:灯具・検知範囲・避難口を書き込む。3)試験設置:仮置きで明るさと反応を確認。4)本設置:配線・固定・角度調整。5)家族周知:停電時の役割分担・保安灯の場所を共有。6)点検:月次・季節の表に沿って記録。
5-4.よくあるQ&A
Q:人感が頻繁に点いて在宅がばれない?
A:明暗しきい値と点灯時間を見直し、通行が少ない向きへ光軸を逃がす。常夜灯併用で不自然な点滅を避ける。
Q:停電時の持ちが不安。
A:保安灯+ソーラー+ポータブル電源の三層構えに。電池は月に一度残量確認。
Q:高齢の家族がまぶしいと言う。
A:色温度を低め(電球色)にし、遮光フードで眩光をカット。足元重点で上方向は控えめに。
Q:賃貸で工事が難しい。
A:ソーラー灯・電池式保安灯中心に。配線不要で原状回復が容易。
Q:非常灯はどれくらいで交換?
A:内蔵蓄電池の寿命(目安数年)を点検表に記録。点灯時間の短縮が出たら更新。
Q:人感でペットが反応してしまう。
A:検知高さの調整と感度の弱め設定で誤作動を抑える。足元灯の常時弱点灯に切り替える方法も有効。
5-5.用語辞典(平易な言い換え)
人感センサー:人の動きを感じて自動で点灯する装置。
常夜灯:一晩中弱い光で点けっぱなしにする灯。
保安灯:停電時に自動点灯し、携帯ライトにもなる室内灯。
非常灯:停電時に所定時間、明るく照らす内蔵蓄電の灯。
色温度:光の色味の尺度。電球色は落ち着く、昼白色は見えやすい。
演色性(Ra):色の見え方の自然さ。数値が高いほど顔色が正しく見える。
ルクス(lx):明るさの単位。数値が大きいほど明るい。
配光:光の広がり方。広角・狭角などの性格。
グレア:まぶしさのこと。遮光や角度で軽減できる。
まとめ
防犯×防災の照明は、外で近づけば点く、中で消えずに導く、停電でも重ねて光を確保の三本柱。これに色温度・配光・電源の重ね掛けという三つの工夫を合わせると、夜の不安と停電時の混乱は大きく減る。今日の一灯を正しい場所に、正しい明るさで—それが家族の安心を長く支える最短ルートだ。