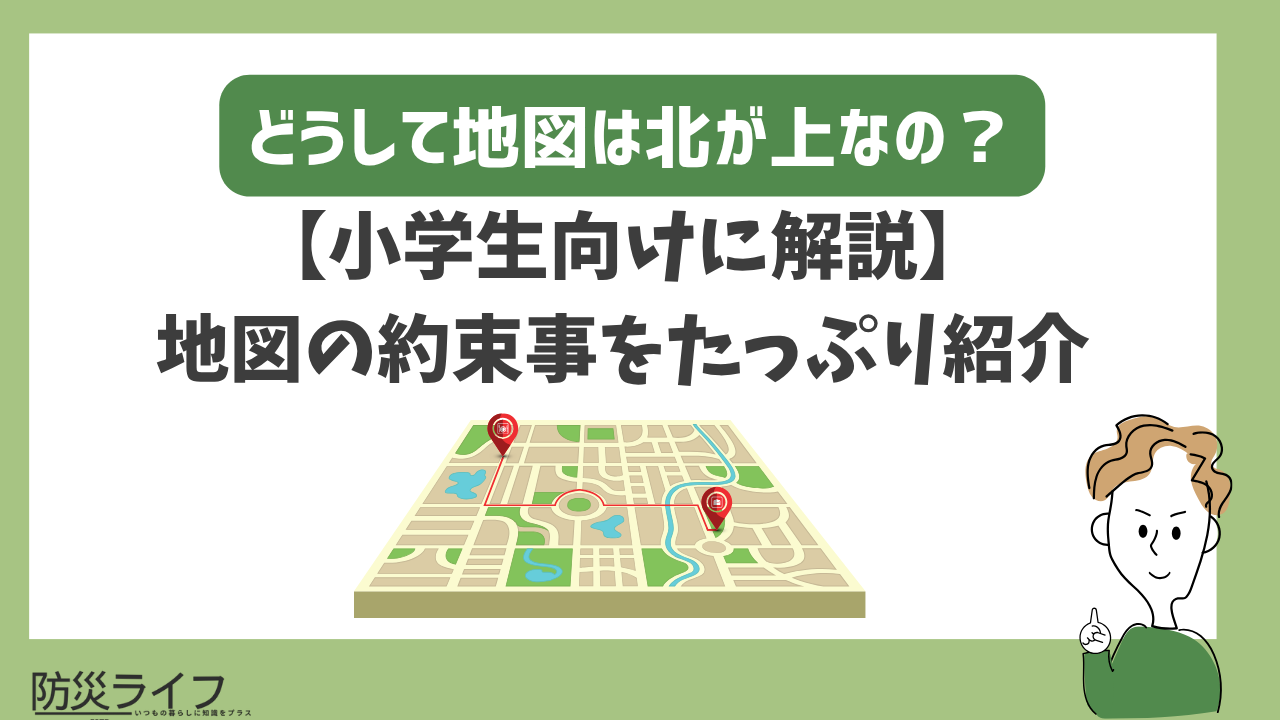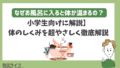「どうして地図はいつも北が上?」――そんな疑問に、歴史・ルール・読みこなし・世界の地図の見え方・デジタル地図の使い方まで、やさしい言葉で解説。読んだその日から、地図を“使える道具”に変えよう!
1.なぜ地図は北が上なの?基本の理由をやさしく
1-1 北が上は“世界共通の約束”だから
今の多くの地図は「上=北」。同じ向きでそろえると、国がちがっても見方が同じになり、だれでも比べやすく、迷いにくくなります。教科書・観光地図・世界地図を横に並べても、上が北だと位置関係がすぐ分かります。
1-2 みんなで方角をそろえると超便利
防災、旅行、授業、スポーツ(オリエンテーリング)など、北を上に固定しておくと、チームで情報を伝えるときにもズレが起きにくく、安全・迅速です。
1-3 例外もあるよ(逆さ地図・特別地図)
国やテーマによっては「南が上」「東が上」の地図もあります。南半球の国で自分たちの位置を強調するために南を上にしたり、駅の構内図やテーマパークでは進みやすさを優先して向きを変えることもあります。
1-4 “北”にも種類がある
- 真北(しんぼく):地球の自転の軸にそった、地図の本当の北。
- 磁北(じほく):方位磁石が指す北。地域や年で少しズレます。
- 地図の北:地図上で上に決められた北(図の北)。
→ 学校の地図はふつう真北基準。方位磁石を使うときは**磁気偏角(ズレ)**があることを覚えておくと“通”!
1-5 北は見つけやすい
北極星(きたの空の目印)や方位磁石で北を見つけやすいため、昔の船乗りや旅人にとっても便利でした。これも「北が上」が広がった理由です。
2.地図の歴史:方角のうつり変わり
2-1 昔は“上=南”や“上=東”もふつう
日本や中国、エジプトには南が上の地図がありました。王さまやお寺のある方角、太陽ののぼる東を大切にしていた時代もあります。
2-2 方位磁石の広まりで「北」基準へ
方位磁石(コンパス)が広まると、だれでも北を一定に決められるようになりました。船乗りや旅人が北を手がかりに道を決め、北基準の地図が増えました。
2-3 大航海時代と地球儀の登場
約500年前、ヨーロッパで世界地図・地球儀がたくさん作られ、その多くが北上でした。これがそのまま世界標準に。イギリスの**本初子午線(ほんしょしごせん/経度0°)**が使われ、世界の位置合わせが進みました。
2-4 港の地図・航海図の工夫
海の上では、風・潮・暗礁など危険がいっぱい。港町では**港湾図(こうわんず)**が作られ、灯台や浅瀬を正確に表すため、方角を統一する必要がありました。
3.地図を読みこなすための約束事(ルール)
3-1 方位記号(N・E・S・W)をチェック
地図のすみにある矢印やN(北)/E(東)/S(南)/W(西)を見れば、方角がすぐ分かります。屋外では太陽の位置・影・方位磁石でも確認できます。
3-2 縮尺(しゅくしゃく)で“距離感”をつかむ
縮尺は「現実の距離をどれだけ小さくしたか」を示す約束。例:1:10,000 → 地図1cm=現地100m。定規やスマホのスケール機能で、歩く時間の見積もりもできます。
- 練習:1:25,000の地図で学校まで4cm→ 現地1km(= 250m×4)
- 曲がった道の距離:定規で折り曲げる/糸をなぞって長さを測るのがコツ。
3-3 凡例(はんれい)と地図記号を読む
色とマークは情報の宝庫。凡例に記号の意味がまとめてあります。
- 色:山=茶/川・湖=青/平地=黄〜緑
- 記号:学校・駅・郵便局・神社・寺・田・畑・森林・病院 など
→ **危険箇所(がけ・川沿い・踏切)**も記号でチェック!
3-4 等高線(とうこうせん)で“高低差”を見る
等高線は、同じ高さをつないだ線。線の間隔がせまい=急な坂、広い=ゆるい坂。尾根と谷の形の見分けができると、歩く道を安全に選べます。
3-5 経度・緯度、グリッドで“位置”を表す
地球上の地点は**経度(東西)と緯度(南北)で表せます。地図の上に方眼(グリッド)**があると、座標で場所を伝えられて便利。
4.地図の見え方:投影法(とうえいほう)でこんなに違う!
地球は丸いので、平らな紙にすると形や大きさがゆがむことがあります。投影法のちがいを知ると、“地図の見え方”が納得できます。
| 投影法の名前 | 何が得意? | 気をつける点 | どんな用途で使われやすい? |
|---|---|---|---|
| メルカトル図法 | 角度・方位が分かりやすい | 高緯度ほど面積が大きく見える | 航海図、世界の位置関係ざっくり理解 |
| 正積図法(例:ガル・ピータース) | 面積の比が正しい | 形がのびる・つぶれる | 面積比較(人口・森林面積など) |
| ウィンケル・トリペル | 形・面積のバランスが良い | 少しずつ誤差がある | 一般向け世界地図、教科書 |
| 正距方位図法 | 中心からの距離と方位が正しい | 周辺がゆがむ | 航空路、震源からの距離表示 |
例:グリーンランドがアフリカと同じくらいに見える地図がありますが、面積はアフリカの方が約14倍ほど大きい。これは投影法の“見え方の違い”です。
5.デジタル地図の使いこなし
5-1 「北上」と「進行方向上」を切り替える
スマホやカーナビは、進む向きが上になる設定もできます。歩く・運転は進行方向上、学習・比較は北上に切り替えると頭が整理されます。
5-2 レイヤー(層)で情報を重ねる
航空写真/地形(等高線)/交通/自転車/混雑度など、目的に合わせてレイヤーを選ぶと、地図がもっと“話す”ようになります。
5-3 オフライン地図とバッテリー対策
山や海外では電波が弱いことも。事前に地図を保存/モバイルバッテリーを持つ/位置共有のしすぎに注意、など安全第一で。
5-4 プライバシーと安全
位置情報の共有は必要な範囲だけに。夜道の検索は明るい道を選ぶ、踏切やトンネルではイヤホン音量を下げるなど、地図+安全行動で守ろう。
6.“目的別”いろいろな地図
| 地図の種類 | 何がわかる? | 使いみち・コツ |
|---|---|---|
| 路線図(鉄道・地下鉄) | 乗換え・駅のつながり | 実際の距離より見やすさ重視。駅間所要時間と合わせて見る |
| 観光地図 | 見どころ・写真スポット | 名所のイラストで楽しく計画。混雑時間は別途調べよう |
| ハザードマップ | 洪水・土砂災害・津波の危険 | 自宅→避難所の安全ルートを2本以上確認 |
| 天気図・雨雲レーダー | 前線・風・雨の動き | 屋外活動の判断、雷注意報に注目 |
| 地形図(等高線) | 高低差・地形の特徴 | 山歩き・防災・土地の成り立ち学習に最適 |
| 統計(主題)地図 | 人口・農業・言語・産業など | 色分けの凡例を必ず確認、比較がコツ |
7.今日からできる!地図力アップ練習帳
7-1 マイ地図づくり(自由研究)
- 自宅から学校まで歩き、信号・橋・坂・横断歩道をメモ。
- 方角を確認して北上で下書き。
- 縮尺を決め、定規で清書。
- 凡例を作り、危険箇所は赤で表示。
→ 仕上げに家族へプレゼン!
7-2 三角測量ごっこ(やさしい版)
校庭で2本の定規とメジャーを使い、離れた木までの距離を測ってみよう。2つの地点からの角度で場所が決まることを体験できます。(安全に大人と実施)
7-3 太陽と影で方角を知る
- 正午前に棒を立て、影の先に印(A)。
- しばらくしてもう一度印(B)。
- A→Bの線が東西。その線に直角が南北。
※ 広い・安全な場所で実験しよう。
7-4 北極星で方角を知る(夜)
北斗七星からこぐま座の北極星を見つけると、だいたいの北が分かります。星座図アプリを使うと探しやすいよ。(夜間は安全第一)
8.防災に強くなる“地図の見方”
- 避難所・広域避難地:最寄りを地図で確認。夜道・雨天でも安全なルートを2本以上。
- 川・海・がけ:ハザードマップの色分けを確認。低地・合流点は水が集まりやすい。
- 集合場所:家族で2か所決め、地図と文字でメモ。スマホが使えない前提で練習。
- 通学路点検:踏切・交通量・歩道の幅・照明などを地図と実地でチェック。
9.“北が上”をもっと深く:比べて理解する表
9-1 北の種類くらべ
| 種類 | どうやって決まる? | 使う場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 真北 | 地球の自転軸にもとづく北 | 地形図・教科書 | いつも一定(基準) |
| 磁北 | 方位磁石が指す北 | 山歩き・屋外活動 | 地域・年で偏角がある |
| 図の北 | 地図の“上”として決めた北 | 路線図・案内図 | 実際の北と違うことがある |
9-2 地図の約束事・「北が上」まとめ表(拡大版)
| 地図のポイント | どんな意味?/読み方 | 使いこなしのコツ・観察ポイント |
|---|---|---|
| 上=北 | 世界共通で見くらべやすい | 例外の逆さ地図も“アリ”と知る |
| 方位記号 | N/E/S/Wで方角を示す | 太陽・影・方位磁石でも確認 |
| 縮尺 | 距離を小さく表す約束 | 地図1cmが何mか“声に出す” |
| 凡例・記号 | 地形・施設を素早く把握 | 危険箇所は赤で強調 |
| 等高線 | 高低差の読み取り | 間隔=傾斜のきつさ、谷と尾根の見分け |
| 投影法 | 見え方のちがいを理解 | 形・面積の“ゆがみ”に注意 |
| デジタル地図 | 進行方向上・レイヤー | オフライン保存、充電対策 |
| 特別地図 | 路線・観光・防災・統計 | 目的で読み方を切り替える |
10.かんたん地図クイズ(レベルアップ)
- 1:20,000の地図で8cmは現地で何m?
- 等高線の間隔がせまい場所は坂がゆるい/きつい?
- メルカトル図法は角度が正確?面積が正確?
- “磁北”と“真北”は同じ?ちがう?
- デジタル地図のレイヤーって何のこと?
こたえ:1) 1600m(=200m×8)/2) きつい/3) 角度/4) ちがう(偏角あり)/5) 情報を重ねる層のこと
11.Q&A よくある質問
Q1:どうして“北”がえらばれたの?
A:方位磁石と星で見つけやすい、航海・探検で道しるべになった、ヨーロッパ発の世界地図が北上で統一された――これらが合わさって世界標準になりました。
Q2:北が上じゃない地図はまちがい?
A:いいえ。目的に合った表し方です。路線図や観光図、南上の地図も立派な“正しい地図”。使う目的を確認しよう。
Q3:縮尺ってむずかしい…コツは?
A:最初に**縮尺バー(スケール)**を確認し、1cm=何mか声に出す。曲がった道は糸でなぞる、または定規を折り返して測ると分かりやすい。
Q4:スマホ地図はなぜ向きが変わるの?
A:現在地の向きに合わせて進行方向が上になる設定があるから。移動時は便利、学習時は北上へ切り替えよう。
Q5:地球儀と紙地図、どっちが正しいの?
A:どちらも正しい表し方。地球儀は形の正しさ、紙地図は見やすさ・比べやすさが得意。用途で使い分け!
Q6:防災で大事な地図の見方は?
A:避難所・高台・広場・危険区域(川沿い・がけ・低地)を色と記号でチェック。家族の集合場所とルートを2通り以上決めておく。
Q7:磁北と真北のズレ(偏角)はどうやって知る?
A:国土地理院や自治体の資料に目安値がのっています。登山地図には地域の偏角が書かれていることも。
Q8:世界の上下が逆の地図を見る意味は?
A:自分の見方をひっくり返すことで固定観念をやわらげる練習に。世界の多様性を学べます。
12.用語辞典(やさしいことばで)
- 方位記号:N(北)・E(東)・S(南)・W(西)。地図の方角を示す印。
- 縮尺(しゅくしゃく):現実の距離を小さく表すきまり。1:25,000なら地図1cm=250m。
- 凡例(はんれい):地図に使った色や記号の意味の一覧表。
- 地図記号:学校・駅・郵便局・神社・寺・田・畑・森林・病院などのマーク。
- 等高線:同じ高さの点をつないだ線。高低差が分かる。
- 投影法(とうえいほう):丸い地球を平らに表す方法。見え方が変わる。
- 経度・緯度:地球上の位置を表す数字。経度は東西、緯度は南北。
- 真北/磁北:真北=地球の軸の北。磁北=方位磁石が指す北(少しズレる)。
- グリッド:地図の上の方眼。場所を座標で伝えやすい。
- レイヤー:デジタル地図で情報を重ねて表示する仕組み。
13.まとめ
地図が「北が上」なのは、世界中で見方をそろえて比べやすくするため。でも、歴史や場所によって上下がちがう地図もあり、目的に合わせて表し方はさまざまです。
方位記号・縮尺・凡例・等高線・投影法を読み取り、紙地図・地球儀・デジタル地図を使い分ければ、世界はグッと分かりやすくなります。さあ、地図を片手に、学びと冒険を始めよう!