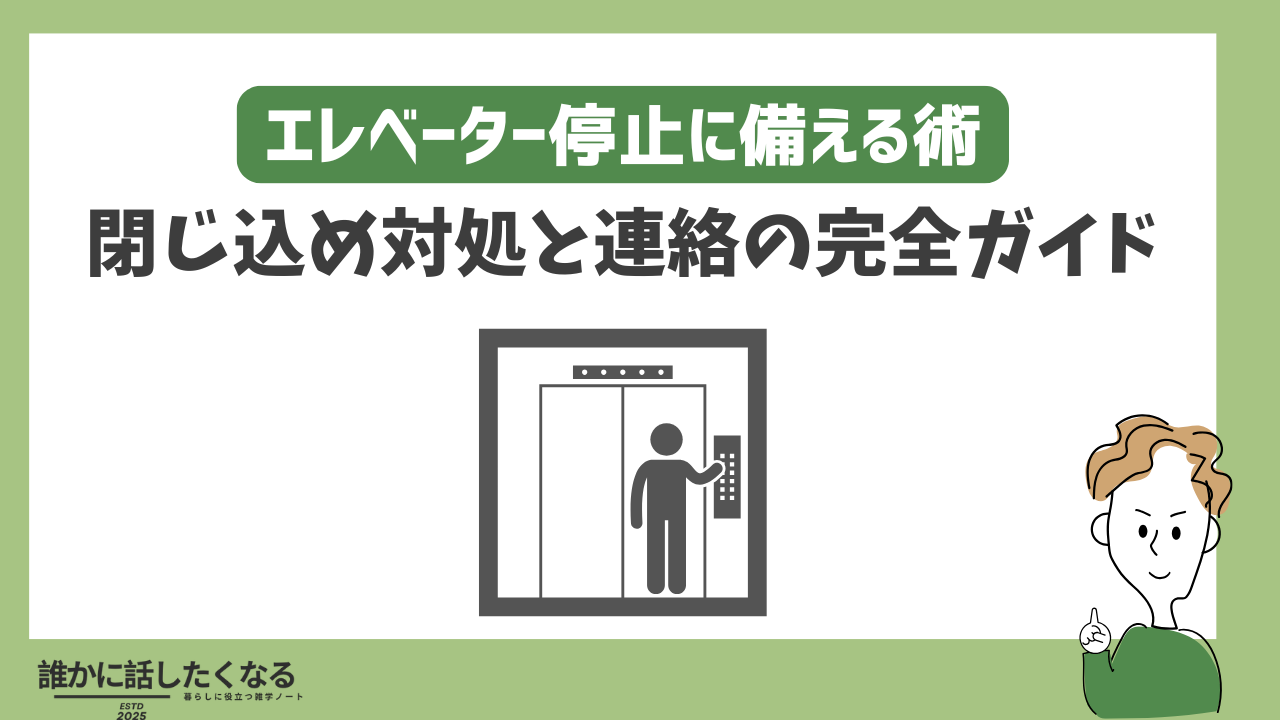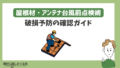停電や地震、機械故障でエレベーターが止まるのは珍しくありません。大切なのは、「閉じ込められても命を守る」ための手順を平時に決め、非常時は確実に伝える・待つ・節電するの3本柱を守ること。本ガイドは、事前準備→停止直後→閉じ込め中→救出後→再発防止の流れで、家庭・職場・マンション管理でそのまま使える形に整理しました。子ども・高齢者・障害当事者の視点も織り込み、印刷して貼れる表とチェックリスト、Q&A、用語辞典まで一括で掲載します。
加えて、停止の主因(停電・保安回路の作動・地震感知・火災連動・戸閉不良・定員超過・落雷・浸水・通信断)と、それぞれの初動の優先順位を明確化します。はじめの3分で「場所・階数・人数・体調」を整え通報を確立、10分で姿勢と水分を整え、30分で体温維持と衛生を確保、60分超では省電力運用と定期連絡をルーチン化——という時間帯別の行動基準も示します。無理な脱出を避け、「かご内の安全を確保しながら助けを呼び続ける」ことが最短の解決であると理解できるはずです。
対象は、日常的にエレベーターを使う家庭の保護者、職場の安全担当、マンション管理者。多言語の定型文や筆談カード、要配慮者(小児・妊婦・高齢者・障害当事者)への具体的配慮、夜間・休日体制の作り方まで踏み込みます。読み終えたらそのまま掲示できる要点表と貼って使える手順カードで、迷いを即座に行動へ変えましょう。
1.停止に備える事前準備:連絡・物品・掲示を整える
1-1.連絡先と通報チャネルの整備
- 保守会社の直通番号、管理室、119/110を乗場の見やすい位置とスマホに登録。
- 通話不能時の代替:非常ボタン→インターホン→携帯→館内放送の順番を館内で共有。
- 外国人・聴覚障害者向けに定型文カード(「エレベーターに閉じ込められています。階数は◯階表示です。」)を用意。
1-2.非常備品の配置(かご内・乗場)
- かご内:簡易トイレ、飲料水小瓶、毛布/アルミシート、ライト、携帯電源、マスク、手袋。
- 乗場(機械室付近):工具は原則管理者のみが扱う。利用者が手を出さない運用を明記。
- 衛生:使い切り用品は密閉袋へ。交換時期は半年ごと掲示。
1-3.掲示・訓練・役割分担
- 停止時手順ポスターを各階乗場・管理室に掲示。
- 年2回の避難訓練で閉じ込め時の声掛け・情報伝達をロールプレイ。
- 夜間・休日の当番表を作成し、救助要請→安否確認→誘導の役割を分担。
事前準備チェック表(掲示用)
| 項目 | 内容 | 点検頻度 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 連絡先 | 保守・管理・緊急の番号掲示 | 半年 | 管理室 |
| 物品 | 簡易トイレ/水/毛布/ライト | 半年 | 防災担当 |
| 訓練 | 年2回ロールプレイ実施 | 半年 | 総務 |
| 当番 | 夜間/休日の体制表 | 四半期 | 管理組合 |
2.停止直後の行動:安全確認と通報の“最短手順”
2-1.無理な脱出はしない
- 内扉をこじ開けない、屋根に上らない。上下に急発進する危険あり。
- 体勢を安定:背を壁に預け、足を肩幅に。荷物は床へ下ろす。
2-2.階数・状態の把握(言葉の準備)
- 階数表示、扉の隙間の有無、室内人数・体調、停電の有無をメモに箇条書き。
- 定型通報文を用意:「◯号機で停止。表示は◯階付近。◯人。けが人◯。呼吸困難なし。」
2-3.通報チャネルの使い分け
- 非常ボタン→管理室/保守直通→不通なら携帯電話→館内放送→最後に119/110。
- 通話が難しい環境では、短文+ゆっくり。静かな者が話す、話者交代で疲労を防ぐ。
通報時のポイント早見表
| 確認事項 | 例 |
|---|---|
| 場所 | ◯◯ビル ◯号機 |
| 階数 | 表示は4階と5階の間 |
| 人数 | 大人3/子ども1 |
| 体調 | けがなし・1名不安強 |
| 電源 | 館内停電らしい |
| 連絡 | 非常ボタン応答あり |
3.閉じ込め中の過ごし方:空気・水分・安心の確保
3-1.空気と温度の管理
- 換気口・隙間から空気は入る。扇ぐ・走るなど消耗行動は避ける。
- 暑さ:上着を脱ぎ、扇子/紙で静かに送風。寒さ:アルミシートで身体を包む。
3-2.体調管理と衛生
- 座り方:壁に背、膝を立てて腹圧を逃がす。持病の薬は最優先で服用。
- 水分:のどが渇く前に小口で。子ども・高齢者を優先。
- 簡易トイレ:かご隅に目隠し(毛布・上着)。使用後は密閉袋へ。
3-3.心のケアと情報共有
- 役割を決める(通報役・記録役・声掛け役)。
- 時間の区切り(5〜10分ごと)で体調確認。「大丈夫です」の声を保守側へ届ける。
- 暗所:ライトは点滅ではなく常時弱。バッテリーを節約。
かご内・安心のための行動表
| 目的 | 行動 | 備考 |
|---|---|---|
| 安全 | 無理な脱出禁止 | 二次災害回避 |
| 連絡 | 5〜10分ごとに状況送信 | 体調変化は即時 |
| 体力 | 立位⇔座位を交代 | 血行促進 |
| 衛生 | 簡易トイレ使用/密閉 | 匂い対策にシート |
4.救出後〜再開まで:記録・受診・再発防止
4-1.救出直後の注意
- 急に立ち上がらない。立ちくらみに注意し、壁づたいに移動。
- 扉の隙間や機械室に近づかない。作業員の指示に従う。
4-2.記録と報告(次に備える)
- 時刻・階数・人数・要救助時間、体調変化を記録。管理室へ提出し、掲示板で共有。
- 原因の仮説(停電・地震・故障)と改善要望(掲示更新・備品補充)をメモ。
4-3.健康チェックと受診の目安
- 胸痛・息苦しさ・強い不安が続く場合は受診。子ども・妊婦・高齢者は低血糖・脱水に注意。
- 擦過傷・打撲は冷やす→洗う→保護。感染徴候があれば医療機関へ。
救出後のフローチャート(要点)
| 段階 | 行動 |
|---|---|
| 1 | 安静・水分・深呼吸 |
| 2 | 管理室へ状況報告 |
| 3 | 体調変化を自己/相互確認 |
| 4 | 必要に応じて受診 |
| 5 | 再発防止の提案と掲示更新 |
5.多様な利用者への配慮と運用:子ども・高齢者・障害当事者
5-1.子どもと保護者のポイント
- 非常ボタンを押す勇気を育てる。「押していい」訓練を定期的に。
- 暗闇の不安に備え、小型ライトをランドセルに。
- 合言葉:「落ち着いて、座って、水のむ、待つ」。
5-2.高齢者・持病のある人のポイント
- 薬を分けて携帯。足腰が弱い人は座位で待機、体位変換を手伝う。
- 補聴器・眼鏡の予備電池・ケースを非常持出しへ。
5-3.障害当事者への配慮
- 聴覚:筆談ボード・定型文カードを常備。
- 視覚:ライトで足元を照らし、段差を声で伝える。
- 車いす:ブレーキ・足置きの位置を確認し、移動時は声かけを徹底。
利用者別・配慮の一覧表
| 対象 | 配慮 | 具体策 |
|---|---|---|
| 子ども | 不安軽減 | 合言葉・ライト・押していい訓練 |
| 高齢者 | 体力低下 | 座位・水分・体位変換 |
| 聴覚 | 伝達 | 筆談・カード・指差し確認 |
| 視覚 | 誘導 | 足元照射・段差実況 |
| 車いす | 安全 | ブレーキ/足置き確認・声かけ |
Q&A(よくある疑問)
Q1. 閉じ込められたら扉をこじ開けてもいい?
A. **絶対にしません。**再始動や落下の危険があります。非常ボタン→通報→待機が基本です。
Q2. 通話ができない/圏外なら?
A. 非常ボタンとインターホンを最優先。大声で叫ばず、床を一定間隔で軽く叩くなど規則音で知らせます。
Q3. 息苦しいと感じたら?
A. **姿勢を変え、服をゆるめ、ゆっくり深呼吸。**換気口から空気は入ります。扇いだり走ったりはしないで体力温存を。
Q4. 停電時に自動で最寄階に止まる機能は?
A. 設置により有無が異なります。管理室に確認し、掲示して共有しましょう。
Q5. 子どもだけの乗車中に停止したら?
A. 非常ボタンを押す→名乗る→座って待つを教え込みます。保護者は建物名・号機を把握しておくと通報が早いです。
Q6. 長時間になったら水やトイレは?
A. 小口で水分、簡易トイレを使用。目隠しと密閉袋をかご内に常備すると安心です。
用語辞典(やさしい言い換え)
- かご:人が乗るエレベーターの箱。
- 乗場:各階のエレベーター前。
- 非常ボタン:保守や管理室につながる呼び出しボタン。
- 号機:同じ建物に複数ある場合の機械の番号。
- 最寄階停止:停電時などに一番近い階に自動で止まる機能。
まとめ:伝える・待つ・節電の3本柱
エレベーター停止への最適解は、無理をしないこと。伝える(正確な通報)、待つ(安全姿勢と体調管理)、節電(ライト・携帯の電源)の3本柱を守れば、閉じ込め時間が長くても命は守れます。平時の掲示・備品・訓練を整え、誰が・何を・何分でできるかを見える化しておきましょう。