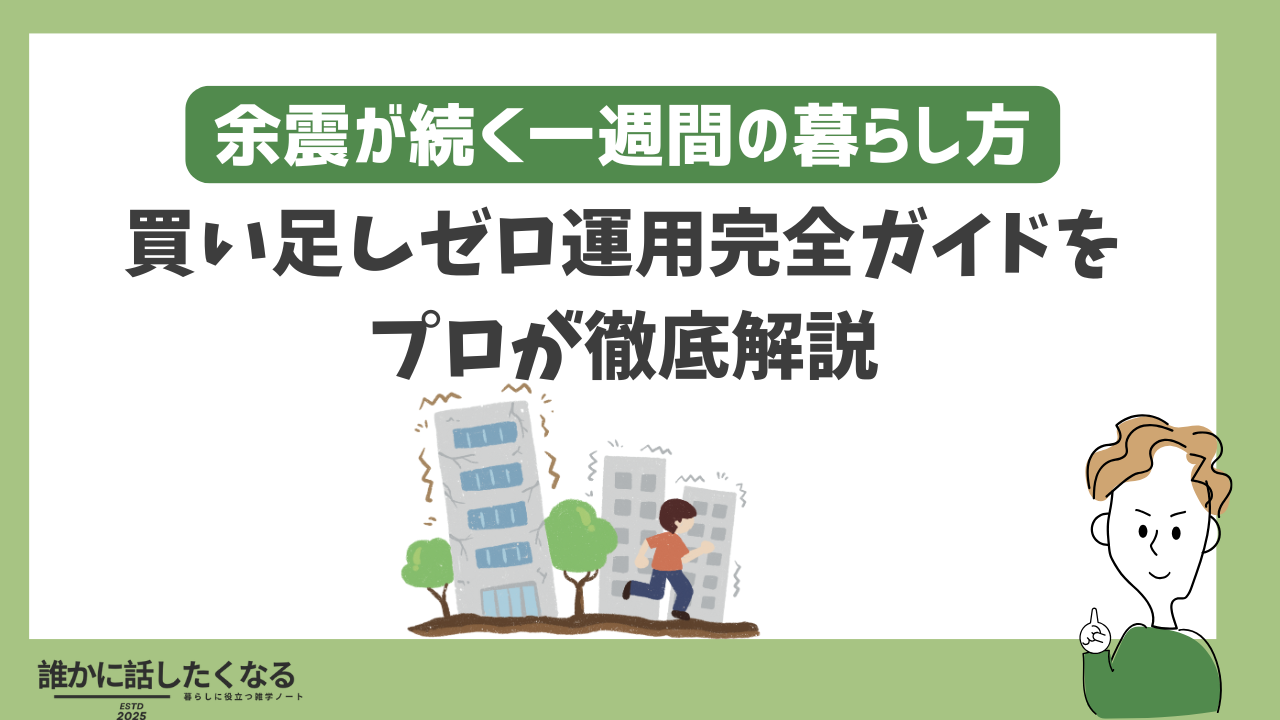余震が続くときは、買い足しを前提にしない運用に切り替えるのが安全かつ現実的です。鍵は、水とエネルギーの節約配分、住まいの安全運用、日課化による心身の安定。
本記事は、発災直後から7日間を家族単位の行動設計に落とし込み、食・水・衛生・灯り・情報・睡眠を“手持ちの物だけ”で回すための完全ガイドです。
1.結論と原則:0〜24時間/2〜3日目/4〜7日目の設計
1-1.0〜24時間:命を守り、暮らしを「安定モード」へ
- 安全確認:落下物・ガス臭・感電リスクの排除。玄関と通路は幅90cmを確保。
- 水と灯りの棚卸し:飲料水、湯沸かし手段(カセット・固形燃料・保温ボトル)、乾電池、充電残量を紙に見える化。
- 寝床再配置:窓・高家具・割れ物から離す。靴・ライト・笛は枕元。夜は**一点照明(ヘッドライト)**を基本。
1-2.2〜3日目:買い足しゼロの回し方に移行
- 水は“飲む>食べる>洗う”の順に優先。紙皿・ラップで洗い物ゼロ化。
- 無火・少火メニューへ切替。温かさは湯たんぽ/保温ボトルで補う。
- 情報の整え:ラジオ、携帯、省電力モード、充電の時間割りを決める。朝夕2回の確認に絞り疲労を軽減。
1-3.4〜7日目:節約を「習慣化」し疲れを貯めない
- 朝夕のミニ点検(ガス・電気・水・破損・体調)。
- 睡眠・休息の枠を先に確保(昼の短い仮眠を許す)。
- ご近所との物資・作業の交換で偏りをならす。安否メモを玄関に掲示。
1-4.家庭タイプ別の初動(単身/子連れ/高齢者/ペット)
- 単身:作業と休息の時間割を紙で固定。充電と水の残量メモを見える場所へ。
- 子連れ:**役割(ライト係・メモ係)**を渡し、できたことを言葉で承認。不安の回路を断つ。
- 高齢者:トイレ動線の短縮、段差解消、座った姿勢での洗顔・歯磨きを基本に。
- ペット:クレート固定・水・トイレ砂をひとまとめ。避難所ルールを家族で共有。
1-5.在宅/避難の判断基準 早見表
| 状況 | 在宅継続 | 一時避難 | 退避の基準 |
|---|---|---|---|
| 建物 | ひび小・出入口可 | 天井落下物・ガラス多数 | 柱や壁の大きな歪み |
| 周辺 | 火災遠い | 近隣でガス臭 | 火の手・黒煙が接近 |
| 地形 | 高台・内陸 | 低地 | 津波・浸水の恐れ |
1-6.72時間→7日への移行サイン
- 水が計画通り回る、睡眠が6時間取れる、通路が維持できている → 7日運用へ移行。
- めまい・不眠・食欲低下が続く → 作業を半分に、助けを求める。
7日間の“優先順位表”
| 項目 | 優先 | 理由/目安 |
|---|---|---|
| 水 | 最優先 | 1日1人3L(飲用2L+調理1L) |
| 灯り | 高 | 夜間の安全・心理安定 |
| 食 | 高 | 高カロリー・保存優先 |
| 情報 | 中 | 正確な避難・支援情報 |
| 洗浄 | 中 | 手指・口腔は重点、食器は簡略 |
2.食・水・衛生を「買い足しゼロ」で回す
2-1.飲料水と節水調理の配分
- 基本配分(成人1人/日):飲用1.5〜2.0L、調理・歯磨き・薬0.5〜1.0L。
- 節水の工夫:湯せん料理(袋麺・レトルト)は鍋の水を再利用。蒸し焼きは水少量で温かさ確保。
- 洗い物ゼロ化:皿はラップ/紙皿、コップはマイボトルで使い回す。まな板は使わない。
1日の水配分(例)
| 用途 | 朝 | 昼 | 夜 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 飲用 | 500ml | 500ml | 500ml | 1500ml |
| 調理/歯磨き | 200ml | 200ml | 300ml | 700ml |
| 合計 | 700ml | 700ml | 800ml | 2200ml |
2-2.無火・少火メニュー(買い足しゼロ)
- 無火:ツナ缶+クラッカー、さば味噌缶+パン、ドライフルーツ、ナッツ。
- 少火:湯せんでレトルトごはん・カレー、蒸しでじゃがいも・根菜。
- 温度の工夫:保温ボトルに熱湯を満たして保温、湯たんぽで体を温めて食欲維持。
3食×7日 無火・少火メニュー例
| 日 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 1 | パン缶+ピーナッツ | ツナ缶+クラッカー | レトルトごはん+缶詰カレー |
| 2 | ビスケット+果物缶 | さば味噌缶+パン | スープパック+乾パン |
| 3 | シリアル+粉乳 | いわし缶+クラッカー | どんぶりレトルト |
| 4 | パン缶+はちみつ | ささみ缶+コーン缶 | おでん缶+ごはん |
| 5 | クラッカー+チーズ | 豆缶+コーンスープ | カレー+ごはん |
| 6 | ドライフルーツ | 焼き鳥缶+パン | シチュー缶+ごはん |
| 7 | 乾麺(湯戻し) | サラダ豆+スープ | 鮭缶+アルファ米 |
2-3.衛生:トイレ・手洗い・食器
- 簡易トイレ:便座に袋+凝固剤。1人/日5回分を目安。二重袋で臭いと漏れを軽減。
- 手洗い:水はコップ1杯を流さず使う(拭き取り→消毒)。爪は短く保つ。
- 食器:ラップ・紙皿で洗い物ゼロ化。缶は口を拭いてから食べる。
2-4.栄養と体調維持(買い足しゼロでもできる)
- たんぱく質:魚缶・鶏ささみ缶・豆缶を1日1品。
- 塩分:汗をかく日は味噌汁パックで補う。むくみが出たら量を調整。
- 甘味:はちみつ/ジャム/果物缶でエネルギー補給。寝る直前は控えめ。
7日間の栄養バランス メモ表
| 栄養 | 例 | 目安 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 魚缶/豆缶/ささみ缶 | 毎日いずれか1品 |
| 塩分 | 味噌汁/スープ | 発汗時に1杯 |
| 糖質 | パン缶/ごはん/乾麺 | 各食で主食1つ |
2-5.子ども・高齢者の食の注意
- 子ども:甘味は少量頻回、好きな食感を優先。窒息しやすい堅い物は避ける。
- 高齢者:柔らかく・温かく。水分ゼリーで嚥下を助ける。
3.住まいの安全運用:余震に強い配置と行動
3-1.寝床と動線の再配置
- 窓・高い家具・ガラス前から寝床を離す。通路は90cm。割れ物は低い位置へ移動。
- 枕元セット:靴・ライト・笛・携帯、ヘッドライトが便利。軍手を追加。
3-2.ガス・電気・灯りの扱い
- ガス:臭い・異音があれば元栓を閉。復帰操作は落ち着いて行う。迷えば専門家を待つ。
- 電気:濡れた床・破損箇所ではブレーカーOFF。再通電前に漏電の恐れを点検。
- 灯り:乾電池ランタン・ヘッドライト中心。ロウソクは転倒火災の恐れがあるため避ける。
省エネ“灯り運用”表
| 灯り | 使いどき | 代替 |
|---|---|---|
| ヘッドライト | 夜間移動/作業 | 置き型ランタン |
| ランタン | 食事/家族の時間 | 壁反射で拡散 |
| 懐中電灯 | 点検 | 予備電池を同封 |
3-3.入浴・洗濯の代替
- 体拭き:濡れタオル→乾拭きの順。ワセリンで肌保護。
- 髪:ドライシャンプーやお湯少量+タオル。
- 洗濯:袋もみ洗い→陰干し。衣類は重ね着で回数を減らす。
3-4.小さな修繕と養生(家の応急)
- ガムテープ・養生テープでガラス割れ目の固定。段ボールで割れ物の仮覆い。
- ブルーシートで雨仕舞い、ロープで固定。風下側から作業。
家の中の“危険ゾーン”回避表
| 場所 | 避けたいこと | 代替 |
|---|---|---|
| 窓際 | 就寝・荷物の山 | 壁側の低家具前へ |
| 高家具周り | 子どもの遊び場 | 床座スペースを別に確保 |
| 台所 | 長時間の加熱 | 湯せん・蒸しに短縮 |
4.情報・連絡・心のケア:混乱時の“整え方”
4-1.情報の整え方
- 出所・時刻・場所の明確な情報を優先。出所不明は「参考」に留める。
- 紙のメモに、今日の予定・注意点を書き、家族で読み合わせ。
- 充電の時間割:日中は省電力モード、充電は安全時間帯にまとめて。
4-2.近所との助け合い
- 声かけ対象(高齢者・乳幼児家庭)をメモ。水・道具・作業の交換で偏りをならす。
- 掲示板/玄関ドアに簡易メモ(在宅/外出)を掲示。
4-3.睡眠と不安対処
- 昼の仮眠(15〜20分)を許容。夜は照明を落として入眠儀式。
- 呼吸法:4秒吸う→6秒吐くを数分。背中呼吸で肩の力を抜く。
- 子どもには**役割(懐中電灯担当など)**を渡し、できたことを言葉で確認。
4-4.デマ対策の要点
- **「誰が」「いつ」「どこで」**がない情報は拡散しない。スクショ保存→後で検証。
- 不安を煽る文言のみの投稿は距離を置く。
4-5.情報メモのテンプレ
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 今日の危険 | 倒木で通行止め、屋根からの落下物 |
| 今日の優先 | 水2.2L/人、充電18:00〜20:00 |
| 連絡 | 親族Aへ19:00に状況報告 |
5.役割分担・日課・チェックリスト:疲れをためない仕組み
5-1.家族の役割分担(例)
| 役割 | 主担当 | 代替 | ひと言メモ |
|---|---|---|---|
| 水の管理 | 大人A | 大人B | 残量メモを冷蔵庫に貼る |
| 灯り・充電 | 大人B | 大人A | 充電の時間割を守る |
| 食事準備 | 大人A | 大人B | 無火/少火の原則 |
| 子ども担当 | 大人B | 大人A | 就寝前の声かけ |
| 近所連絡 | 大人A | 大人B | 安否メモをポストへ |
5-2.朝夕のルーティン
- 朝:水・ガス・電気・破損・体調の確認→その日のメニューと充電計画を決定。
- 夕:使用量の記録→翌日の配分見直し→寝床と通路の点検。
5-3.1日点検リスト(チェック式)
| 項目 | 朝 | 夕 |
|---|---|---|
| 水の残量を確認・記録 | ||
| 充電残量と使用計画 | ||
| ガス・電気の安全 | ||
| 寝床・通路の安全 | ||
| 食材の消費・補充計画 | ||
| 近所安否・掲示メモ更新 |
5-4.時間割の例(無理しない)
- 6:30 起床→通路点検→朝の水配分
- 7:00 朝食(無火)→洗顔・口腔
- 8:00 家事小分け(15分×2)
- 12:00 昼食(少火)→短い休息
- 15:00 近所連絡・物資交換
- 18:00 夕食→充電タイム
- 20:00 温め(湯たんぽ)→就寝準備
Q&A(よくある疑問)
Q1.水が足りない。最小限は?
A. 飲用を最優先に1日1人1.5Lを確保。調理は湯せん再利用、食器はラップで水を使わない。
Q2.カセットガスが少ない
A. 無火メニューへ寄せ、加熱は湯せん一括で効率化。保温ボトルで温かさを伸ばす。
Q3.子どもが怖がって眠れない
A. 役割を渡す(懐中電灯担当など)→できたことを言葉で認める→柔らかい光で寝かしつけを。
Q4.入浴できないときの汗とにおい
A. 濡れタオル→乾拭き、脇・首・足を重点、ワセリンで保護。着替えは重ね着で回数を減らす。
Q5.冷蔵庫が止まった
A. 先に冷凍→冷蔵→常温の順で消費。開閉を減らし、保冷剤と発泡容器を活用。
Q6.情報が多すぎる
A. 出所・時刻・場所が明確なものだけ採用。朝夕の2回だけ確認に絞ると疲れにくい。
Q7.トイレ袋が足りない
A. 二重袋を優先し、凝固剤の使用量を守る。新聞紙・猫砂で吸水補助。
Q8.電池が底をつきそう
A. ヘッドライト中心で使い、壁反射で広げる。点灯時間を必要最小限に。
Q9.夜の冷えがつらい
A. 湯たんぽ+重ね着+首・足首の保温。寝床は窓から離す。
Q10.ペットのトイレが心配
A. 使い慣れた砂・シートを優先。水と餌は少量頻回に。
用語辞典(やさしい解説)
- 湯せん:袋や缶をお湯で温める調理。鍋のお湯を再利用できる。
- 保温ボトル:熱湯を入れて温度を保つ容器。調理の補助や体の温めに有効。
- 二重袋:袋を二枚重ねにすること。臭い・漏れの軽減に役立つ。
- 省電力モード:携帯の電池消費を抑える設定。通知や明るさを控えめにする。
- 湯たんぽ:お湯を入れて温める容器。寝床や服の中を暖め、燃料節約に役立つ。
- 養生:壊れた部分を応急で覆う・保護すること。ガムテープや段ボール、ブルーシートを使う。
まとめ
余震が続く一週間は、買い足しゼロでも配分と習慣で乗り切れます。水は飲む>食べる>洗う、食事は無火・少火、住まいは寝床と通路の安全を最優先。朝夕の点検と役割分担で迷いを減らし、正確な情報と小さな休息で心身を守りましょう。今日から棚卸し→配分表の作成→寝床の再配置を実行してください。