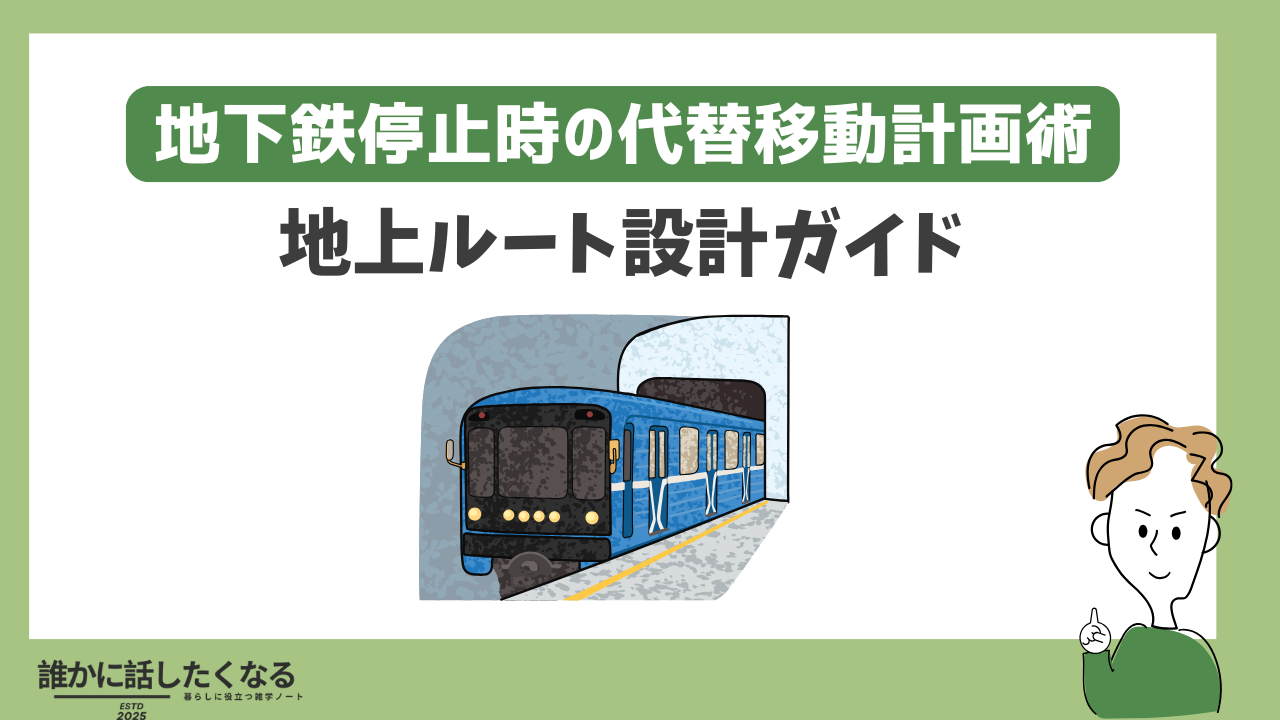止まっても、迷わず動ける設計図を。 事故・停電・点検・自然災害などで地下鉄が停止した瞬間、手元にあるべきは「地上の骨格」「決める順」「同じ言葉の短文」。
本稿は、出発前→駅での初動→地上ルート運用→結節点での乗継→在宅判断の5段で、背骨の道づくり・徒歩/バス/相乗りの切替・混雑/悪天候の安全策・家族/同僚との役割分担までを具体化しました。通勤・通学・受験・出張・通院のいずれでもそのまま使える表とテンプレを多数収録しています。
1.出発前の設計:地下鉄が止まる前に“地上の骨格”を持つ
1-1.地図の三層化(幹線・並行鉄道・結節点)
- 幹線道路=背骨:歩道幅と外灯がある太い通りを一本通しで確保。曲がり角は大きな交差点に限定し、裏道の近道は切り捨てる。
- 並行鉄道=第二の足:地上の私鉄・JRなど並行線を地図に重ね、乗換え可能な駅名を3つ書いておく。
- 結節点=たまり場:大駅・バスターミナル・官公庁を中継地に指定。屋根・照明・トイレの有無を事前確認。
三層化メモ(5分で作る)
1)背骨の道に太線、2)並行鉄道の駅に丸印、3)結節点に星印、4)徒歩分を地図の余白へ手書き。
1-2.徒歩圏の数字化(分・斜度・橋)
- 100m=1分(大人)/2分(子ども・高齢)を基準に、坂・橋・陸橋は+2〜5分を上乗せ。
- 雨・雪・強風は**所要+20〜40%**で見積もる。横断は信号交差点のみと決めて計算。
- 夜間は明るい道優先で**+10%**。点滅信号の渡り直しも所要に含める。
徒歩分・補正早見表
| 条件 | 補正 | 例 |
|---|---|---|
| 坂・橋・陸橋 | +2〜5分 | 川越え・高架横断 |
| 雨・雪 | +20〜40% | 雪の轍・白線回避 |
| 夜間 | +10% | 視認性低下・渡り直し |
| 子ども/高齢 | ×2 | 休憩込みの安全速度 |
1-3.代替の優先順位(人→路線→車)
- 徒歩→他線→路線バス→相乗り→タクシーの固定順で検討。自家用車は渋滞・駐停車不可で遅れやすく最後の手。
- 受験・面接・診療の時間厳守は待たずに即徒歩→他線へ。家庭内では誰が迎え・誰が在宅切替連絡か役割固定。
事前設計チェック表(印刷用)
| 項目 | 決めごと | 実施 |
|---|---|---|
| 幹線の背骨 | ○○通り→△△通り | □ |
| 並行鉄道 | 私鉄A・JRB・私鉄C | □ |
| 結節点 | ○○駅・バスターミナル | □ |
| 徒歩分 | 自宅→結節点 18分 | □ |
| 予備 | 相乗り合流=駅正面口 | □ |
| 役割 | 迎え=父/連絡=母 | □ |
持ち物ミニ表(上着のポケット運用)
| 位置 | 入れるもの | ねらい |
|---|---|---|
| 胸 | 身分証・IC・少額現金 | すぐ出せる |
| 内ポケット | 小電源・短ケーブル | 充電待ち対策 |
| 外ポケット | 反射・小型ライト・ばんそうこう | 視認と小さな応急 |
2.停止を知ったら:駅で“見る→決める→知らせる”
2-1.見る(掲示・振替・地上口)
- 掲示:運転見合わせ区間・見通し、振替の対象路線、臨時バスの有無を写真で保存。
- 地上口:明るい正面口と背骨の道に直結する階段を選ぶ。狭い裏口は回避。
- 流れ:人が同じ出口に集中していれば隣の出口へ1本ずらしで混雑回避。
2-2.決める(30分砂時計)
- 30分は待つ/60分で切替を原則。混雑・暑さ寒さ・同行者の体調が悪化するなら即切替。
- 受験・面接・診療は待たない。徒歩→他線か路線バスへ即移行。
2-3.知らせる(短文テンプレ)
- 出発:「地下鉄停止。幹線で△△駅へ徒歩→他線。返信不要。」
- 遅延:「+30分見込み。交差点××で合流可。」
- 在宅:「本日在宅へ切替。会議はURLで参加。」
駅での判断テンプレ
| 分 | 行動 | 要点 |
|---|---|---|
| +0 | 掲示と放送 | 区間・見通し・振替 |
| +5 | 地上口選定 | 正面口・背骨方向 |
| +10 | 代替決定 | 徒歩→他線/バス/相乗り |
| +15 | 短文送信 | 合流点・時刻を明示 |
構内の安全ポイント
- 階段は中央の手すり側、エスカレーターは右/左の地域作法に従い歩かない。
- ホーム端の吹きだまりは避け中央寄りで待機。
3.地上ルート設計:幹線で“見える・止まれる・曲がれる”
3-1.徒歩ルート(見通し優先)
- 明るい幹線を直進。長い壁・空き地・細い路地は避ける。横断は信号交差点のみ。
- 橋・坂では風と足元に注意。白線・金属板・タイルは滑りやすい。歩幅を短く、足裏フラットで着地。
- 夜間・荒天は反射・ライトを増やし、黒系の服は白いタオルを外側へ。
徒歩の所要・安全早見表
| 距離 | 大人 | 子ども・高齢 | 荒天加算 |
|---|---|---|---|
| 1km | 12〜15分 | 20〜25分 | +2〜5分 |
| 2km | 25〜30分 | 40〜50分 | +5〜10分 |
| 3km | 40〜50分 | 60〜75分 | +8〜15分 |
3-2.路線バス(停留所の選び方)
- 大通りの停留所を使う。駅前の最混雑停留所は一本ずらすと乗れる確率が上がる。
- 系統表を写真に撮り、本数/所要/循環の方向を把握。終点手前で降りると降車混雑を避けやすい。
- 乗車は後ろ・降車は前など地域の作法に従い、運賃支払い方式(先払い/後払い)も確認。
3-3.相乗り(固定ルールで安全)
- 同方向2〜3人、正面口→幹線のみの固定ルート。裏道走行は不可と先に合意。
- 降車は明るい交差点手前。現金割り勘、領収書保管、運転席の安全運転最優先。
- 迎えの家族車も停車は幹線の乗降所。路上急停車はしない。
地上ルート早見表
| 手段 | 強み | 弱み | 向く距離 | 追加メモ |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩 | 確実・費用ゼロ | 体力・天候 | 1〜3km | 最短ではなく最明を選ぶ |
| 路線バス | 本数次第で速い | 遅延・満員 | 2〜8km | 一本ずらしで乗れる |
| 相乗り | 体力温存 | 相手選び | 3〜10km | 幹線固定・領収書 |
| タクシー | 直行で速い | 費用高 | どこでも | 正面口で乗降 |
4.結節点での乗継:並ぶ順より“決める順”
4-1.乗継の型(歩く→待つ→切替)
- 歩く:結節点まで**最短“直線”**を歩く。脇道の近道は避ける。
- 待つ:30分の砂時計で様子見。風避け・屋根・照明の三点を満たす位置で待機。
- 切替:別路線/バス/相乗り/在宅へ。時間厳守の用件は即切替が原則。
4-2.並び方と隊列(転倒・混雑対策)
- 列幅は人1.5人分、蛇行禁止。足元の雪だまり・金属板・白線を避ける。
- 先頭は譲り合い、後方は詰め過ぎない。子ども・高齢者は壁側で待機。
- 係員の指示語(停止・進行)を復唱して全体に共有。
4-3.費用と時間の目安(判断の材料)
| 選択肢 | 追加時間 | 追加費用 | 向く場面 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩→他線 | 10〜30分 | 0〜数百円 | 並行線あり | 都市部に有効 |
| 路線バス | 10〜40分 | 200〜400円 | 本数次第 | 系統の向きを要確認 |
| 相乗り | 5〜20分 | 数百〜数千円/人 | 体力温存 | 幹線限定・領収書 |
| 在宅切替 | 0分 | 0円 | 会議/作業 | 早い宣言が混乱を防ぐ |
合流テンプレ(家族・同僚)
| 文例 | 使う場面 |
|---|---|
| 「正面口で合流、10分待つ」 | 駅前で集合 |
| 「交差点××の北西角へ移動」 | 人の流れが詰まった時 |
| 「私は窓口、Aは掲示、Bは列整え」 | 役割分担 |
5.在宅・中止の判断:動かない勇気も“計画のうち”
5-1.在宅切替の基準
- 停止見通しが不明で60分超の遅れ。
- 猛暑・寒波・大雨・強風など健康リスクが高い。
- 会議・報告・学習など遠隔対応が可能。
- 受験・診療など時間厳守は前日移動/早着か即切替。
5-2.短文テンプレ(読み上げ用)
- 上司・学校:「地下鉄停止で60分超見込み。在宅へ切替、10時接続。提出物は共有に保存。」
- 家族:「地上ルートへ変更。○○通りで△△駅へ。到着は再送。迎え不要。」
- 取引先:「移動障害のため開始を+30分、または在宅接続へ切替可能。ご希望を返信ください。」
5-3.帰宅後の“次回に生かす”記録
- 歩けた距離/時間、混んだ停留所、役立った迂回、使えた合流場所を地図へ追記。次回は迷いゼロへ。
在宅・中止の判断表
| 指標 | しきい値 | 対応 |
|---|---|---|
| 復旧見通し | 不明〜60分超 | 在宅宣言 |
| 体感温度 | とても暑い/寒い | 室内待機→在宅 |
| 同行者 | 子ども/高齢者 | 即切替 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.地下鉄復旧の見通しが出ない。待つべき?
A. 30分で様子見→60分で切替が目安。時間厳守の用件は即切替。
Q2.路線バスのどの停留所から乗れば良い?
A. 駅前の最混雑停留所を避け、一本ずらした停留所を選ぶと乗れる確率が上がる。
Q3.相乗りは安全?
A. 同方向2〜3人、正面口→幹線のみ、明るい場所で降車、現金割り勘の固定ルールで運用。
Q4.子ども・高齢者が一緒。徒歩は不安。
A. 歩道の広い幹線を選び、交差点ごとに休憩。相乗り・在宅も早めに検討。
Q5.雨や雪の日は?
A. 歩幅を短く、足裏フラット。白線・金属板・斜路を避け、明るい大通りへ。
Q6.どの程度の遅延で在宅を考える?
A. 60分超が一つの目安。健康・安全を優先し、短文で早めに宣言。
Q7.通信が混み合って連絡できない。
A. SMS→音声→公衆通信の順で試す。短文に統一し、位置共有は15分限定。
Q8.夜間の徒歩が不安。
A. 反射・ライトを増やし、明るい背骨の道に寄せる。正面口→交番→店の前を合流順に。
Q9.受験や面接で遅れられない。
A. 前日移動または開場90分前到着を基本に。待たずに地上へ。
Q10.乳幼児連れ。
A. 段差の少ない道を選び、交差点ごとに休憩。抱っこ紐で両手を空ける。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 結節点:路線やバスの乗り換えの中心(大駅・役所・バスターミナル)。
- 並行鉄道:地下鉄と同じ方向に走る地上の線。
- 砂時計(30分ルール):30分待つ→60分で切替という判断の型。
- 相乗り:同じ方向の複数人で一台に乗ること。降車は明るい場所で。
- 背骨ルート:幹線道路をつないだ直線の徒歩道。迷いにくい基準線。
- 臨時バス:地下鉄停止時に走る代わりのバス。停留所と本数を掲示で確認。
- 地上口:地下駅から地上へ出る出入口。正面口は人が多く明るい。
まとめ:地上の“背骨”を持てば、止まっても動ける
幹線の背骨・並行鉄道・結節点の三層地図を用意し、30分砂時計で判断、短文テンプレで共有。これだけで、地下鉄停止でも迷わず切替できます。並ぶ順より決める順。 地上の骨格を先に作り、毎日の移動を止まらない計画にしましょう。