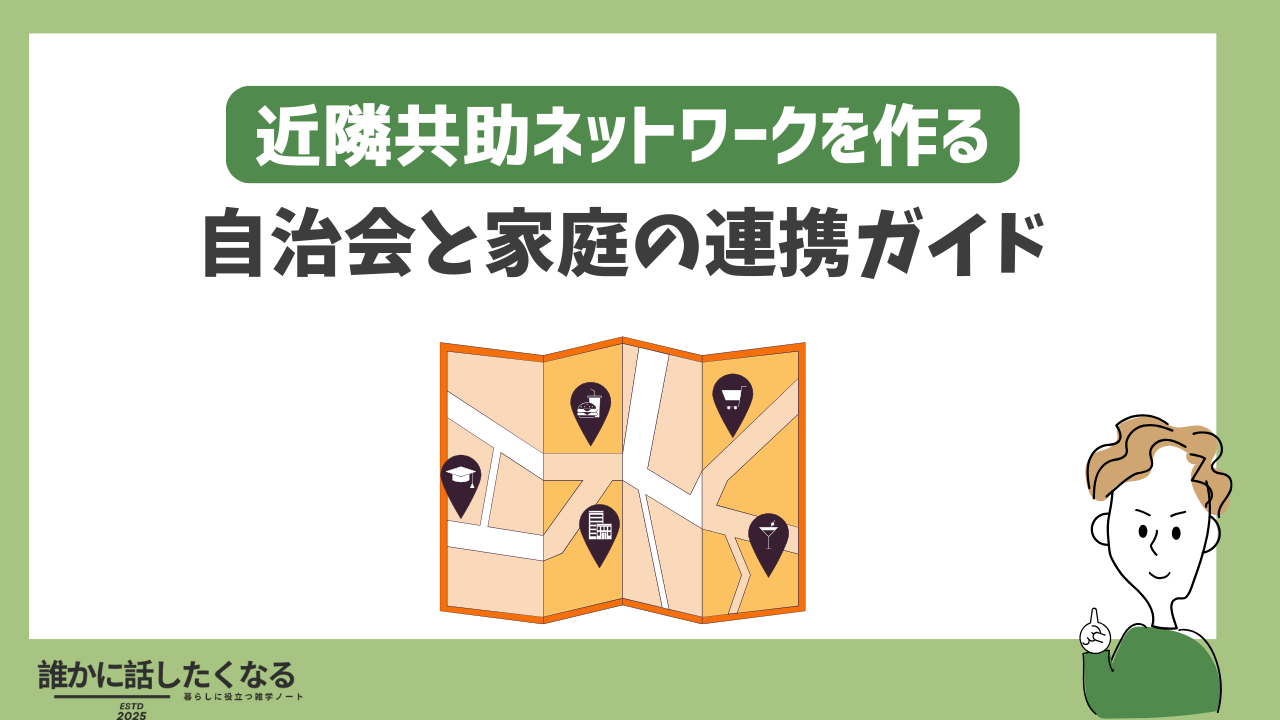「助け合いはしたいけれど、何から始めればいい?」——答えは顔と情報と動線をそろえることです。本記事は、自治会・管理組合・町内会と各家庭が今日から着手できる具体手順を、名簿作り→連絡網→拠点→物資→訓練→見直しの順で徹底解説します。
役員経験がなくても迷わないよう、テンプレート・チェックリスト・表を多数掲載。停電・断水・通信障害・広域災害のいずれでも機能する**“軽くて壊れにくい共助の仕組み”**を一緒に組み上げましょう。
共助ネットワークの骨格設計:顔・情報・動線をそろえる
顔が見える仕組み:世帯カードと戸別掲示
世帯カードに「世帯人数・年齢層・支援が必要な人・連絡手段・在宅の傾向・ペットの有無」を記入し、玄関内側に保管。集合掲示板には班長名・拠点地図・集合時の合言葉を常時掲示し、初動で迷わない土台を作ります。顔合わせ日を**季節ごと(年4回)**に設け、初めての人に声をかける当番を回します。
情報が流れる仕組み:四重連絡網+紙の予備
電話/SMS/無線/掲示の四重が基本。停電時は有線電話・電池式ラジオ・ホイッスルを併用。オンライン名簿は紙のバックアップを必ず作成し、施錠保管。連絡訓練日を月1回設定して応答率・所要時間を記録し、弱点を見える化します。
動線が止まらない仕組み:集合・搬送・避難の三段導線
一次集合(近所の公園等)→物資拠点→広域避難所の三段導線を地図化。高齢世帯・車いす世帯にはサポート担当を平時から割り当て、搬送用の台車・そり・キャスター板を拠点に常設します。道が狭い区画は別ルートを事前に決め、看板と矢印で示します。
ネットワークの骨格(早見表)
| 要素 | 仕組み | 担当 | 点検頻度 |
|---|---|---|---|
| 顔 | 世帯カード・班名簿・季節の顔合わせ | 各戸・班長 | 半年ごと(名簿)/年4回(顔合わせ) |
| 情報 | 電話SMS無線掲示の四重+紙の予備 | 情報係 | 月1訓練 |
| 動線 | 三段導線(一次→拠点→避難所)・別ルート | 動線係 | 半年ごと |
平時→発災→復旧の時系列
| 段階 | すること | 合言葉/合図 | 完了の目安 |
|---|---|---|---|
| 平時 | 名簿更新・道具整備・30分訓練 | 「三段導線で動く」 | 月次記録が埋まる |
| 発災直後 | 安否確認→一次集合→情報収集 | 笛1短=集合 | 30分以内に点呼 |
| 継続期 | 物資配布・見守り・衛生管理 | 笛2短=物資搬送 | 3時間ごとに記録 |
| 復旧期 | 片付け・仮修理・振り返り | 笛1長=集合解除 | 1週間以内に報告会 |
名簿と連絡網:情報の“質”を上げる書き方と回し方
世帯カードの必須項目と配布テンプレ
- 氏名(ふりがな)・人数・年代
- 持病・アレルギー・常用薬(本人同意)
- 支援区分(杖・車いす・乳幼児・妊娠・耳や目の不自由など)
- 連絡手段(固定・携帯・SMS・無線)
- 避難先候補(親族宅・職場)
- ペット(種類・頭数・避難時の対応)
- 在宅時間の傾向(平日昼・夜・休日など)
連絡網の作り分け:平時・発災直後・長期
平時は連絡板(回覧)+グループチャットで共有、発災直後は電話一斉→SMSに切替、長期は掲示板+定時巡回。**“受信したらOK返信”**を徹底し、未応答の再送タイム(例:10分後)を定めます。聴こえにくい人には紙メモを用意します。
個人情報の取り扱い:開示レベルを段階化
名簿は班長版(詳細)と配布版(簡略)に段階化。外部流出防止に持ち出し禁止・撮影禁止を明記。保管責任者・施錠場所をはっきりさせ、更新ログと閲覧記録を残します。同意の取り方の文面もテンプレ化して摩擦を減らします。
連絡訓練の記録フォーマット(例)
| 実施日 | 対象班 | 送信手段 | 応答率 | 平均応答秒 | 再送回数 | 課題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 第3班 | SMS | 82% | 96 | 1 | 既読は付くが返信遅い |
| 6/14 | 第3班 | 電話+SMS | 94% | 52 | 0 | 高齢者宅は固定回線が有効 |
玄関掲示用・短文メモの型(停電時)
「場所:○丁目○班/状況:無事・けがなし/向かう先:一次集合/時刻:○:○○」
物資・拠点・役割分担:止まらない運営の段取り
拠点の三種:屋根・水・電気の確保
- 物資倉庫型:簡易トイレ・水・毛布・ライト・発電機。
- 給配水型:給水車の受け口、手押しポンプ、雨水タンク。
- 情報中継型:無線・メガホン・掲示板・ソーラーパネル。
拠点は日陰・風通しと段差の少ない動線を優先し、夜間照明と鍵の保管を明確にします。
役割分担:機能で割ると続く
情報・動線・物資・衛生・見守り・記録・会計に区分し、1機能=最少3名(主・副・予備)。在宅率や体力に合わせて無理のない配置へ。休む係も先に決め、交代表を作って燃え尽きを防ぎます。
物資の“回る台帳”:出し入れと期限管理
台帳に入庫日・数量・使用期限・次補充日・保管場所を記入。配布時の受領サインと残量写真で誤差を抑えます。共同購入(乾電池・簡易食)は班単位で回し、**期限前の“消費会”**でムダをなくします。
推奨備蓄(1班20世帯を想定)
| 品目 | 目安数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 飲料水(2L) | 120本 | 1人1日3L×2日分目安 |
| アルファ米 | 120食 | 味を分散 |
| 簡易トイレ | 400回分 | 消臭剤・凝固剤付 |
| 乾電池(単3) | 200本 | 共通規格を決める |
| LEDランタン | 20台 | 調光機能付き |
| 簡易担架・台車 | 各2 | 折りたたみ可 |
| ブルーシート・養生テープ | 各10 | 雨漏り・仕切り |
| 使い捨て手袋・マスク | 500枚・200枚 | 衛生管理 |
| カセットこんろ・燃料 | 4台・48本 | 炊き出し・温食 |
| 乳幼児・高齢向け食 | 適量 | 粥・やわらか食 |
拠点運営の交代表(例)
| 時間帯 | 情報 | 物資 | 衛生 | 見守り | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–10時 | A主/B副 | C主/D副 | E主/F副 | G主/H副 | I主/J副 |
| 10–14時 | B主/A予 | D主/C副 | F主/E副 | H主/G副 | J主/I副 |
訓練と当日運用:短く・軽く・繰り返す
30分訓練の型:集合→点呼→連絡→搬送→ふり返り
1)集合:一次集合で名札配布、役割を配る。
2)点呼:世帯カードで在宅確認。
3)連絡:一斉送信→返信確認の時間を計測。
4)搬送:台車で物資を拠点へ運ぶ。
5)ふり返り:良かった点×1、改善点×1を各自口頭で。短く回数を増やすのが続くコツです。
当日の運用ルール:前倒しで安全側に倒す
- 判断は安全側:迷ったら早めの集合。
- 情報は簡潔に:場所→状況→必要な支援→氏名の順で伝える。
- 役割は重ねない:無線と搬送を同じ人にしない。
- 疲労の見える化:1時間ごとに交代、水分と塩分を配布。
- 誘導表示:矢印・色テープ・大文字で迷いをゼロに。
記録と共有:失敗を整備に変える
時系列メモ(いつ・誰が・何を)と写真を残し、次回の備品購入に直結。恥ずかしい失敗ほど価値が高い。**“失敗展”**を掲示板で共有すると、学びが早く広がります。
訓練の採点表(配布用)
| 項目 | S | A | B | 改善メモ |
|---|---|---|---|---|
| 集合の速さ | ||||
| 連絡の通り | ||||
| 物資搬送 | ||||
| けが・危険 | ||||
| 表示・誘導 |
家庭の準備と日常運用:小さな習慣が地域を強くする
家庭の“共助ポーチ”:渡して助かる中身
身分証コピー・連絡先・常備薬・小銭と千円札・小型ライト・笛を家族人数分。名札用カードと油性ペンを入れておくと、集合時の点呼が速くなります。
生活の中に“共助の種”をまく
玄関に声かけゾーン(高齢者宅の前でひと声)、ゴミ出しは見守り時間、町内清掃で通路幅を確保。犬の散歩ルートは掲示板の見回りを兼ね、破れやすい掲示物は養生テープで補強します。
要支援世帯への“過度でない手助け”
できること表(ゴミ回収・買い物同行・電球交換など)を配布し、頼みやすい入口を用意。“無理をしない/断ってよい”を明記して、依存と反発の両方を避けます。見守りの時間帯は朝・昼・夕の3本立てが効率的。
家庭の共助チェックリスト
| 項目 | できた | 次回まで |
|---|---|---|
| 共助ポーチの作成 | ||
| 世帯カードの更新 | ||
| 近所の声かけ習慣 | ||
| 掲示板の確認 | ||
| 非常時の短文メモ用紙の常備 |
防犯・風評・トラブルの予防:場を守る共通ルール
防犯の基本:出入口・持ち出し・夜間
拠点の出入口は2か所を確保し、名札のない人の立入りは控える。物資は出庫表で管理し、夜間は鍵+見回り。子どもだけの来場には必ず保護者呼び出しを行います。
風評対策:情報の一本化
掲示板と班長連絡を一本化。未確認の話は**「未確認」と明記**し、確認に動く人を指定。うわさ話を広げない姿勢を共有します。
意見の違いの扱い方
会議は時間制限と発言回数の公平化を導入。反対意見は要点を紙に集約し、次回までに候補案を持ち寄る方式にすると、対立が熱くなりにくい。
Q&A(よくある疑問)
Q1. 人が集まらない。どうすれば?
A. 短時間・明確な役割・成果の見える化が鍵。30分訓練にして採点表を掲示、次回に反映する購入を約束すると参加率が上がります。
Q2. 個人情報が心配。名簿に何を書けば?
A. 段階化で解決。配布版は最低限(人数・連絡手段)、班長版は詳細。保管場所と責任者を明確に。
Q3. 役員の負担が重い。
A. 機能別3人制(主・副・予備)に再編し、休む係を設ける。共同購入の割引など小さな報酬も効果的。
Q4. 無線や発電機は高くて買えない。
A. 貸し出し制度・共同購入・リースを検討。小型ソーラー+モバイル電源なら段階的に導入できます。
Q5. ペットが多い地域。避難所で困らない?
A. ペットの区画・消臭・ケージの数を事前に把握。リードと名札を共助ポーチに入れておきます。
Q6. 日本語が得意でない人への伝え方は?
A. 絵・色・矢印を使った掲示、多言語の定型文カードを配布。大事な言葉は短く大きく書きます。
Q7. 高齢者の夜間トイレ移動が心配。
A. 簡易トイレの近設・足元灯・見守り時間帯を設定し、段差解消マットで転倒を防ぎます。
用語辞典(やさしい言い換え)
世帯カード:各家庭の人数・連絡・支援の要否をまとめた紙。
一次集合:近所で最初に集まる場所。点呼や情報共有をする。
水平避難:階段を使わず同じ階の安全な場所へ移動すること。
共同購入:班や自治会でまとめて買って費用を下げること。
三段導線:一次集合→物資拠点→広域避難所の流れで動く考え方。
応答率:連絡に返事が来た割合。
出庫表:物資を誰に何個渡したかの記録。
まとめ:軽く、壊れにくく、続く仕組みへ
共助は道具の量ではなく、顔・情報・動線の単純で強い骨格が命です。世帯カード→四重連絡→三段導線の三本柱に、役割分担と30分訓練を重ねれば、地域は静かに強くなります。まずは班の名簿更新と30分訓練の告知から始めましょう。今日の一歩が、明日の安心になります。