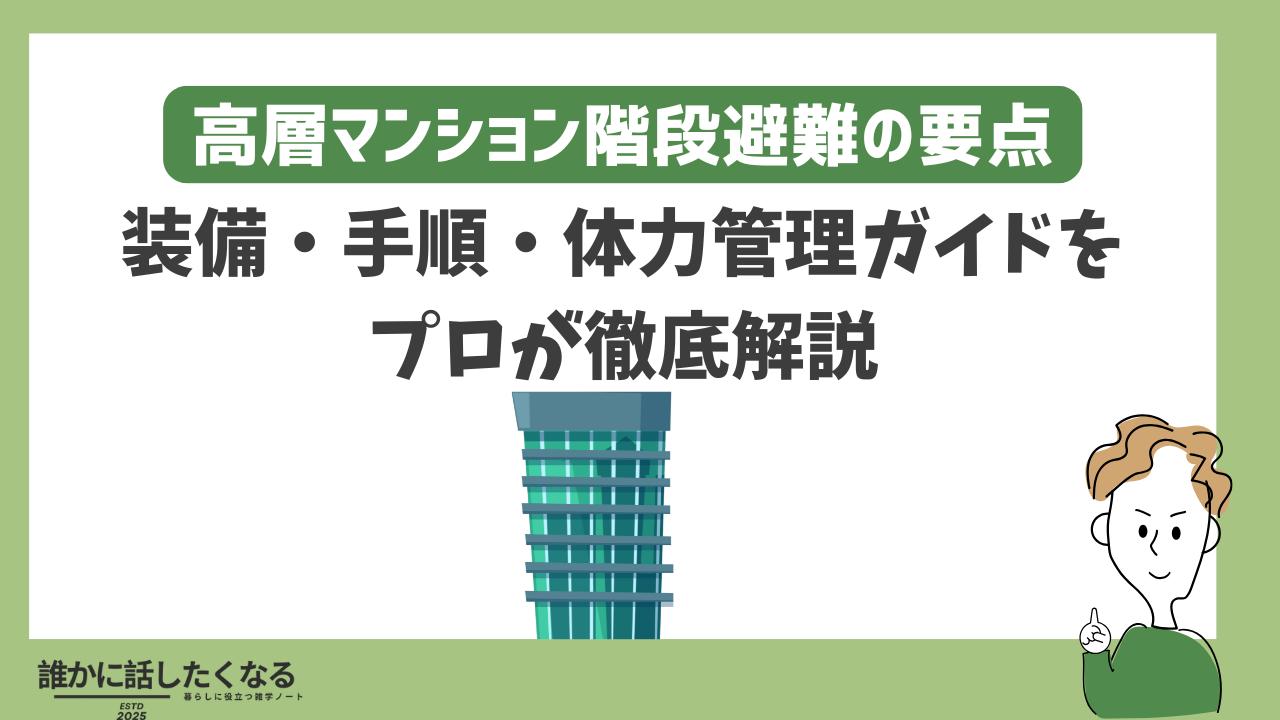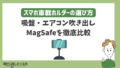エレベーター停止、停電で暗闇、階段は混雑――高層階の避難は準備と段取りで安全度が大きく変わります。本記事は、装備を軽くして両手を空ける工夫、降下前の安全確認、階段での歩き方と隊列、脱水・足つりの予防、地上到達後の行動までをまとめました。各章に表・チェックリスト・時間配分の目安を用意し、今日から家族で練習→見直し→定着できる実用ガイドです。
1.結論と全体像:高層階避難の“5本柱”
1-1.5本柱の設計図
- 軽く・両手を空ける装備(背負う/装着):片手持ちは転倒の原因。背負う・腰に付ける・首から下げるで手ぶらに。
- 降下前の安全確認(火気・煙・ガラス・余震):玄関ドアの温度・におい・音を確かめ、危険方向を避ける。
- 階段の隊列と声かけ(右寄り・手すり・一段一呼吸):手すり側を確保し、**短い合図(OK/止/待)**で伝える。
- 途中の補給と温度管理(水・塩・汗冷え対策):30分で一口の水+塩、汗はタオルで拭き上着で調整。
- 地上到達後の点呼・離れない・情報更新:集合→点呼→公式情報確認の順で判断ミスを減らす。
高層階避難の優先順位表
| 項目 | 優先 | 目標 | 具体策 |
|---|---|---|---|
| 両手を空ける | 最優先 | 背負う/装着で手ぶら | リュック、腰ポーチ、ネックストラップ |
| 手すり確保 | 最優先 | 常に片手は手すり | 右寄り通行、左手で手すり固定 |
| 水と塩 | 高 | 30分ごとに一口+塩 | 500ml水+塩飴、口を湿らす量で可 |
| 隊列維持 | 高 | 先行1・中核2・殿1 | 先行が踊り場で確認・合図 |
1-2.避難の判断:在宅・待機・降下の境目
- 煙・炎・破損が近い→即時降下。防火扉の向こうが熱い/煙のにおいが強いなら別経路。
- 停電・断水のみ→情報収集→準備→段階的降下。夜間は明かり確保後に移動。
- 階段室に薄い煙→濡れタオルで口鼻を覆い、低姿勢。上昇する煙を意識して下層に早く移る。
降下判断のめやす
| 状況 | すぐ降下 | 準備して降下 | その場待機 |
|---|---|---|---|
| 炎・強い煙 | ● | ||
| 薄い煙・におい | ● | ||
| 停電のみ | ● | ||
| 大雨・暴風 | ●(弱まるのを待つ) |
1-3.家族編成と役割分担
- 先行(偵察):1名。階段の破損・混雑・煙を確認し、踊り場で合図。
- 中核(子/高齢の介助):2名。歩幅と呼吸を合わせ、水・塩の時間管理を担当。
- 殿(しんがり):1名。後方の安全確認とドアの閉鎖、落とし物回収を担当。
役割と持ち物の割り振り
| 役割 | 主な仕事 | 手に持つ物 | 背負う物 |
|---|---|---|---|
| 先行 | 偵察・合図 | なし(手ぶら) | 軽い非常袋 |
| 中核 | 介助・ペース管理 | なし(手ぶら) | 水・塩・救急 |
| 殿 | 後方確認・ドア | なし(手ぶら) | 充電・タオル・予備手袋 |
2.装備の最適化:軽く・両手を空け、汗で冷えない
2-1.身につける装備(両手を空ける)
- ヘッドライト:足元と手すりを照らす。予備乾電池は同じ袋に。
- 軍手/厚手手袋:手すりのささくれ・割れ物対策。利き手を手すり側に。
- マスク/タオル:煙・粉じん対策。濡れタオルは口鼻に当てる。
- 薄手の上着:汗で体が冷えるのを防ぐ。脱ぎ着しやすい前開きが良い。
2-2.背負う装備(最小限の非常袋)
- 水:500ml×人数分。口を湿らす量で良い。凍結ペットボトルは重さ増に注意。
- 塩・飴:足つり予防。塩飴2〜3粒を小袋に。
- 救急:絆創膏、テーピング、鎮痛解熱、三角巾。踵用保護パッドがあると靴ずれ防止。
- 携帯充電:軽量バッテリー+ケーブル。節電のため機内モードも活用。
2-3.足元と衣類のポイント
- 滑りにくい靴:紐靴を甲の上で二重結び。サンダル不可。
- 長ズボン:膝を守る。裾は引きずらない長さに。
- 靴下は厚手:汗を吸い、靴ずれを減らす。
装備ミニマム表(身につける/背負う)
| 区分 | 品目 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 身につける | ヘッドライト/手袋/タオル | 人数分 | 両手を空けるのが原則 |
| 背負う | 水/塩/救急/充電 | 人数×最小 | 重い物は背中側下部へ |
| 服装 | 滑りにくい靴・長ズボン | 即出発可 | 上着で温度調整 |
個人ごとの目安重量
| 体格 | 非常袋重量のめやす | 備考 |
|---|---|---|
| 小柄/高齢 | 2〜3kg | 水は分担、最小限 |
| 標準 | 3〜4kg | 水500ml+救急 |
| 体力あり | 4〜5kg | 予備電池・タオル増 |
3.階段降下の手順:安全・一定・途中で立ち止まらない
3-1.出発前チェック(30秒)
- ドアの熱/におい:手の甲でそっと触れて熱さを確認。熱い→別経路。
- ガス元・ブレーカー:可能なら閉める/落とす。
- 鍵・連絡手段:首から/ポケットに固定。落下防止。
玄関まわりチェック表
| 項目 | 確認 | 備考 |
|---|---|---|
| ドアの熱・煙 | 触るのは手の甲 | |
| ガス・電気 | 可能な範囲で処置 | |
| 鍵・携帯 | 首から/ポケット固定 |
3-2.階段での歩き方と隊列
- 右寄り通行・左手で手すり。人とすれ違う時は止まらず歩幅を小さく。
- 一段一呼吸:段ごとに呼吸を合わせ、会話が続く強度を保つ。
- 合図は短く:「OK(進む)/止(止まる)/待(待つ)」。
階段の種類別注意点
| 種類 | 注意 | 対策 |
|---|---|---|
| 屋内階段 | 照度が低い | ヘッドライトで手すりと足元 |
| 屋外非常階段 | 風雨・滑り | 歩幅小さく、手すり強く握る |
| 螺旋階段 | 目が回りやすい | 視線を2〜3段先に固定 |
3-3.途中階での休憩・合流・時間の目安
- 休憩は踊り場で30〜60秒。水一口+塩で足つり予防。
- 合流は踊り場外側に寄せ、通行をふさがない。
降下時間のめやす(一定ペース)
| 出発階 | 目安分/10階 | 参考 |
|---|---|---|
| 子/高齢含む | 18〜25分 | 休憩2〜3回 |
| 大人中心 | 12〜18分 | 休憩1〜2回 |
階段での禁止事項と代替行動
| NG | 危険 | 代替 |
|---|---|---|
| 手すりを離す | 転倒・接触 | 片手は必ず手すり |
| 大声で叫ぶ | 混乱・転倒 | 短い合図(OK/止/待) |
| 荷物片手持ち | 体幹が崩れる | 背負う・装着 |
4.体力・脱水・足つり管理:30分で一口、歩幅は小さく
4-1.疲労のサインと早期対応
- 息が上がる→歩幅を小さく、一段一呼吸に切り替え。
- ふくらはぎが張る→塩+水、つま先上げで筋を戻す。
- 汗で冷える→上着を追加、濡れタオルは外す。
4-2.脱水と熱の管理
- 基本は30分ごとに一口の水+塩。子ども・高齢者は20分ごとに短休憩。
- 汗冷えは体温低下→足つりのもと。乾いたシャツを1枚忍ばせると安心。
- 行動食はようかん/クラッカー/塩飴など一口で食べられる物。
4-3.足の痛み・靴ずれ対策
- テーピングで足指保護。靴紐は甲の上で二重結び。
- 踵が擦れたら早めに絆創膏。痛みは上へ広がる前に対処。
- 膝が不安な人はゆっくり大股ではなく小股で段差を刻む。
体力管理の目安表
| 現象 | 兆候 | その場の対処 |
|---|---|---|
| 息切れ | 会話が続かない | 歩幅小さく・一段一呼吸 |
| 足つり | ピクピクする | 塩+水・つま先上下運動 |
| 冷え | 鳥肌・震え | 上着追加・汗拭き |
| 低血糖 | ふらつき | ようかん一口・水少量 |
5.地上到達後:点呼・離れない・情報更新
5-1.点呼と合流ポイント
- 集合位置は建物から離れた広い場所。落下物の射程を外す。
- 人数確認は名簿+口頭の二重。持ち物紛失もここで確認。
5-2.情報の取り方と戻る判断
- 公式情報(行政・管理組合)を優先。うわさ話に流されない。
- 余震・火災・煙が続くなら戻らない。エレベーター再開までは階段利用。
- 再集合場所と次の移動先を紙に書き合図にして共有。
5-3.再入室の注意と片付けの順番
- ガラス片に注意し靴は脱がない。手袋着用で作業。
- 水・電気・ガスの安全を再確認。感電・漏電に注意。
- 上から下へ片付け、窓・割れ物は最後。子どもは別室待機。
地上での行動チェックリスト
| 項目 | 実施 | 備考 |
|---|---|---|
| 集合地点に移動 | 落下物の射程外 | |
| 点呼(名簿+口頭) | 二重確認 | |
| 情報収集(公式) | 再入室の判断 | |
| 次の集合・連絡方法 | 紙で共有/撮影 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.何階から下り始めるべき?
A. 煙・火・破損が近いなら即時。それ以外は情報を取り、体力・混雑に応じて段階的に。夜間は明かり確保後に移動。
Q2.小さな子どもや高齢者がいる
A. 先行1・中核2・殿1で挟み、歩幅を小さく。20分ごと短休憩と水+塩を徹底。抱っこは胸側で安定。
Q3.暗い階段が怖い
A. ヘッドライトで足元と手すりを照らし、短い合図(OK/止/待)で落ち着いて伝達。声は低く短く。
Q4.荷物はどれを持つ?
A. 背負う最小限(水・塩・救急・充電)に絞り、両手を空けるのが原則。重い水は分担する。
Q5.途中で足がつったら?
A. 踊り場で30〜60秒休み、塩+水、つま先上下運動。再開は歩幅小さく、一段一呼吸へ。
Q6.ベビーカーや車いすは?
A. 階段では使用せず、人の手で介助。先行が段差確認→中核で肩・腰を支える→殿が後方支援の順でゆっくり降下。
Q7.長時間の停電で上階に戻る時は?
A. 明るい時間帯に少人数で。水は最小だけ持ち、両手を空ける。戻りは上がるほど休憩多めに。
用語辞典(やさしい解説)
- 踊り場:階段途中の平らな部分。休憩・合流に使う。
- しんがり(殿):列の最後尾で後方確認を担う人。
- 汗冷え:汗が冷えて体温が下がること。上着の脱ぎ着で調整。
- 一段一呼吸:段ごとに呼吸を合わせる歩き方。ペース維持に有効。
- 防火扉:炎や煙の広がりを遅らせる扉。開閉は最小限に。
- 非常階段:避難用の階段。手すり側優先で通行。
まとめ
高層階の階段避難は、手ぶら化・手すり・小さな歩幅・こまめな水と塩が基本です。隊列(先行1・中核2・殿1)で互いを見守り、踊り場で短休憩を挟み一定のリズムで降下しましょう。
地上に着いたら集合→点呼→情報更新→次の集合合図を共有。今日、ヘッドライトと手袋を玄関の定位置に置き、**家族で合図(OK/止/待)**を決めておく――それが最初の一歩です。