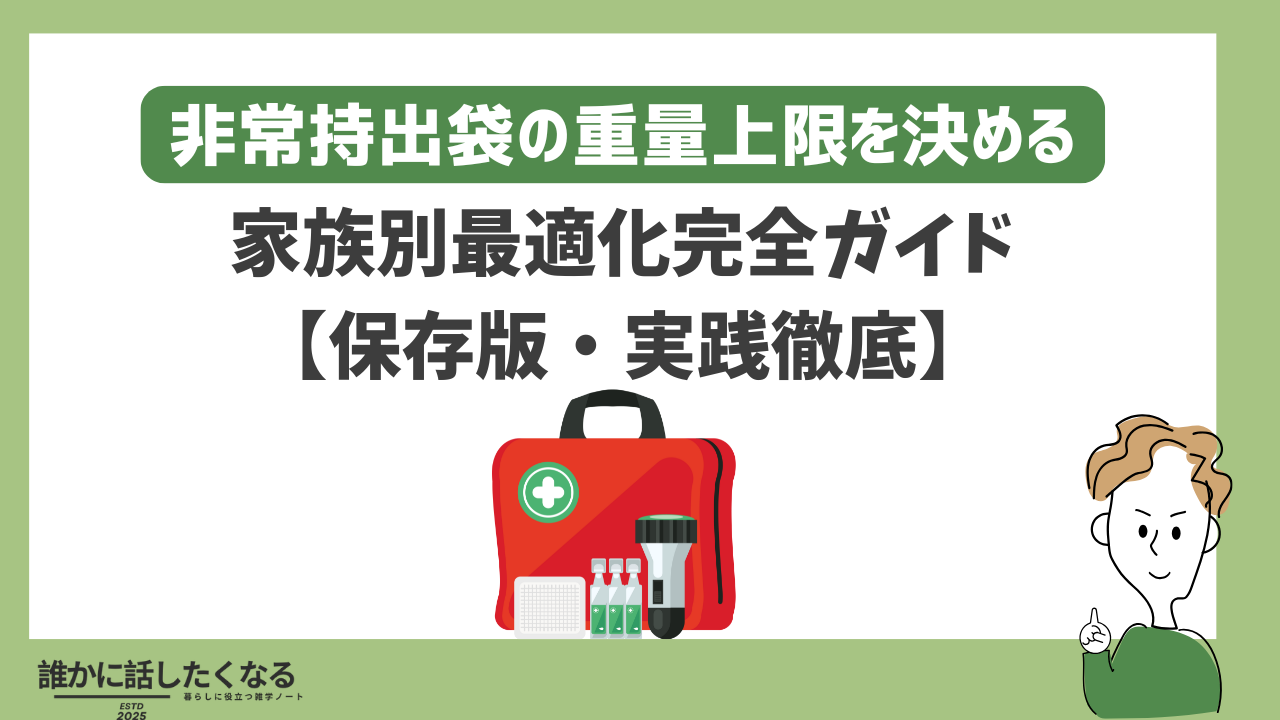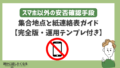重量上限は「体格×距離×時間」で決まる
基本の目安(体重比の考え方)
非常持出袋の上限は、まず体重比で考えると判断が速い。無理のない重さの目安は、
- 体重の10%=長時間歩ける日常上限
- 体重の15%=短時間のがんばり上限(1〜2時間)
- 体重の20%超=緊急時の一時的限界(推奨せず)
これを出発点にし、年齢・体力・既往症・荷のかさで下げていく。迷ったら10%以内に収めると安全側に倒せる。
行動条件で補正する(距離・段差・背負時間)
同じ重さでも、歩く距離と段差、背負う時間で辛さは変わる。おおまかな補正の例:
- 5km以上歩く見込み → 上限−2%
- 階段が多い・上り坂が多い → 上限−2〜3%
- 30℃超の暑さ・0℃近い寒さ → 上限−2%(水・防寒が増えるため)
複数当てはまるときは合算して下げる。安全第一で設計する。
気温・地形と水の重さ
水は1L=約1kg。夏場は1人あたり1〜2L/日必要になる。移動が長いときは、給水地点で補給する前提に切り替え、初期携行は0.5〜1Lに抑え、浄水手段(煮沸・薬剤・ろ過)を加えると重量を削れる。乾きやすい人は塩分補給を少量持つと水の消費が抑えられる。
「数値で決める」簡易計算法
1)体重×10%=基準重量。
2)距離・段差・気温の補正を引く(合計2〜7%)。
3)最終上限=基準重量−補正。
4)装備総重量が最終上限を超えたら削減、8割以内に収めるのが理想。
体重別・上限のめやす(計算の早見表)
| 体重 | 基準(10%) | がんばり上限(15%) | 推奨運用(8割) |
|---|---|---|---|
| 40kg | 4.0kg | 6.0kg | 3.2kg |
| 50kg | 5.0kg | 7.5kg | 4.0kg |
| 60kg | 6.0kg | 9.0kg | 4.8kg |
| 70kg | 7.0kg | 10.5kg | 5.6kg |
| 80kg | 8.0kg | 12.0kg | 6.4kg |
家族別の最適重量と中身(モデル別の実例)
大人(18〜64歳)の目安
- 体重60kg→基準6.0kg。都会で5km歩行+階段多めなら4.5〜5.0kgに調整。
- 優先:水0.5〜1L、保存食(1日分)、雨具、保温具、救急、小型灯り、充電、貴重品。
- 余裕があれば:簡易トイレ、衛生用品、薄手のシート。
- 落とし穴:着替えを詰め込むと一気に重くなる。重ね着で代替し、下着1組を圧縮袋で。
高齢者(65歳〜)の目安
- 体重50kg→基準5.0kgだが、3.0〜4.0kgを上限にする。
- 優先:服薬7日、名簿・連絡先、杖先ゴム予備、貼る保温具、紙パンツ。
- バッグは軽いフレームなし、胸・腰ベルトで安定させる。
- 注意:水は小分けで左右に配置。片側偏りは転倒のもと。
小学生・中高生の目安
- 体重30kg(小中)→基準3.0kg、実際は2.0〜2.5kg。
- 優先:水350〜500ml、非常食1食、ポンチョ、笛、ライト、連絡札。
- 反射材と色分けで取り違い防止。
- 置き備え連動:学校のロッカーに上着・水少量を置き、持出袋は軽さを最優先に。
乳幼児同伴者(保護者の加重)
- 抱っこ・ベビーカー併用で親の上限をさらに−2kg。
- 優先:ミルク・おむつ・おしりふき・哺乳びん・熱源(固形燃料)。
- 抱っこひも+ヒップシートで体幹に近づけて負担軽減。
- 工夫:おむつは1枚ずつ圧縮、哺乳びんは軽量1本+予備乳首に集約。
妊娠中・持病がある人
- 上限は**体重の5〜8%**を目安。
- 優先:母子健康手帳、服薬、診察券、保温、座れるシート。
- 無理をしないを最優先に、搬送・合流計画を平時から共有。
- 補足:においでつらい時期は無香料の衛生用品を選ぶ。
障がいのある人・介助が必要な人
- **移動手段(車いす・杖・歩行器)**に合わせ、背負いより固定を選ぶ。
- 優先:連絡カードに支援の要点、予備の装具、皮膚保護。
- 家族の分担:本人は超軽量の最小セット、重い共同装備は介助者へ。
ペット同伴の加重
- 犬猫は体重×50〜60ml/日の水が目安。初期携行は0.25〜0.5L+携行皿。
- 名札・写真・迷子札と予備リードは必携。
- フードは小袋分包でにおい漏れを防ぐ。
家族構成別・上限早見表
| 区分 | 体重例 | 基準(10%) | 推奨上限(補正後) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 60kg | 6.0kg | 4.5〜5.0kg | 都市部・5km・階段多め |
| 高齢者 | 50kg | 5.0kg | 3.0〜4.0kg | 体調優先でさらに減らす |
| 中高生 | 45kg | 4.5kg | 3.0〜3.5kg | 通学距離で調整 |
| 小学生 | 30kg | 3.0kg | 2.0〜2.5kg | 水は小容量を分割 |
| 幼児同伴の親 | 60kg | 6.0kg | 3.5〜4.0kg | 乳幼児用品の加重あり |
重さを減らす工夫(三段構えで最小化)
層1:身に着ける(必ず身につくもの)
笛、身分証、少額現金、家の鍵、小型ライト、連絡カード。上着の胸ポケットか首下げに分散。荷物を下ろした場面でも情報と光は失わない。スマホの非常連絡メモは画面固定にして誤操作を防ぐ。
層2:背負う(すぐ必要な最小セット)
水0.5〜1L、主食1日、救急、雨具、保温具、携帯トイレ、充電、薄い敷物。袋を袋のまま入れない(中身だけにして容積を圧縮)。圧縮袋は空気抜きバルブ付きが扱いやすい。
層3:置き備え・分散(家・車・職場)
家・車・職場に同じ考えの小分け箱を置く。家を飛び出す持出袋は1日分に絞り、2〜3日目以降は置き備えを使う前提にすれば大幅に軽くなる。車には水の箱買いを常備し、期限前入替で飲み回す。
共同装備の分担(家族で割る)
一家に1つで足りる装備(大容量充電、工具、鍋、ろ過器など)は家族で分担。子どもは軽い物(笛、手袋、軽食)に限定する。分担表に名前と重量を記入すると、総量が見える化できる。
同等機能をまとめる(重複排除)
「切る・縛る・照らす・熱する・覆う」の機能で数える。同じ機能が3つ以上入っていないかを点検。たとえばカッターナイフ+はさみのどちらかをやめ、小型多機能工具で代替する。紙テープ+麻ひもなど、軽くて多用途の組み合わせを選ぶ。
水と食料の軽量化
食は高密度を選び、水を使わず食べられるものを中心にする。例:ようかん、ナッツ、乾パン、栄養クラッカー、レトルトそのまま。湯が必要な品は小袋で。粉の飲料は水量の計算が必要なため、最少数に抑える。
季節モジュール(夏・冬で入れ替える)
- 夏:日よけ帽子、汗拭き、塩分補給、虫よけ。
- 冬:薄手の重ね着、手袋、首元保温、貼る保温具。
- 通年:薄い雨具と体温維持具。
- 台風期:防水袋と替え靴下を追加。
軽量化のチェック表(抜粋)
| 分類 | 入れすぎ例 | 置換の例 | 目安削減 |
|---|---|---|---|
| 衣類 | 厚手上着×2 | 薄手重ね着+保温具 | −400g |
| 食 | カップ麺多数 | 高密度非常食 | −300g |
| 水 | 2L一括 | 500ml×2+補給手段 | −500g |
| 充電 | 予備多数 | 共有1台+乾電池 | −200g |
パッキングと背負い方・歩行テスト
重心の作り方(下ではなく背中中央)
重い物は背中の高い位置の中央へ。下に寄せると腰を引かれ疲れやすい。ボトルは左右に分散させ、転がらないよう布で巻く。上外側には軽い物を入れ、落下時の危険を減らす。
からだに合わせる三つの調整
1)肩ひも:鎖骨の少し外を通り、指2本入る程度。
2)胸ベルト:呼吸を妨げない位置で軽く固定。
3)腰ベルト:骨盤に乗せ、荷重の半分以上を腰で受ける。歩いて食い込みがないか確認。
4)背面の長さ:背中に沿うよう上端と肩甲骨の位置を合わせる。
60分歩行テスト(家の周りで)
実際に60分歩いて、肩・腰・太もものどこが痛むかをメモ。痛む場所は重心がずれている合図。5分ごとに肩と腰のベルトを微調整し、階段と坂も必ず含める。合格=痛みが出ない・息が上がりすぎない・会話ができる。不合格なら中身を100g単位で減らす。
住宅内の置き位置と退避動線
持出袋は玄関の上がり框の外側、もしくは寝室ドアの外にフックで吊る。倒れやすい家具の直下は避ける。靴・上着・ヘッドライトを同じ場所にまとめ、暗闇でも手で取れる配置にする。非常時の動線をテープで床に矢印表示しておくと家族が迷わない。
カート・ベビーカー・自転車の併用
長距離の搬送は折りたたみカートが有効。ただし段差と階段で動きが止まりやすいので、持ち上げられる重量に収める。ベビーカーは荷物を上に積みすぎない(後方に転ぶ)。自転車は荷崩れ防止のひもを一つ加える。雨天時は荷物を防水袋に入れてから積む。
歩行ペースと休憩のめやす
| 条件 | 歩行ペース | 休憩 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平地・涼しい | 4.5〜5.0km/h | 50分歩+10分休 | 会話できるペース |
| 坂・階段多め | 3.5〜4.0km/h | 40分歩+15分休 | 水は小分け補給 |
| 真夏日 | 3.0〜3.5km/h | 30分歩+15分休 | 日陰優先、帽子必須 |
重量と中身を「数値で管理」する
参考装備重量(成人1人・夏の平地想定)
| 品目 | 重量目安 | 採用のコツ |
|---|---|---|
| 水 500ml×2 | 約1.0kg | 片側に寄せない、歩きながら片方ずつ消費 |
| 食(1日分) | 0.6〜0.8kg | 水なしで食べられる高密度食品 |
| 雨具(上下) | 0.3kg | 薄手・透湿。ポンチョは風に弱い |
| 保温具(軽量上着) | 0.3kg | 圧縮袋で小型化 |
| 充電(小型蓄電+線) | 0.25kg | 予備線1本のみ。乾電池機器と揃える |
| 灯り(頭用+手持ち) | 0.2kg | 頭用を主灯、手持ちは予備 |
| 救急・衛生 | 0.25kg | 服薬と絆創膏、圧迫止血材を中心に |
| 簡易トイレ×3 | 0.18kg | 個包装で配布しやすく |
| 敷物(薄手シート) | 0.1kg | 断熱が効くタイプ |
| 紙類・現金 | 0.05kg | 連絡カード・小銭・身分証の写し |
| 合計 | 約3.2〜3.8kg | ここに季節物を加減 |
想定距離別の水量(初期携行の目安)
| 距離 | 夏(30℃) | 春秋(15〜25℃) | 冬(0〜10℃) |
|---|---|---|---|
| 〜2km | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 〜5km | 1.0L | 0.5〜0.75L | 0.5L |
| 10km前後 | 1.5L | 1.0L | 0.75L |
「一日の行動例」と消費量の見積もり
| 時間帯 | 行動 | 水の消費 | 食の消費 |
|---|---|---|---|
| 朝 | 退避開始・歩行 | 250ml | 非常食1/3 |
| 昼 | 日陰で休憩 | 300ml | 非常食1/3 |
| 夕 | 到着・整頓 | 200ml | 非常食1/3 |
| 夜 | 体温維持・就寝 | 100ml | 予備(状況次第) |
点検と入替の周期(年間カレンダー)
- 毎月:賞味期限・電池残量・背負いテスト10分
- 季節の変わり目:夏冬モジュールの入替
- 年度替わり:連絡先・家族構成の更新、服薬見直し
- 大掃除のついで:重量実測と総量表の更新
家族別チェックリスト(抜粋)
| 項目 | 大人 | 高齢者 | 子ども | 乳幼児同伴 |
|---|---|---|---|---|
| 重量が上限の8割以下 | □ | □ | □ | □ |
| 水と食の1日分 | □ | □ | □ | □ |
| 服薬・診察券 | — | □ | — | □(親も) |
| 連絡カード | □ | □ | □ | □ |
| 笛・灯り | □ | □ | □ | □ |
| 反射材(夜間識別) | □ | □ | □ | □ |
Q&A(よくある疑問を短く解決)
Q1.「少し重いけど慣れれば平気」でもいい?
A.不可。 非常時は階段や段差、暑さ寒さが加わる。平時の楽さ=非常時の最小条件と考え、上限の8割に落とす。
Q2.水は多いほど安心では?
A.重さで歩けなくなれば本末転倒。初期は最小限+補給手段が基本。行き先の給水地点を地図に書く。
Q3.家族で歩く速度が合わない。
A.隊列を縦に短く保ち、角で待つ。重い共同装備は体力のある人、軽い品は子どもと役割を分ける。
Q4.ベビーカーか抱っこか迷う。
A.段差が多い道は抱っこひも+ヒップシート。平坦路はベビーカー+軽量荷が楽。途中で持ち替えできる設計に。
Q5.腰痛持ちで背負うのが不安。
A.胸・腰ベルトで荷重分散し、上限をさらに−1〜2kg。歩行テストで痛みゼロが合格ライン。
Q6.雨の日の装備は重くなる?
A.重くなりがち。 ただし雨具は薄手で良い。替え靴下と防水袋を足すほうが効果的。
Q7.眼鏡・補聴器の予備は入れる?
A.入れる。 軽量で効果が大きい。小型の硬いケースで破損を防ぐ。
用語辞典(やさしい言い換え)
非常持出袋:家から出るときに最初に持つ最小の袋。
上限(重量上限):無理なく歩ける重さの天井。体重や距離で決める。
補給:途中や到着地で水や食を足すこと。
モジュール:用途ごとに小分けしたまとまり。入替が楽になる。
歩行テスト:家の周りで実際に歩いて試すこと。痛みや息切れの確認。
圧縮袋:衣類などの空気を抜いて小さくする袋。
反射材:光を返して夜間でも見えやすくする布やテープ。
まとめ
非常持出袋の重量上限は、体重の10%を基本に、距離・段差・気温で安全側に下げるのが要点だ。持つものを三層に分け、共同装備を分担し、歩行テストで仕上げる。家族それぞれの上限を表と数値で見える化すれば、非常時でも足が止まらない。今日、体重と距離を入れて自分の上限を数字で決めるところから始めよう。