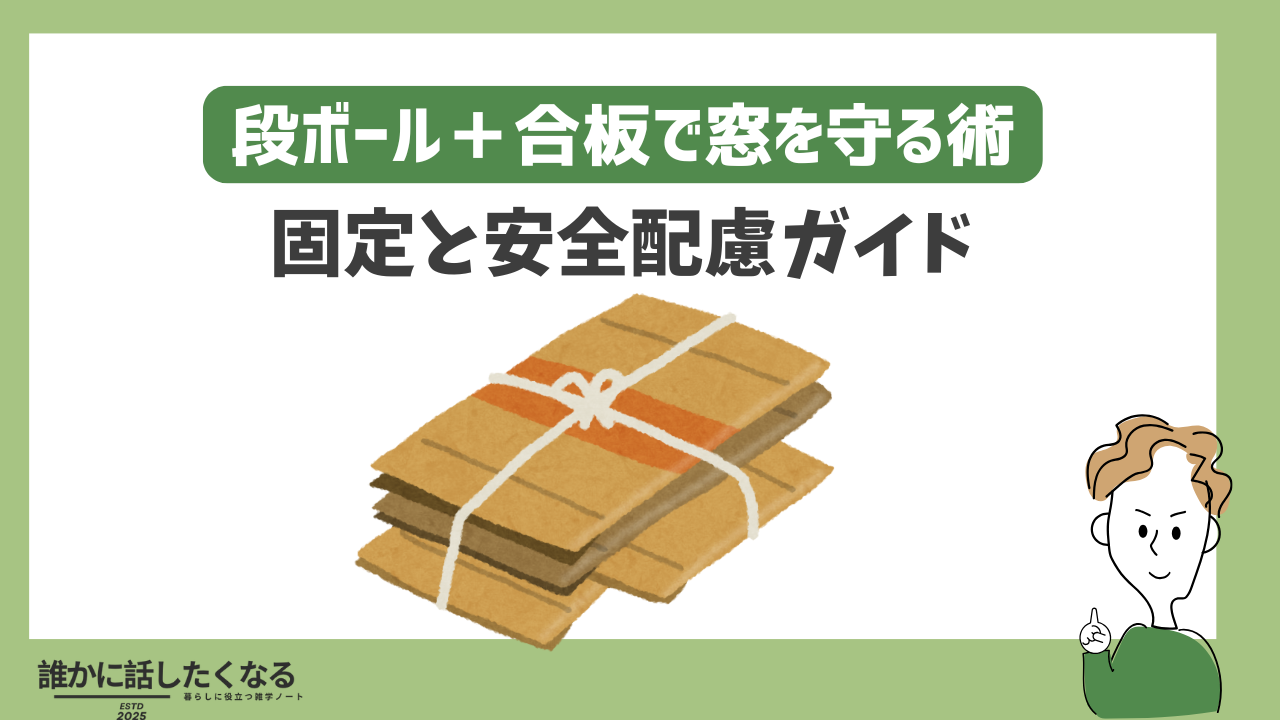台風や突風、飛来物による割れから窓ガラスを守るには、段ボールと合板を賢く組み合わせて、短時間で強い面を作り、家の躯体に無理をかけない固定が肝心である。ビニールや新聞紙の貼り付けでは破片の飛散は抑えにくい。
この記事は、厚み・重ね方・固定点の設計を具体的な数値で示し、賃貸でも傷を残しにくい方法から持ち家の本格対策まで段階別に整理した。さらに採寸〜設置の手順、やってはいけない例、チェックリスト、Q&A、用語辞典まで網羅し、初めてでも迷わず再現できる内容に仕上げている。
まず決めるのは「厚みと重ね方」|段ボールと合板の役割分担
段ボールの役割:衝撃の緩衝と破片止め
段ボールは空気層を持つ波形構造で、初期衝撃を面に散らし、割れた破片の飛散を内側で受け止める。二重〜三重に重ねて波目を直交させると強度が大きく上がる。縁だけが薄いと点圧で抜けやすいので、全面を同じ層数にそろえるのが基本だ。
合板の役割:面で受け止める盾
合板は一枚で剛性を確保する盾。目安は針葉樹合板9mm以上、飛来物が想定される窓は12mmを推奨。軽量化したい場合は5.5mm+段ボール多層でも一定の保護が得られるが、看板片・瓦片などを想定するなら9mm以上を基準にする。
重ね方の基本:柔→硬→柔で点圧を避ける
室内側から**(壁)→段ボール→合板→段ボール(室内側)の順で“サンド”すると、硬い板の縁の点圧がガラスへ直撃しない。縁には帯状の緩衝材(ゴム5〜10mm)**を貼っておくとさらに安心だ。
厚みと重ね方の早見表
| 想定リスク | 段ボール | 合板 | 推奨構成 | ひと言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 雨風・軽い飛来物 | 2層 | 5.5mm | 段(窓側)→合板→段(室内側) | 小窓・高所に向く |
| 看板片・枝など | 2〜3層 | 9mm | 段→合板→段+縁に緩衝材 | 掃き出し窓の標準 |
| 小石・瓦片など | 3層 | 12mm | 段→合板→段+内側に段1層 | 角部の補強を厚めに |
材料の選び分け(合板・OSB・樹脂板)
- 針葉樹合板:軽めで扱いやすい。9〜12mmが主力。
- OSB:面剛性は十分だが縁のささくれに注意。縁のやすり掛け+テープ巻きで安全性を上げる。
- 樹脂中空板(プラ段):単体では弱いが段ボールの代替やひさしの補助に便利。
固定の設計|家を傷めず、吸排気や避難を妨げない
窓種ごとの固定ポイント
- 引き違い窓:縦枠・下枠が強い。中央の桟に力を集中させないよう、面で押さえる。
- はめ殺し窓:枠が細いことが多い。**内装側の壁下地(間柱)**を探し、L金具で受けを作って面を支える。
- 出窓:上面の天板と左右側板で受ける構造に。天板の下地を探し、吊り下げ+下受けで落下を防ぐ。
穴あけ不要の固定(賃貸向け)
- つっぱり棒+ベルト:窓枠左右の壁面に太めのつっぱり棒を立て、ラチェットベルトで合板を面として押える。角部にはゴム板を挟み点圧を拡散。過締めは禁物。
- 養生テープ+面ファスナー:枠や壁に養生テープを下貼り→その上に面ファスナー受け→合板側にフックを貼り、段ボール+合板の一体パネルを面で支持する。高温多湿で粘着力が落ちるため、補助の突っ張りを併用すると安定。
本格固定(持ち家向け)
- 間柱へのビス止め:下地探しで柱位置を特定し、座金付きビスでL金具→合板の順に固定。配線・配管の位置に注意する。
- 上部吊り下げ+下部受け:上に吊り金具、下に受け材を設け、レール状に出し入れ。避難用の一枚だけは軽量化しておくと良い。
固定方法の比較表
| 方法 | 固定力 | 原状回復 | 費用感 | 施工の難易度 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| つっぱり棒+ベルト | 中 | 容易 | 低〜中 | 低 | 過締め不可、角にゴム当て |
| 養生テープ+面ファスナー | 低〜中 | 容易 | 低 | 低 | 夏場の粘着低下、補助必須 |
| 間柱ビス+L金具 | 高 | 困難 | 中〜高 | 中 | 下地位置を確実に、電線回避 |
| 吊り下げ+下受け | 中〜高 | 中 | 中 | 中 | 金具強度・ビス長さを確認 |
風・換気・吸排気の配慮
換気口や給気ガラリ、給湯器の排気をふさがない。室外機の吹き出し方向も確保する。避難に使う窓はワンタッチで外せる構造を優先し、固定位置に取り外しメモを貼っておく。
施工手順の実際|採寸→裁断→仮止め→本固定
1. 採寸と材料取り
窓の見付け幅・高さを測り、左右上下に10〜20mmの余白を取って板を切り出す。段ボールは波目が縦横直交になるよう2〜3枚準備。角部は面取りして手や壁を傷つけないようにする。
2. パネル化(屋内の床で作業)
床に段ボール→合板→段ボールの順で重ね、四隅と中央を両面テープ+短いタッカーで仮固定。縁に帯状のゴム板を貼り、ガラスとの間に緩衝を作る。持ち手用の紐穴を室内側上辺に一か所開け、紐を結ぶと脱着が容易。
3. 仮合わせと逃げの確認
窓前で仮合わせし、取っ手・クレセント錠・吸気口・配線などの干渉部を確認。必要に応じて逃げの切り欠きを設け、窓の開閉・避難動線を確保する。上下左右の水平を確認し、指1本分の逃げを保つと歪みに強い。
4. 本固定と増し締め
選んだ方法で上下左右の4点以上をバランスよく留める。ベルトは対角に2本が基本。中央にたわみが出ないよう軽く増し締めする。ベルトの食い込みには**角当て(ゴム・ベニヤ片)**を必ず挟む。
5. 仕上げと表示
避難に使う窓には取り外し手順をA6メモで貼付。暗闇対策として蓄光テープを持ち手の近くに貼る。保管袋(大きめのゴミ袋や布袋)を一緒に用意すると撤去後の片付けが速い。
施工の所要時間の目安
| 施工規模 | 人数 | 目安時間 | 材料例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小窓 1か所 | 1人 | 30〜45分 | 段2層+合板5.5〜9mm | 初回は+10分見込む |
| 掃き出し窓 1か所 | 1〜2人 | 60〜90分 | 段2〜3層+合板9〜12mm | ベルト2本・角当て必須 |
| 3か所セット | 2人 | 2〜3時間 | 同上 | 作業台・のこぎりが有効 |
追加設計|掃き出し窓の二枚割り・扉式・保管
掃き出し窓の二枚割りパネル
大板が重い場合は縦半分の二枚割りにして、中央で桟を跨ぐ形にする。上下2点+左右2点の計6点で支持し、中央は共締め用の短いベルトを追加するとたわみが出にくい。
扉式(可動)パネルの作り方
片側を吊り下げ金具で回転軸にし、反対側をフック金具で固定すれば、平時に開け閉めできる。ただし暴風時の開閉は不可。通気は別の小窓で確保する。
片付け・保管のコツ
パネルは壁に立て掛けると反るので、床で平置きが理想。難しい場合は2点以上で水平吊り。段ボール面が湿ったら風通しの良い場所で完全乾燥させてから保管する。
安全配慮とやってはいけない例|家電・換気・避難の確保
窓まわりの設備に配慮
換気口や給気ガラリをふさぐと二酸化炭素が上昇する。最小限の通風を確保し、台風通過中は火気を避ける。室外機前、給湯器排気、浴室乾燥の排気など熱や排気の通り道は必ず空ける。
やってはいけない固定
- ガラスへ直接ガムテープでバッテン:破片止め効果は限定的で、剥がし跡の糊が厄介。
- 枠の見切り材だけにビス:割れ・反りの原因。**下地(間柱)**に効かせること。
- 全面ビニール密閉:結露で木枠が傷む。湿気抜きの隙間を確保する。
- 過度な過締め:ガラスに点圧が掛かり、破損の恐れ。緩衝材を挟み、均一に締める。
賃貸の原状回復ポイント
穴あけ不可の場合はつっぱり+ベルトや面ファスナーで対応。テープは必ず養生テープを下貼り。退去時に糊残りを出さないよう、低粘着タイプを選ぶ。
生活動線と停電への備え
懐中電灯・軍手・はさみを窓そばに常備。把手位置に蓄光テープを貼り、暗闇でも外せるようにする。避難に使う窓の一枚は軽量パネルにしておくと安心。
コストと重量の目安|準備量を見積もる
| 材料 | 参考価格帯 | 1枚あたり重量(約) | 再利用性 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 合板5.5mm(910×1820) | 2,000〜3,000円 | 約4.5kg | 中 | 小窓や内側サンド向け |
| 合板9mm(910×1820) | 3,000〜4,500円 | 約7.5kg | 高 | 掃き出し窓の標準 |
| 合板12mm(910×1820) | 4,000〜6,000円 | 約10kg | 高 | 飛来物多い地域向け |
| 段ボール(大判) | 無料〜500円/枚 | 軽量 | 低〜中 | 多層・直交で強度UP |
| つっぱり棒(太) | 1,500〜3,000円/本 | 1〜2kg | 高 | ベルトと併用で安定 |
| ラチェットベルト | 1,000〜2,000円/本 | 300g | 高 | 角当てを必ず併用 |
| ゴム板(5〜10mm) | 500〜1,500円/枚 | — | 高 | 点圧拡散・すき間調整 |
タイムライン&チェックリスト|前日〜通過後
前日(30〜60分)
- 採寸→材料カット、角の面取り。
- 段ボール・合板を仮組みし、緩衝材を帯状に貼る。
- 排気・換気の通路を確認し、塞がない位置を決める。
直前(20〜40分)
- 仮合わせ→逃げの切り欠きを入れる。
- つっぱり+ベルトまたは金具で本固定。対角で2本が基本。
- 取り外しメモ・蓄光テープを貼る。
通過後(20〜40分)
- 湿気を逃がすため一旦取り外し、乾いた場所で保管。
- 枠や壁の跡・汚れを確認し、早めに拭き取り。
- 次回に向け不足物資をメモし、保管場所を家族で共有。
Q&Aと用語辞典|迷いをなくす最後の確認
Q&A(よくある疑問)
Q1.段ボールだけでも効果はある? 軽い衝撃の緩和と破片止めには有効だが、飛来物対策には合板併用が必須。最低でも5.5mm、推奨は9mm以上。
Q2.外側に付けた方が守れる? 基本は内側。外側は風雨で剥がれやすく落下の危険。内側なら破片の室内飛散も抑えられる。
Q3.合板の代わりに発泡スチロールは? 面剛性が不足。段ボール+発泡材+合板の中間層としてなら可だが、主材にはできない。
Q4.貼ってからも窓は開けられる? 扉式に作れば可能。ただし暴風時は開閉しない。通気は別窓で確保する。
Q5.養生テープで壁紙がはがれない? 下にマスキングを貼り、端からゆっくり。ドライヤーの温風で糊が剥がれやすくなる。
Q6.湿気で段ボールがへたらない? 室内側の乾燥を保ち、通過後は速やかに外して乾かす。長期連用は避け、再利用時は反りとカビを確認。
Q7.二重サッシでも必要? 外側ガラスの破片飛散を抑えるため、外側に近い面で保護すると効果的。ただし換気・排気は必ず確保。
Q8.地震にも役立つ? 破片止めとしては有効。重量物の落下には効果が限定的なので、別途の家具固定を併用する。
用語辞典(やさしい言い換え)
段ボール:波のある紙板。衝撃の緩衝・破片止めに使う。
合板:薄板を向きを変えて重ねた板。面の強さがある。
間柱:壁の中にある細い柱。ここへビスを効かせると強い。
座金:ビス頭の力を広く伝える円板。めり込み防止に使う。
つっぱり棒:床と天井や壁に押し当てて支える棒。穴あけ不要で使える。
緩衝材:ゴムやスポンジなど、点の力を面に広げる材料。
まとめ|柔と硬で面を作り、安全に固定する
窓を守る要点は、段ボールの柔らかさで衝撃を受け、合板の硬さで面強度を出し、家を傷めない固定で支えること。厚み・重ね方・固定点を数値で決め、換気・避難・表示の三点を忘れない。作ったパネルは再利用でき、次の荒天でも短時間で設置できる。家族で役割を決め、安全に外せる工夫まで用意しておけば、突風の日も落ち着いて備えられる。