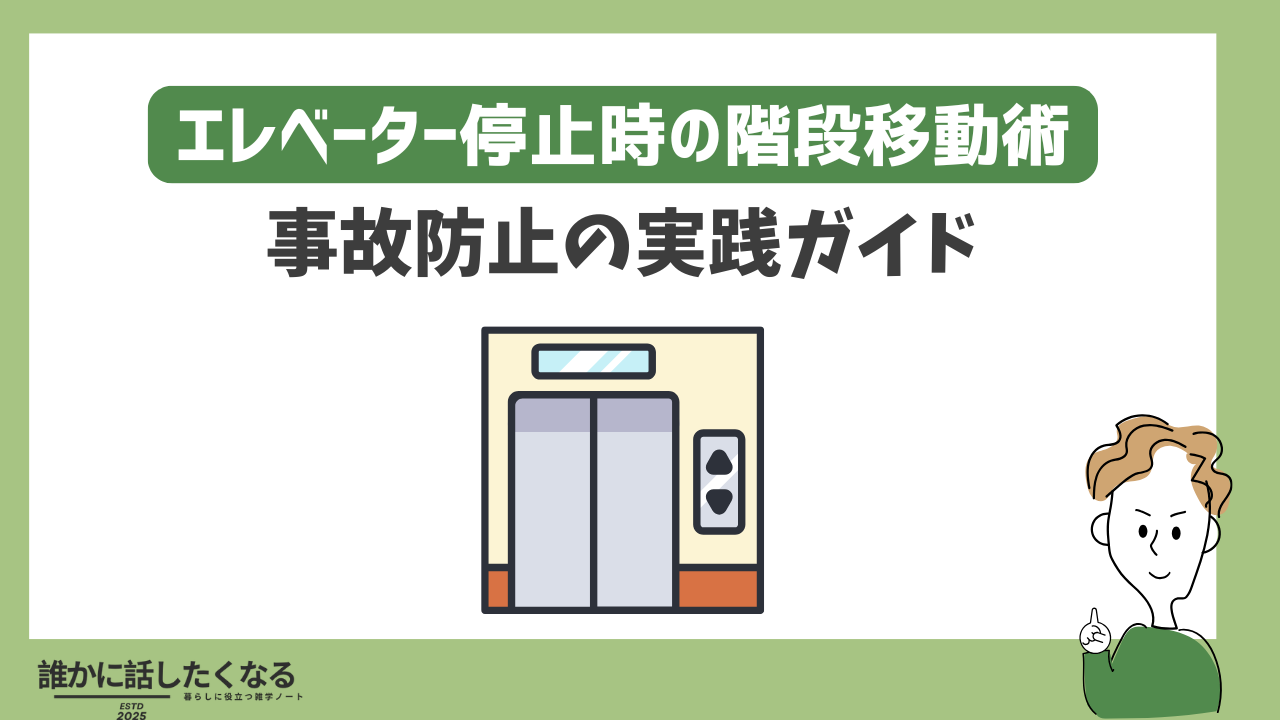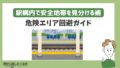止まった日こそ、落ち着いて“安全に上下する”。 停電・点検・混雑・地震や火災でエレベーターが使えないと、階段は唯一の動線になる。転倒・将棋倒し・踏み外し・荷物落下・体調急変を防ぐために、フォーム(上り/下り)→通行の作法→装備と服装→介助→ケース別対応を実地目線で体系化した。
まずは**「手すり・三点接触・半歩リズム」の型を体に入れ、段差と踊り場の見え方を整える。さらに体力差・服装差・施設差を前提に訓練プランとチェック表**まで用意した。
1.階段移動の基本設計:体の使い方と通行ルール
1-1.三点接触と半歩リズム(上り/下りの共通基礎)
- 三点接触:常に手すり+左右いずれかの足の3点を接地。足を出す前に手を置く。
- 半歩リズム:一段=半歩で小刻み。二段飛ばしは厳禁。
- 視線は3〜4段先。足元ばかり見ると頭が下がり転びやすい。
1-2.“通行は手すり優先”と列の作り方
- 右/左側通行のルールがあれば従う。ただし空いている手すり側を優先し手を離さない。
- 追い越し禁止が原則。抜く必要があるときは踊り場で声掛けしてから。
- 列は1列。肩が触れない距離=一段以上の間隔を保つ。止まるときは壁側へ。
1-3.“事前の一手”で事故を減らす
- 靴ひもを結び直す(緩さは指一本)。かかとを奥まで入れる。
- カバンは背負う(リュック)か体に密着。両手を空ける。
- 息が上がる前に休む:踊り場で5〜10秒、壁側に寄って水分一口。
基本フォーム・通行ルール 早見表
| 項目 | ルール | 理由 |
|---|---|---|
| 接触 | 手すり+足の三点 | 転倒時の支点を確保 |
| 歩幅 | 半歩(小刻み) | 踏み外しを抑える |
| 追越 | 原則禁止 | 将棋倒しの起点を作らない |
| 休憩 | 踊り場の壁側 | 流れを妨げない |
2.上りの技術:疲れにくい・踏み外さない
2-1.体重の載せ方(前傾すぎない)
- 胸から前ではなく“骨盤から前”へ。上体はわずか前傾、膝は曲げすぎない。
- 踏面の中央に足を置き、親指の付け根で押す。
2-2.手すりの使い方(引くより“置いて支える”)
- 強く引かない。体の倒れ込みを止める支点として軽く添える。
- カバンは反対側に持ち替え、手すり側の腕を自由に。
2-3.呼吸とペース配分(息切れ前に休む)
- 2段で吸う→2段で吐くの一定リズム。
- 階ごとに5〜10秒の小休止。息が弾む前に休む。
- 心拍サイン:会話が1文で切れるならペース落とす。
上りで効く“疲れない工夫”表
| 課題 | 兆候 | すぐ効く対策 |
|---|---|---|
| 太ももが重い | 歩幅が広がる | 半歩化・手すりで体幹安定 |
| 息が切れる | 肩で息をする | 2-2呼吸・壁側休憩 |
| 足裏が痛い | つま先立ち | 踏面中央を使う・靴紐調整 |
| 腰がつらい | 反り腰 | 骨盤前・上体わずか前傾 |
3.下りの技術:事故が多い“降り”を守る
3-1.体の位置(重心はやや後ろ)
- つま先から降りない。踵から静かに置く。
- 上体は直立、膝を軽く曲げて衝撃を吸収。
3-2.視線と足運び(3段先を見る)
- 視線は3〜4段先。段鼻(段の縁)をぼかすように見る。
- 手すりの握り直しは踊り場手前で行う。
3-3.“やってはいけない”を減らす
- 片手スマホ→止まって操作。
- 小走り→一段一歩に置き換え。
- 荷物偏り→重い側を内側、手すり側の手を空ける。
下りの“転ばない”対策表
| 危険ケース | ありがちな行動 | 置き換える動作 |
|---|---|---|
| 駆け下り | 急ぎで速度UP | 一段一歩・踵から着地 |
| 片手スマホ | 目線が落ちる | 止まって操作・両手フリー |
| 荷物偏り | 体が傾く | 重い側を内側・手すり側の手を空ける |
| 子連れ | 手すりから離れる | 子は内側・手首を軽く保持 |
4.荷物・服装・視界:転倒を呼ばない準備
4-1.荷物の持ち方(両手を空ける)
- リュックが基本。肩掛けは短くして体に密着。
- 買い物袋は左右で分散。段鼻から出ない長物は斜めに。
4-2.靴と服装(滑らない・絡まない)
- 踵が固く反りにくい靴、溝3mm以上の底。
- 裾の長いコートは前を留める。
- 手袋で手すりに汗を残さない。
4-3.視界の確保(傘・フード・曇り)
- 傘は閉じる/水切りしてから階段へ。
- フードは視野を狭める。
- 眼鏡の曇り止めは出入口前に。
荷物・服装・視界 チェック表
| 項目 | NG例 | 正解例 |
|---|---|---|
| カバン | 片手下げ+反対手スマホ | リュックで両手フリー |
| 靴 | すり減った底 | 溝3mm以上・踵しっかり |
| 服 | 長い裾が遊ぶ | 前を留めて絡み防止 |
| 雨具 | 差したまま下り | しまう/斜め持ちで視界確保 |
5.介助・混雑・災害時:弱い人を先に通す設計
5-1.介助の基本(声掛け→位置→合図)
- 名乗って短く具体に:「内側手すり側から支えます」。
- 介助者=手すり側/被介助者=外側で二人三脚。
- 段替わりでは**「今から段です」**と声で合図。
5-2.ベビーカー・車いす(原則は階段に入れない)
- 可能ならエレベーター代替を待つ。やむを得なければ駅員・施設職員を呼ぶ。
- 二人以上で前後を支え、荷重は腰で受ける。
5-3.混雑時の流し方(将棋倒しを作らない)
- 1列固定・追い越し禁止。
- 転倒者が出たら即声掛けで列を止め、端に寄せる。
- 手すりなし側に体が寄らないよう間隔を保つ。
介助・混雑・災害時 早見表
| 場面 | 一言 | 配置 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 高齢者介助 | 「手すり側につきます」 | 介助者=内側 | 段替わりで声合図 |
| 子ども同行 | 「手すり握ってね」 | 子=内側 | 手首を軽くつかむ |
| 混雑 | 「止まります」 | 1列維持 | 追越禁止 |
| 災害 | 「壁側へ寄ります」 | 列を間引く | 将棋倒し回避 |
6.施設タイプ別の注意点:職場・駅・商業施設
6-1.オフィス・学校の階段
- 朝夕の一方向流が起きやすい。下り優先の時間帯は上りは壁側待機。
- 掲示物の直下は落下に注意。手すり側を選ぶ。
6-2.駅の階段
- 列の合流(ホーム→コンコース)が発生。踊り場での急停止を避け、表示に従う。
- 雨天は金属縁が滑りやすい。5cm内側を踵で使う。
6-3.商業施設・病院の階段
- 荷物・ベビーカーが混在。広い側を使い速度差を作らない。
- 香り・照明の演出で段鼻が見えにくいことがある。3段先視線を徹底。
施設別・危険ポイント表
| 施設 | 起きやすい事象 | 先手の一手 |
|---|---|---|
| オフィス/学校 | 一方向の波 | 壁側待機→流れが切れたら合流 |
| 駅 | 合流・金属縁の滑り | 5cm内側を踵着地・手すり優先 |
| 商業施設/病院 | 速度差・視界演出 | 広い側で速度合わせ・3段先視線 |
7.ケース別の“つまずき”対策:雨・雪・停電・視覚不良・煙
7-1.雨・雪で濡れた段(滑る段鼻)
- 段鼻(縁)から5cm内側を踵着地で使う。
- 手すり先行→足の順に。濡れ靴は拭く。
7-2.停電・薄暗がり(誘導灯の活用)
- 踊り場の誘導灯を次の目印に。スマホは止まって操作。
- 片手ライトよりヘッドライトが安全。
7-3.煙・におい(火災の疑い)
- 姿勢を低く、風上へ。手すり側の壁伝いに移動。
- 非常口表示をたどり、扉の向こうの煙も確認して進む。
ケース別・即効テク表
| 事象 | 危険 | 即効テク |
|---|---|---|
| 雨・雪 | 段鼻が滑る | 踵から静かに・5cm内側 |
| 停電 | 足元不明 | 誘導灯→次の踊り場へ |
| 煙 | 視界・吸入 | 低い姿勢・風上・壁伝い |
8.短時間で身につく訓練:週30分のミニプラン
8-1.平日5分×3本(基礎)
- 上り:半歩リズムで10段×3セット。
- 下り:踵着地で10段×3セット。
- 手すり:握る→離す→置くの支点感覚を練習。
8-2.週末15分(応用)
- 荷物3kgを背負って上り下り各3本。
- 雨用の靴で段鼻5cm内側の着地を反復。
8-3.月1チェック(実力確認)
- 2階分を会話が続くペースで上り下り。
- 靴底の溝と靴ひもの状態を確認・交換。
ミニ訓練・記録表(例)
| 日付 | 上り(本) | 下り(本) | 荷重 | 気づき |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 3 | 3 | 0kg | 息切れ前休憩が効いた |
| 10/8 | 3 | 3 | 3kg | 踵着地が安定 |
9.Q&A(よくある疑問)
Q1.急いでいる時、どこまでなら走っていい?
階段は走らないが答え。踊り場だけ小走りも、他者の進路変化で危険。時間に余裕を。
Q2.荷物が重い。下りが怖い。
重い側を内側に。手すり側の手を空ける。一段一歩・踵からに徹する。
Q3.ヒールや厚底靴の時は?
前足部が大きく出る靴はNG。片手で靴を脱ぎ、靴を手で持って降りる選択も。裸足は滑るので靴下を履く。
Q4.子どもが階段を怖がる
数える遊びでリズムを作る。「1・2で吸う、3・4で吐く」。手すり側を歩かせる。
Q5.杖を使っている
杖→足→足の順で三点接触。踊り場ごとに休憩し、ペースは人任せにしない。
Q6.めまい・息切れを感じた
壁側に寄って座り、深呼吸。同伴者がいれば連絡し、無理せず中断。
Q7.手すりが片側しかない
手すり側=内側を通行。対向者が来たら踊り場でやり過ごす。
10.用語辞典(やさしい言い換え)
三点接触:手すりと両足のうち二つ、合計三箇所が常に階段に触れている状態。
段鼻:階段の段の縁。滑りやすいので踏み外しに注意。
踊り場:階段の途中にある平らな場所。休憩や方向転換に使う。
踏面/蹴上:踏む面の奥行き/一段の高さ。
誘導灯:停電時にも点く避難を示す灯り。
内側/外側:手すり側/反対側のこと。安全度は内側が高い。
まとめ:階段は三点接触・半歩リズム・手すり優先。上りは骨盤から前・2-2呼吸、下りは踵から静かに・3段先を見る。荷物は両手を空け、混雑時は1列固定で追越禁止。雨・雪・停電・煙でも踊り場を次の目印に落ち着いて。週30分のミニ訓練で型を体に入れ、靴・荷物・視界の三点を整えれば、エレベーター停止の日でも安全に移動できる。